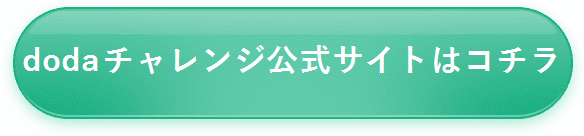dodaチャレンジで断られた!?断られた理由や断られる人の特徴について解説します
dodaチャレンジを利用しようと思っても、登録後に「求人を紹介できない」と断られてしまうケースがあります。
その背景には、希望条件の厳しさやサポート対象外の事情など、いくつかの共通した要因があります。
利用者にとってはショックに感じることもありますが、断られる理由を知っておくことで事前に対策をとり、次の行動につなげることができます。
例えば条件を柔軟に見直す、経験を積んでから再挑戦する、就労移行支援を活用するなど、改善できる手段はいくつもあります。
ここでは、dodaチャレンジで断られる代表的な理由と、その特徴について具体的に解説していきます。
断られる理由1・紹介できる求人が見つからない
dodaチャレンジでは、希望条件に合う求人が見つからない場合に「紹介が難しい」と断られることがあります。
特に「在宅勤務限定」「フルフレックス」「年収500万円以上」といった条件を設定すると、求人の幅が極端に狭くなり、現実的に紹介できる案件が減ってしまいます。
また、希望職種や業種が限られすぎている場合も注意が必要です。
例えば、クリエイティブ系やアート系など一部の専門職は求人自体が少なく、地方などエリアが限定されるとさらに難しくなります。
断られる背景には「条件が厳しすぎるために候補がゼロになってしまう」という単純な事情があることが多いです。
条件を少し広げることで紹介の可能性が大きく広がるため、柔軟さを持つことが大切です。
希望条件が厳しすぎる(在宅勤務限定、フルフレックス、年収500万円以上など)
希望条件を細かく設定しすぎると、それに該当する求人がほとんど存在せず、結果として紹介不可となる場合があります。
在宅勤務限定や高年収などの条件は魅力的ですが、求人数が限られることを理解しておく必要があります。
希望職種や業種が限られすぎている(クリエイティブ系、アート系など専門職など)
専門性が高い職種を希望する場合、そもそも求人が少なくなる傾向があります。
特にクリエイティブやアート系は都市部に集中しており、地方ではほとんど募集が見つからないこともあります。
勤務地が限定的(地方で求人自体が少ない)
勤務地を狭く限定してしまうと、そもそも求人が見つからない場合があります。
地方では障がい者雇用の求人数が少なく、結果的に紹介できる案件がゼロになってしまうのです。
断られる理由2・サポート対象外と判断される場合
dodaチャレンジは障がい者雇用の支援を専門とするサービスであるため、サポート対象に該当しないと判断された場合には求人を紹介してもらえないことがあります。
例えば、障がい者手帳を持っていない場合は、原則として障がい者雇用枠での求人紹介ができません。
また、長期間のブランクがあり職務経験がほとんどない場合も「すぐの就労が難しい」と判断されることがあります。
さらに、体調が不安定で安定した就労が難しい場合には、まずは就労移行支援を勧められることもあります。
断られたとしても「一切サポートが受けられない」というわけではなく、状況に応じて別の支援機関を案内してもらえる可能性があります。
焦らずに次のステップを考えることが大切です。
障がい者手帳を持っていない場合(障がい者雇用枠」での求人紹介は、原則手帳が必要)
障がい者雇用枠を利用するには障がい者手帳の所持が原則必要となるため、持っていない場合は求人紹介が難しくなるケースがあります。
長期間のブランクがあって、職務経験がほとんどない場合
ブランクが長いと即戦力として判断されにくく、求人の紹介が制限されることがあります。
職業訓練や就労移行支援を経てからの再挑戦が勧められることもあります。
状が不安定で、就労が難しいと判断される場合(まずは就労移行支援を案内されることがある)
体調や生活リズムが安定していないと判断されると、すぐの就労ではなく支援機関での準備を優先するよう案内される場合があります。
断られる理由3・面談での印象・準備不足が影響する場合
面談はアドバイザーが求職者の状況を理解し、求人紹介につなげる大切な機会です。
しかし、準備不足のまま臨むと「何を希望しているのかが伝わらない」「障がい内容や配慮事項が説明できない」「職務経歴が曖昧」という印象を与えてしまい、結果的に求人紹介につながりにくくなる場合があります。
印象は第一歩で大きく影響するため、表情や声のトーン、姿勢なども意識して臨むことが大切です。
事前にどのような仕事をしたいのか、どの条件が必須で、どこに柔軟性があるのかを整理しておくと、自分の考えをスムーズに伝えることができます。
アドバイザーはその情報を基に求人を選ぶため、情報が不足しているとマッチングの幅も狭まってしまいます。
準備を丁寧に整え、誠実な態度で臨むことが、求人紹介につながる大きなポイントです。
障がい内容や配慮事項が説明できない
障がいの内容や職場で必要な配慮をうまく伝えられないと、アドバイザーはどの企業を紹介すればよいか判断できなくなります。
難しいことを詳細に説明する必要はありませんが、自分が働くうえでどんな工夫をしているのか、どんなサポートがあると安心できるのかをシンプルに伝えることが重要です。
どんな仕事をしたいか、ビジョンが曖昧
「とにかく何でもいい」という姿勢では、逆に求人が見つかりにくくなることがあります。
アドバイザーは希望を基に求人を紹介するため、ビジョンが曖昧だと紹介数が限られてしまいます。
業種や職種の方向性、働き方の希望をある程度示しておくことが必要です。
職務経歴がうまく伝わらない
これまでの経験やスキルを伝えられないと、アドバイザーが強みを理解できず、求人紹介につなげにくくなります。
事前に職務経歴書を整理して、どんな業務を経験し、どんな成果を出したのかを具体的に話せる準備をしておくと安心です。
断られる理由4・地方エリアやリモート希望で求人が少ない
求人紹介がスムーズに進まない理由として、地方エリアや完全在宅勤務のみを希望している場合が挙げられます。
dodaチャレンジは全国対応のサービスですが、地域によって求人数に大きな差があり、特に北海道や東北、四国、九州といった地方では都市部と比べて求人が限られる傾向があります。
また、完全在宅勤務に限定して希望していると、さらに選択肢が狭まってしまいます。
企業側も在宅勤務を認めるには環境整備やセキュリティの面で制約があるため、求人数が限られてしまうのです。
そのため、地方や在宅にこだわる場合は、条件の優先順位を整理し、一部は通勤可能範囲を広げる、在宅と出社を組み合わせるなど柔軟性を持つことが紹介数を増やすコツです。
アドバイザーと相談しながら条件を調整すれば、より多くの選択肢を得られる可能性が広がります。
地方在住(特に北海道・東北・四国・九州など)
地方に住んでいる場合、都市部に比べて求人が少ない傾向があります。
希望条件をそのままにすると紹介数が限られるため、通勤範囲を広げたり在宅併用の可能性を検討したりすることが有効です。
完全在宅勤務のみを希望している場合(dodaチャレンジは全国対応ではあるが地方によっては求人がかなり限定される)
完全在宅勤務は魅力的ですが、企業の受け入れ体制が限られているため求人数は少なくなりがちです。
在宅勤務と出社を組み合わせる形を検討することで、紹介される求人の幅を広げることができます。
断られる理由5・登録情報に不備・虚偽がある場合
dodaチャレンジでは、正確な情報をもとに求人紹介やマッチングを行っているため、登録情報に不備や虚偽があると利用を断られることがあります。
例えば、障がい者手帳をまだ取得していないのに「取得済み」と記載してしまったり、実際には働ける状況にないのに無理に登録してしまうケースなどです。
こうした誤った情報は、本人だけでなく企業やアドバイザーにも不利益を与えてしまう可能性があるため、慎重に避ける必要があります。
また、職歴や経歴に偽りがある場合も信頼を大きく損ない、今後のサポートを受けにくくなる原因になります。
サービスを最大限活用するためには、正しい情報を正直に登録することが大切です。
多少のブランクや経験不足があっても、アドバイザーは状況に合ったサポートをしてくれるので、無理に取り繕う必要はありません。
手帳未取得なのに「取得済み」と記載してしまった
障がい者手帳をまだ取得していないのに、誤って「取得済み」と入力してしまうと、企業への紹介時に大きなトラブルになる可能性があります。
手帳の有無は雇用区分を決定する重要な条件であるため、正確に記載することが必要です。
取得予定であれば、その旨を正直に伝えておくことが安心です。
働ける状況ではないのに、無理に登録してしまった
体調や生活リズムが安定しておらず、働くことが難しい状況で無理に登録してしまうと、就職活動自体がうまく進まないことがあります。
その結果、紹介を断られることにつながることもあります。
まずは医師や支援機関と相談し、安定して働ける準備を整えてから登録することが大切です。
職歴や経歴に偽りがある場合
職歴や経歴を偽って登録すると、企業面接や入社時に必ず矛盾が発覚してしまいます。
虚偽の記載は信用を失うだけでなく、最悪の場合は内定取消につながるリスクがあります。
ブランクや短期間の職歴があっても、正直に記載することでアドバイザーが適切なサポートをしてくれるため、正確さを優先することが重要です。
断られる理由6・企業側から断られるケースも「dodaチャレンジで断られた」と感じる
dodaチャレンジの利用中に断られたと感じる理由のひとつに、企業側の選考結果があります。
求人紹介を受けて応募しても、不採用になることは当然ながらありますが、これはdodaチャレンジが断っているのではなく、企業が自社の選考基準に基づいて判断しているものです。
経験やスキルが条件に合わない場合や、他の候補者との比較によって結果が分かれることもあります。
不採用が続くと「サービス側から断られている」と誤解しがちですが、実際には選考の過程で起こる自然な結果です。
大切なのは結果に一喜一憂するのではなく、アドバイザーと一緒に改善点を確認し、次の応募につなげる姿勢です。
履歴書や職務経歴書の見直し、面接練習、希望条件の調整を行うことで、次のチャンスをつかみやすくなります。
不採用は企業の選考基準によるもの
不採用の判断は企業ごとに異なる基準で行われるため、必ずしも自分の能力が否定されているわけではありません。
求めるスキルや経験に合わなかっただけというケースも多いため、気持ちを切り替えて次の応募に挑むことが大切です。
アドバイザーと相談して改善点を把握すれば、次の選考で良い結果につながる可能性があります。
dodaチャレンジで断られた人の体験談/どうして断られたのか口コミや体験談を調査しました
体験談1・障がい者手帳は持っていましたが、これまでの職歴は軽作業の派遣だけ。PCスキルもタイピング程度しかなく、特に資格もありません。紹介できる求人がないと言われてしまいました
体験談2・継続就労できる状態が確認できないため、まずは就労移行支援などで安定した就労訓練を』と言われてしまいました。
体験談3・精神疾患で長期療養していたため、10年以上のブランクがありました。dodaチャレンジに相談したものの、『ブランクが長く、就労経験が直近にないため、まずは体調安定と職業訓練を優先しましょう』と提案されました
体験談4・四国の田舎町に住んでいて、製造や軽作業ではなく、在宅でのライターやデザインの仕事を希望していました。dodaチャレンジからは『ご希望に沿う求人はご紹介できません』といわれました
体験談5・これまでアルバイトや短期派遣での経験ばかりで、正社員経験はゼロ。dodaチャレンジに登録したら、『現時点では正社員求人の紹介は難しいです』と言われました
体験談6・子育て中なので、完全在宅で週3勤務、時短勤務、かつ事務職で年収300万円以上という条件を出しました。『ご希望条件のすべてを満たす求人は現状ご紹介が難しいです』と言われ、紹介を断られました
体験談7・精神障がい(うつ病)の診断を受けていますが、障がい者手帳はまだ取得していませんでした。dodaチャレンジに登録を試みたところ、『障がい者手帳がない場合は求人紹介が難しい』と言われました
体験談8・長年、軽作業をしてきたけど、体調を考えて在宅のITエンジニア職に挑戦したいと思い、dodaチャレンジに相談しました。『未経験からエンジニア職はご紹介が難しいです』と言われ、求人は紹介されませんでした
体験談9・身体障がいで通勤も困難な状況で、週5フルタイムは無理。短時間の在宅勤務を希望しましたが、『現在ご紹介できる求人がありません』と断られました
体験談10・前職は中堅企業の一般職だったけど、今回は障がい者雇用で管理職や年収600万以上を希望しました。dodaチャレンジでは『ご紹介可能な求人は現在ありません』と言われました
dodaチャレンジで断られたときの対処法について詳しく紹介します
dodaチャレンジを利用しようと登録しても、必ずしも全員がすぐにサポートを受けられるわけではありません。
スキル不足や職歴不足、あるいは長期のブランクがある場合には、現時点ではサポートの対象外と判断されることもあります。
しかし、断られたからといって転職や就職を諦める必要はありません。
むしろ、断られた理由を客観的に見つめ直すことで、自分に必要な準備や改善点がはっきりし、次の挑戦に活かせるチャンスになります。
スキルを磨く、資格を取得する、生活リズムを整える、短時間から働く実績を積むといった工夫を積み重ねれば、数か月後、数年後に改めて再挑戦できる可能性は十分にあります。
ここでは、よくあるケースごとに現実的な対処法を詳しく紹介しますので、自分に合った方法を取り入れて前向きに進めていきましょう。
スキル不足・職歴不足で断られたとき(職歴が浅い、軽作業や短期バイトの経験しかない、PCスキルに自信がないなど)の対処法について
スキルや職歴が十分でないと判断されて断られるケースは珍しくありません。
特に職歴が浅く、軽作業や短期アルバイトのみの経験であったり、PCスキルに自信が持てない場合は、まず「基礎力をつけること」が大切です。
ハローワークの職業訓練を利用すれば、WordやExcel、データ入力などのスキルを無料または低額で学ぶことができ、就職活動に直結する力を養えます。
さらに、就労移行支援を活用すれば、ビジネスマナーや面接練習、メンタル面のサポートも受けられるため、社会人としての総合力を高められます。
資格取得も効果的で、MOSや日商簿記3級などの資格を取ることで求人紹介の幅が広がり、自信を持って再挑戦できます。
断られたことを前向きに捉え、自分を成長させる準備期間に変えることが成功への近道です。
ハローワークの職業訓練を利用する/ 無料または低額でPCスキル(Word・Excel・データ入力など)が学べる
ハローワークが提供する職業訓練は、就職に必要なPCスキルを基礎から学べる貴重な機会です。
WordやExcelを中心に、文書作成や表計算、データ入力といった業務で必須となるスキルを体系的に習得できます。
多くのコースは無料または低額で受講でき、失業給付と併用できる制度もあります。
資格取得支援がセットになっていることも多く、修了後には実務で使える知識を備えられます。
職歴不足を補うためにも、まずは訓練を受けて「できること」を増やすことが、再度登録や応募に挑戦する際の大きなアピールポイントになります。
就労移行支援を活用する/実践的なビジネススキル、ビジネスマナー、メンタルサポートも受けられる
就労移行支援は、障がいのある方が一般企業での就職を目指すために活用できるサービスで、実践的なトレーニングを受けられるのが特徴です。
PCスキルだけでなく、報連相や電話応対などのビジネスマナー、面接練習、履歴書の書き方など幅広く学べます。
また、日常的に通所することで生活リズムを整えられ、働く準備を実際の行動を通じて積み重ねることができます。
さらに、メンタル面でのサポートを受けられるため、不安が強い方でも安心して就職活動を進められます。
こうした取り組みは、アドバイザーに対して「就職準備が整っている」という前向きなアピールにつながります。
資格を取る/MOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級があると、求人紹介の幅が広がる
資格取得は自信を高めるだけでなく、求人紹介の幅を広げる強力な手段です。
特にPCスキルを証明するMOS資格や、経理や事務職で評価されやすい日商簿記3級は、実務に直結する資格として人気があります。
資格があることで「基礎能力を備えている」と客観的に示せるため、スキル不足と判断されていた人でも紹介されやすくなります。
また、資格取得に取り組む姿勢自体が「向上心のある人材」として評価されやすいため、就職活動において大きな強みとなります。
ブランクが長すぎてサポート対象外になったとき(働くことへの不安が強い、数年以上の離職や療養期間があるなど)の対処法について
長期のブランクがある場合、就職活動を始めても「継続して働けるのか」という不安が大きく評価に影響することがあります。
そのため、まずは「働けるリズムを取り戻すこと」が重要です。
就労移行支援を利用すれば、毎日の通所で生活リズムを整えながら就労訓練を受けられ、安定した実績を積むことができます。
また、いきなりフルタイムで働くのではなく、短時間のアルバイトや在宅ワークから始めて、少しずつ勤務時間を延ばしていく方法も効果的です。
さらに、企業実習やトライアル雇用に参加して現場経験を積めば、自信を回復できるだけでなく、再登録時に具体的なアピール材料として活用できます。
ブランクは不利に見えがちですが、工夫次第で前向きに変えていけるのです。
就労移行支援を利用して就労訓練をする/毎日通所することで生活リズムを整え、安定した就労実績を作れる
就労移行支援を活用することで、規則正しい生活リズムを取り戻し、安定した就労習慣を身につけられます。
毎日通所して訓練を受けることで、朝起きて出かける習慣がつき、体調管理の面でもプラスになります。
また、支援員や仲間と関わることで社会的スキルを磨ける点も大きなメリットです。
通所を続けることで「毎日通える」という実績ができ、それが企業にとって安心材料になります。
ブランクからの再スタートには、こうした段階的な取り組みがとても効果的です。
短時間のバイトや在宅ワークで「実績」を作る/週1〜2の短時間勤務から始めて、「継続勤務できる」証明をつくる
ブランクが長い方は、いきなりフルタイムで働くのは大きな負担になりがちです。
そこで、まずは週1〜2回、数時間のアルバイトや在宅ワークから始めて「働き続けられる」という実績を積むことが大切です。
継続して勤務できれば、次第に勤務時間を延ばすことも可能になりますし、アドバイザーや企業に対しても説得力のあるアピールになります。
小さな実績でも積み重ねることで自信につながり、次のステップに進みやすくなります。
実習やトライアル雇用に参加する/企業実習での実績を積むと、再登録時にアピール材料になる
企業実習やトライアル雇用は、実際の職場で経験を積める貴重な機会です。
ブランクがある人にとって「働ける」という証明を作るうえで非常に効果的です。
実習を通じて得られた経験や評価は、再登録や面接の際に強力なアピール材料となります。
さらに、実習先でそのまま採用につながるケースも少なくありません。
ブランクを逆に「準備期間」と捉え、実習を積極的に活用することで、将来的な可能性を広げることができます。
地方在住で求人紹介がなかったとき(通勤できる距離に求人が少ない、フルリモート勤務を希望しているなど)の対処法について
地方在住の方は、大都市圏と比べて求人数が少なく、希望条件に合う求人が見つかりにくいことがあります。
特に通勤できる範囲が限られている場合や、フルリモート勤務を希望している場合は紹介が難しいケースもあります。
そのようなときは、まず在宅勤務が可能な求人に目を向け、障がい者に特化した他のエージェント(atGP在宅ワーク、サーナ、ミラトレなど)を併用するのがおすすめです。
また、クラウドソーシングを活用してランサーズやクラウドワークスで実績を作るのも有効です。
さらに、地域の障がい者就労支援センターやハローワークに相談すると、地元ならではの求人情報を得られる可能性もあります。
視野を広げて情報を集めることで、選択肢を増やし、希望に近い働き方を実現できるチャンスにつながります。
在宅勤務OKの求人を探す/他の障がい者専門エージェント(atGP在宅ワーク、サーナ、ミラトレ)を併用
在宅勤務可能な求人は都市部以外に住んでいる方にとって大きな味方になります。
最近はリモート勤務を前提とした求人が増えており、障がい者向けの専門エージェントでも在宅ワークを紹介してくれるサービスがあります。
dodaチャレンジで見つからなくても、atGP在宅ワークやサーナ、ミラトレなどを併用すれば選択肢が広がりやすくなります。
複数のサービスを活用することで、自分の生活スタイルや体調に合った働き方を見つけやすくなり、安心して仕事に取り組める環境を整えられます。
クラウドソーシングで実績を作る/ランサーズ、クラウドワークスなどでライティングやデータ入力の仕事を開始
求人がなかなか見つからないときは、クラウドソーシングで小さな実績を積み重ねるのも効果的です。
ランサーズやクラウドワークスといったプラットフォームでは、ライティングやデータ入力、アンケート回答など初心者でも始めやすい仕事が多数あります。
報酬は少額からのスタートになりますが、継続して実績を積むことで「働き続けられる」という証明になり、今後の就職活動でアピール材料にできます。
オンラインで働く経験は在宅勤務を希望する際にも大きな強みになるので、将来につながる準備としてもおすすめです。
地域の障がい者就労支援センターやハローワークに相談する/地元密着型の求人情報が得られる場合がある
地方での就職活動では、地元の支援機関を活用することも重要です。
障がい者就労支援センターやハローワークでは、地域密着型の求人を紹介してもらえることがあり、全国的な求人サイトには出ていない情報が得られる場合もあります。
また、担当者が企業と直接つながっていることも多く、採用前に職場見学や体験を調整してもらえる可能性もあります。
地域のネットワークを活かすことで、自分の生活圏内で無理のない働き方を見つけられるチャンスが広がります。
希望条件が厳しすぎて紹介を断られたとき(完全在宅・週3勤務・年収◯万円など、条件が多いなど)の対処法について
条件が厳しすぎると、該当する求人が見つからず紹介が難しくなることがあります。
完全在宅勤務や週3日勤務、高い年収など複数の条件を同時に求めると、選択肢が極端に少なくなるのです。
その場合は、条件に優先順位をつけて「絶対に譲れない条件」と「できれば希望する条件」を切り分けることが大切です。
また、譲歩できる部分はアドバイザーに再提示し、勤務時間や勤務地、出社頻度を柔軟に見直すことで新しい求人が見つかりやすくなります。
さらに、最初は条件を緩めて経験を積み、スキルアップや実績を重ねてから理想の働き方を目指す「段階的なキャリアアップ」の考え方も有効です。
柔軟な姿勢を持つことで、長期的に理想の働き方に近づくことができます。
条件に優先順位をつける/「絶対譲れない条件」と「できれば希望」を切り分ける
すべての条件を同時に満たす求人は非常に少ないため、条件に優先順位をつけることが大切です。
例えば「在宅勤務は必須だが、週の勤務日数や勤務時間は柔軟に対応できる」といったように、譲れない条件と希望条件を明確に分けるとアドバイザーが求人を探しやすくなります。
優先順位を整理することで、自分にとって本当に必要な条件が見えてきて、現実的に応募できる求人が広がります。
譲歩できる条件はアドバイザーに再提示する/ 勤務時間、出社頻度、勤務地を柔軟に見直す
一度断られたとしても、条件を柔軟に見直せば紹介が可能になることがあります。
例えば完全在宅を希望していた場合でも「週1日は出社できる」、勤務時間を短時間から始められるなど、譲歩できる点をアドバイザーに伝えることで新しい求人が見つかる可能性が高まります。
勤務地も通勤時間を広げたり在宅併用を検討するなど、少し柔軟に考えることで選択肢が増えるのです。
段階的にキャリアアップする戦略を立てる/最初は条件を緩めてスタート→スキルUPして理想の働き方を目指す
最初から理想の条件にこだわりすぎると求人が見つかりにくくなります。
そのため、まずは条件を緩めてスタートし、経験を積んでから徐々に希望条件に近づけていく戦略が有効です。
例えば、最初は出社ありの仕事から始め、実績やスキルを積み重ねることで在宅勤務中心の仕事に移行していく流れです。
段階を踏んでキャリアアップしていけば、長期的に理想の働き方を実現することができるのです。
手帳未取得・障がい区分で断られたとき(障がい者手帳がない、精神障がいや発達障がいで手帳取得が難航している、支援区分が違うなど)の対処法について
dodaチャレンジを利用したいと思っても、障がい者手帳を持っていない、または区分が合わないことを理由に断られることがあります。
精神障がいや発達障がいの場合、手帳申請が難航することもあり、その時点では利用が難しいと判断されてしまうケースもあります。
しかし、これは最終的な拒絶ではなく「準備が整えば利用できる可能性がある」という意味合いが強いです。
まずは主治医や自治体の窓口に相談し、手帳の申請や取得が可能かどうかを確認してみましょう。
条件が揃えば精神障がいや発達障がいでも手帳を取得できます。
また、手帳がない場合でも、就労移行支援やハローワークで「手帳不要」の求人を探すことは可能で、一般枠での就職活動をしながら実績を積む方法もあります。
さらに、医師と相談して体調や治療を優先し、心身が安定した段階で再度登録に挑戦するのも良い選択肢です。
今は断られても、準備を整えれば将来再チャレンジできる道は開かれています。
主治医や自治体に手帳申請を相談する/ 精神障がい・発達障がいも条件が合えば取得できる
精神障がいや発達障がいであっても、一定の条件を満たせば障がい者手帳を取得できる可能性があります。
手帳の有無は就職活動に大きく影響するため、まずは主治医に相談し、診断書を準備したうえで自治体の窓口に申請する流れを確認しましょう。
取得には数か月かかることが多いですが、その間に体調を整えたりスキルを学んだりする時間として活用できます。
手帳を持つことで、障がい者雇用枠に応募できる幅が広がり、dodaチャレンジのような専門サービスも利用可能になります。
焦らず計画的に申請を進めることが大切です。
就労移行支援やハローワークで「手帳なしOK求人」を探す/一般枠での就職活動や、就労移行後にdodaチャレンジに戻る
手帳を取得していない状態でも、就労移行支援やハローワークを通じて「手帳なしOK」の求人を探すことができます。
一般枠で応募できる求人に挑戦して実績を積むのも良い方法で、短期間でも継続して働いた経験は次の就職活動で大きなアピール材料になります。
就労移行支援を利用してスキルを身につけたうえで再度dodaチャレンジに登録すれば、よりスムーズにサポートを受けられるようになります。
今できることを一歩ずつ積み重ねることが、将来の可能性を広げるカギになります。
医師と相談して、体調管理や治療を優先する/手帳取得後に再度登録・相談する
体調が安定していない状態で就職活動を進めると、働き始めても長続きしないリスクがあります。
そのため、まずは医師と相談しながら治療や体調管理を優先することが大切です。
しっかりと休養を取り、働ける準備が整った段階で手帳を申請すれば、その後の就職活動を安心して進められるようになります。
dodaチャレンジの登録は一度断られても再挑戦が可能です。
無理をせず、自分のペースで治療と準備を進め、次の機会に備えることが将来の安定した就労につながります。
その他の対処法/dodaチャレンジ以外のサービスを利用する
dodaチャレンジが利用できなかった場合でも、就職支援の選択肢は他にもあります。
就労移行支援やハローワークはもちろん、地域の障がい者就業・生活支援センターや民間の転職エージェントを活用することで、自分に合った求人やサポートを受けられます。
特に地域の支援機関は、医療機関や福祉サービスとも連携しているため、生活全体をサポートしてもらえる点が強みです。
また、一般的な求人サイトやクラウドソーシングを使って在宅ワークから始めるという方法もあります。
大切なのは「一つのサービスで断られても道は閉ざされない」ということです。
複数の選択肢を視野に入れ、自分に合った環境を見つける姿勢を持つことで、就職活動を前向きに進めていけます。
dodaチャレンジで断られた!?精神障害や発達障害だと紹介は難しいのかについて解説します
dodaチャレンジを利用したいと考えても、精神障害や発達障害を持っている方の中には「自分はサポートを受けられるのだろうか」「紹介は難しいのではないか」と不安を感じる方が多いです。
実際には、障がいの種類ごとに企業側の受け入れやすさや求人の傾向が異なります。
身体障害者手帳を持つ方は比較的紹介がスムーズに進むケースが多く、精神や発達障害の場合はサポート体制や配慮内容が明確でないと紹介が難しくなることがあります。
しかし、これは「不可能」という意味ではなく、どのように情報を整理し伝えるかによって十分に改善できる部分も多いです。
ここではまず、身体障害者手帳を持つ方の就職事情を整理し、そこから精神障害や発達障害の方が参考にできる視点を紹介します。
身体障害者手帳の人の就職事情について
身体障害者手帳を持つ方は、就職活動において比較的スムーズに求人が紹介される傾向があります。
理由の一つは、障がいの内容が「目に見える形」で伝わることが多く、企業が必要な配慮をイメージしやすいからです。
例えば、バリアフリー設備の整備や業務の一部制限など、合理的配慮を明確に設定しやすいため、採用側も安心して受け入れることができます。
特に等級が軽度の場合は一般職種への採用も多く、事務職やPCを用いた業務は求人の数も豊富です。
一方で、上肢や下肢の障がいが通勤や作業に直接影響する場合は、選べる求人が限られることもあります。
それでも、コミュニケーションに支障がなく、必要な環境整備が整えば幅広い職種にチャレンジできる可能性は十分にあります。
企業にとっても受け入れ準備が明確にできるため、身体障害者手帳を持つ方は比較的就職活動を進めやすい状況にあるといえます。
障害の等級が低い場合は就職がしやすい
身体障害者手帳を持つ方の中でも、等級が比較的軽度で日常生活や業務に大きな制約がない場合は、就職活動がしやすい傾向にあります。
企業にとって負担が少なく、本人の能力をそのまま活かしやすいためです。
応募できる求人の幅も広がり、面接でも自信を持って自分の強みをアピールしやすくなります。
身体障がいのある人は、障がいの内容が「見えやすい」ことから、企業側も配慮しやすく採用しやすい傾向にある
身体障がいは外見的にわかりやすいことが多いため、企業側も事前に配慮事項をイメージしやすいです。
その結果「この業務なら問題ない」という判断がスムーズにでき、採用に前向きになりやすい傾向があります。
お互いの理解が深まりやすく、就職後のミスマッチも少なくなるのが特徴です。
企業側が合理的配慮が明確にしやすい(例:バリアフリー化、業務制限など)から、企業も安心して採用できる
身体障がいの場合、バリアフリー化や一部業務の制限など、合理的配慮が比較的明確に示しやすいです。
企業にとって「どのようにサポートすればよいか」がわかりやすいため、安心して採用につなげられることが多いです。
結果として、身体障害者手帳を持つ方は求人紹介も進みやすくなります。
上肢・下肢の障がいで通勤・作業に制約があると求人が限られる
一方で、通勤や作業に直接影響する上肢や下肢の障がいがある場合は、応募できる求人が限定されるケースもあります。
例えば、移動の多い仕事や体力を使う業務は難しいことが多いです。
ただし、在宅勤務やデスクワークの求人を選べば、自分に合った働き方を見つけられる可能性は十分にあります。
コミュニケーションに問題がない場合は一般職種への採用も多い
身体障がいがあっても、コミュニケーションに問題がない場合は一般職種への採用も多くあります。
企業は配慮すべきポイントを明確にしつつ、業務上のやり取りに問題がなければ安心して受け入れやすいのです。
そのため、協調性や報連相のスキルをしっかり伝えることが就職活動の成功につながります。
PC業務・事務職は特に求人が多い
身体障がいのある方にとって、PCを使った業務や事務職は求人が豊富にあります。
座って作業できる環境が整いやすく、合理的配慮も明確にしやすいため、採用されやすいのです。
スキル次第では専門性の高い業務に携わることも可能で、自分の強みを活かしながら働くチャンスが広がります。
精神障害者保健福祉手帳の人の就職事情について
精神障害者保健福祉手帳を持っている人の就職活動では、症状の安定性や継続勤務のしやすさが重視されるのが特徴です。
精神障がいは外見からは分かりにくいため、企業側が「採用後にどのような対応が必要になるのか」を不安に感じることが少なくありません。
そのため、採用面接の際には、自分の特性を隠すのではなく、どのような配慮があれば働きやすいのかを前向きに伝えることがとても大切です。
例えば「定期的な通院のために月に一度は早退が必要」「静かな環境で集中力を発揮できる」といった具体的な配慮事項を伝えることで、企業は受け入れの準備をしやすくなります。
精神障がいがある人にとって、就職活動では「不安を与えない伝え方」と「安定した働き方の証明」が成功のカギになるのです。
症状の安定性や職場での継続勤務のしやすさが重視される
精神障害者保健福祉手帳を持つ人が採用される際には、特に「症状が安定しているかどうか」と「安定した勤務が可能かどうか」が重要視されます。
休職や離職を繰り返していると企業に不安を与えやすいため、できるだけ安定した生活リズムや服薬管理を整えてから就職活動に臨むことが大切です。
また、無理のない勤務日数や時間から始めることも定着率を高めるポイントです。
見えにくい障がいなので、企業が「採用後の対応」に不安を持ちやすいのが現実
精神障がいは外見から判断できないため、企業は「採用後にどのようなサポートが必要か」が分かりにくく、不安を抱くケースが多いです。
そのため、応募者が自分の特性や必要な配慮を整理して伝えることで、企業の不安を和らげることができます。
特に「こういう配慮があれば長く働ける」と前向きに説明することが信頼につながります。
採用面接での配慮事項の伝え方がとても大切!
面接の場で配慮事項を伝えるときは、できないことを強調するのではなく「こうすれば働きやすい」という形で伝えるのが効果的です。
例えば「繁忙期は体調に影響が出やすいので、残業は控えていただけると助かります」「指示は口頭よりも書面でいただけると確実です」といった具体的な例を挙げると、企業に安心感を与えやすくなります。
療育手帳(知的障害者手帳)の人の就職事情について
療育手帳を持つ人の就職事情は、手帳の区分によって大きく変わるのが特徴です。
A判定(重度)の場合は一般就労が難しいケースが多く、就労継続支援B型といった福祉的就労が中心になります。
一方で、B判定(中軽度)の場合は一般企業での就労も視野に入れることができ、軽作業や事務補助など幅広い選択肢が見込めます。
療育手帳のある人にとって大切なのは、自分の特性に合った職場を選び、無理なく長く働ける環境を整えることです。
企業側も支援機関と連携しながら雇用を進めるケースが多いため、サポート体制を利用して安心して就職活動を進めることができます。
療育手帳の区分(A判定 or B判定)によって、就労の選択肢が変わる
療育手帳は区分によって受けられるサポートや就労可能な職種に違いがあります。
A判定では福祉的就労が中心となり、B判定では一般就労の可能性が広がります。
そのため、自分の判定に合った選択肢を理解することが、安心して働く第一歩です。
A判定(重度)の場合、一般就労は難しく、福祉的就労(就労継続支援B型)が中心
A判定の場合は、一般企業での就労が困難なケースが多く、福祉施設での就労が中心になります。
就労継続支援B型では、自分のペースで作業できるため、無理なく働き続けられる環境を得やすいのが特徴です。
B判定(中軽度)の場合、一般就労も視野に入りやすい
B判定の人は、軽作業や事務補助などの職種で一般企業に就職することが可能です。
支援機関と連携しながら就職活動を進めることで、安心して職場に定着できるケースが多くあります。
障害の種類と就職難易度について
障がい者手帳の種類によって、就職の難易度や適した職種には大きな違いがあります。
身体障害の場合は配慮事項が比較的明確で、事務やIT系の仕事に就きやすい傾向があります。
精神障害の場合は症状の安定と継続勤務のしやすさが評価されやすい一方で、企業が不安を抱きやすく難易度が上がることもあります。
知的障害に関しては、区分によって一般就労が可能な場合と、福祉的就労が中心となる場合に分かれます。
このように障害の種類ごとに特徴が異なるため、自分の特性を理解し、適した就労環境を探すことが大切です。
以下の表は種類ごとの就職のしやすさや職種の傾向をまとめたものです。
| 手帳の種類 | 就職のしやすさ | 就職しやすい職種 | 難易度のポイント |
| 身体障害者手帳(軽度〜中度) | ★★★★★★ | 一般事務・IT系・経理・カスタマーサポート | 配慮事項が明確で採用企業が多い |
| 身体障害者手帳(重度) | ★★ | 軽作業・在宅勤務 | 通勤や作業負担によって求人が限定 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | ★★ | 事務補助・データ入力・清掃・在宅ワーク | 症状安定と継続勤務が評価されやすい |
| 療育手帳(B判定) | ★★★★ | 軽作業・事務補助・福祉施設内作業 | 指導・サポート体制が整った環境で定着しやすい |
| 療育手帳(A判定) | ★★ | 福祉的就労(A型・B型) | 一般就労は難しく、福祉就労が中心になる場合が多い |
障害者雇用枠と一般雇用枠の違いについて
障害者雇用枠と一般雇用枠には、それぞれ特徴や前提条件があり、自分に合った働き方を選ぶうえで理解しておくことがとても大切です。
障害者雇用枠は、障害者雇用促進法に基づき企業が用意している枠組みで、障害をオープンにして働くことを前提としています。
そのため、配慮事項を明確に伝えることで、自分に合った環境で働ける可能性が高いです。
一方、一般雇用枠は障害の有無に関わらず応募できる採用枠で、すべての応募者が同じ条件で競うことになります。
障害を開示するかどうかは本人の自由であり、クローズ就労として進める人もいます。
ただし、一般枠では特別な配慮が前提にないため、体調や環境面でのサポートを求めるのが難しいこともあります。
それぞれの違いを正しく理解し、自分の状況や希望に合った雇用枠を選ぶことが安心して働くための第一歩です。
障害者雇用枠の特徴1・企業が法律に基づき設定している雇用枠
障害者雇用枠は、障害者雇用促進法に基づいて企業が設けている特別な採用枠です。
企業は一定数以上の障がい者を雇用する義務があるため、法律に沿って専用の求人を用意しています。
この枠で採用された場合、勤務内容や働き方に配慮がなされるケースが多く、体調や障害特性に応じた働き方を実現しやすいのが特徴です。
応募の際には障害者手帳の有無や配慮事項の確認が行われ、本人の状況に合わせたマッチングが進められます。
安心して働くための環境を整えやすいのが大きなメリットです。
障害者雇用枠の特徴2・障害者雇用促進法により、民間企業は従業員の2.5%以上(2024年4月〜引き上げ)を障がい者として雇用するルールがある
障害者雇用枠は、法律で義務付けられている雇用率に基づいて設けられています。
2024年4月からは、民間企業は従業員の2.5%以上を障がい者として雇用する必要があります。
この数値は段階的に引き上げられてきており、今後も社会全体で障害者雇用の拡大が進められていく方針です。
このように法的に定められているため、企業は積極的に障害者採用を行っており、就職を希望する側にとっても選択肢が増えている状況です。
制度を理解したうえで活動すれば、自分に合った企業と出会える可能性が高まります。
障害者雇用枠の特徴3・障害をオープンにし配慮事項を明確に伝えた上で雇用される
障害者雇用枠で働く場合は、障害をオープンにして就職活動を進めることが前提となります。
企業には配慮事項を伝えることができ、働くうえで必要なサポートや環境整備を受けやすいのがメリットです。
例えば通院配慮や勤務時間の調整、作業環境の工夫など、安心して働くための仕組みが整えられることが多いです。
オープンにすることで不安を感じる人もいますが、その分企業とのミスマッチが減り、自分に合った環境で長く働ける可能性が高まります。
一般雇用枠の特徴1・障害の有無を問わず、すべての応募者が同じ土俵で競う採用枠
一般雇用枠は、障害の有無に関わらず誰でも応募できる採用枠です。
応募者全員が同じ基準で評価されるため、スキルや経験、即戦力としての能力が重視されます。
そのため、障害者雇用枠に比べて選考基準が厳しい場合もありますが、条件が合えば高待遇の仕事に就ける可能性もあります。
特別な配慮を前提としていないため、体調や働き方の調整が難しい場合がありますが、自分の力を試したい人にとっては挑戦の機会となる採用枠です。
一般雇用枠の特徴2・障害を開示するかは本人の自由(オープン就労 or クローズ就労)
一般雇用枠では、障害を開示するかどうかは本人の選択に委ねられています。
障害をオープンにして配慮をお願いする「オープン就労」も可能ですが、特に伝えずに応募して働く「クローズ就労」を選ぶ人もいます。
クローズで働く場合は、周囲に障害のことを伝えないためサポートが受けにくい反面、自分のスキルだけで評価されるメリットもあります。
どちらを選ぶかは、自分の体調や環境、希望する働き方に合わせて考えることが重要です。
一般雇用枠の特徴3・基本的に配慮や特別な措置はないのが前提
一般雇用枠では、特別な配慮や措置を前提としていないことが多いです。
そのため、障害に合わせた勤務時間の調整や通院配慮、特別なサポートを求めるのは難しいケースがあります。
しかし、自分の力を発揮して一般枠で働ける自信がある人にとっては、やりがいやキャリアアップの可能性が広がります。
自分がどの環境で力を発揮しやすいかを冷静に考え、必要な配慮があるかどうかを踏まえて選択することが大切です。
年代別の障害者雇用率について/年代によって採用の難しさは違うのか
障害者雇用の状況は年代によって大きく異なり、採用のしやすさや求人の傾向も変わってきます。
厚生労働省の障害者雇用状況報告(2023年版)によれば、20代や30代は全体の半数近くを占めており、未経験からの就職や転職がしやすい環境が整っています。
一方で40代以降は職歴やスキルの有無が採用に大きく影響し、未経験から新しい職種に挑戦するのは難しくなる傾向があります。
さらに50代以上になると求人数自体が少なくなり、経験を活かせる特定の業務や短時間勤務、嘱託雇用などに限定されるケースが増えます。
年代によってチャンスの広がり方が変わるため、自分の年齢に合わせた戦略を立てることが重要です。
若い世代は幅広い求人に積極的に挑戦し、中高年層はこれまでの経験や強みを明確にアピールすることが成功につながります。
障害者雇用状況報告(2023年版)を元に紹介します
2023年の障害者雇用状況報告によると、20代は全体の約20~25%を占め、初めての就職や未経験可の求人が多く見られます。
30代は25~30%と割合が高く、経験を活かした安定就労を目指す転職が中心です。
40代は20~25%で、職歴やスキルがある人は幅広く選べますが、未経験からの挑戦は厳しめです。
50代は10~15%と減少し、経験者採用や特定業務に限られることが多くなります。
60代は約5%で、短時間勤務や嘱託雇用が中心となっています。
このように年代ごとに採用の状況が変化しており、若い世代ほど選択肢が広い一方、中高年はこれまでの経験や専門性を武器にしていくことが重要だといえます。
| 年代 | 割合(障害者全体の構成比) | 主な就業状況 |
| 20代 | 約20~25% | 初めての就職 or 転職が中心。未経験OKの求人も多い |
| 30代 | 約25~30% | 安定就労を目指す転職が多い。経験者採用が増える |
| 40代 | 約20~25% | 職歴次第で幅が広がるが、未経験は厳しめ |
| 50代 | 約10~15% | 雇用枠は減るが、特定業務や経験者枠で採用あり |
| 60代 | 約5% | 嘱託・再雇用・短時間勤務が中心 |
若年層(20〜30代)の雇用率は高く、求人数も多い
20代から30代は障害者雇用において最も求人が多く、採用率も比較的高い世代です。
新卒や既卒の就職活動が活発で、企業側もポテンシャル採用として未経験者を受け入れる姿勢を持っていることが特徴です。
キャリアを積むスタート地点として、幅広い職種に挑戦できるチャンスがあるため、積極的に応募することが大切です。
また、経験が浅くても「今後の成長に期待して採用する」というケースが多いため、柔軟に学ぶ姿勢を示すことが重要です。
若いうちにさまざまな経験を積むことで、その後のキャリア形成が有利になり、40代以降の就職活動にもつながっていきます。
40代以降は「スキル・経験」がないと厳しくなる
40代になると、求人数自体はまだ一定数ありますが、未経験から新しい分野に挑戦するのは難しくなります。
この年代では、これまでの経験やスキルがどれだけあるかが採用のカギを握ります。
たとえば、事務職での経験や専門資格、リーダー経験などがあれば強みとして活かせますが、そうした実績がない場合は採用が難航する傾向があります。
そのため、40代での就職活動では、スキルの棚卸しを行い、自分の強みを明確にしてアピールすることが欠かせません。
未経験分野に挑戦する場合は、就労移行支援や職業訓練でスキルを身につけてから再挑戦するのがおすすめです。
50代以上は「短時間勤務」「特定業務」などに限られることが多い
50代を超えると求人の数が大幅に減少し、フルタイムでの採用は難しくなります。
その代わり、短時間勤務や特定の業務に特化した求人が中心になります。
これまでの経験を活かせる職種であれば採用される可能性はありますが、新しい分野に挑戦するのはさらに厳しくなる傾向があります。
企業側は体力面や継続勤務の安定性を重視するため、自分の健康管理や働ける時間を具体的に示すことが求められます。
50代以上での就職活動では、無理に広く応募するよりも、自分の経験やスキルに合った求人を見極めて効率的に応募することが成功のポイントです。
dodaチャレンジなどの就活エージェントのサービスに年齢制限はある?
dodaチャレンジのような障がい者特化型の転職エージェントには、公式には年齢制限は設けられていません。
そのため、20代から60代まで幅広い年代が登録して利用できます。
ただし、実際の求人の多くは若年層から50代前半までをターゲットとしており、それ以降の年齢になると紹介できる案件が減少するのが現実です。
とはいえ、年齢に関係なく経験やスキルがあれば活躍できる可能性は十分にあります。
そのため、年齢を理由に諦めるのではなく、自分の強みをアピールできる準備を整えておくことが大切です。
さらに、エージェントだけでなくハローワークの障がい者窓口や障がい者職業センターを併用することで、より幅広い求人情報を得られるため、選択肢を広げる工夫が必要です。
年齢制限はないが 実質的には「50代前半まで」がメインターゲット層
dodaチャレンジでは年齢制限は設けられていませんが、紹介される求人の多くは50代前半までを中心としています。
これは企業側が長期的な就労を見込んで採用を行うことが多いためです。
50代後半以上になると求人数が少なくなり、短時間勤務や嘱託雇用が中心となる傾向があります。
ただし、豊富な経験や専門知識があれば採用される可能性は十分にあるため、自分の経歴を整理して強みを前面に出すことが大切です。
実際に50代以上で就職している人もいるので、年齢に臆せずに挑戦してみる価値はあります。
ハローワーク障がい者窓口や障がい者職業センター(独立行政法人)も併用するとよい
年齢層が上がるにつれて求人の選択肢は狭まる傾向がありますが、ハローワークの障がい者窓口や障がい者職業センターを併用すれば選択肢を増やせます。
これらの機関は地域の企業と強くつながっているため、エージェントでは扱っていない求人を紹介してもらえることもあります。
また、就労に向けた訓練やセミナー、実習の機会が用意されているため、スキルを補いながら就職活動を進められるのもメリットです。
特に50代以降は、民間エージェントと公共機関を組み合わせて利用することで、自分に合った求人を見つけやすくなります。
dodaチャレンジで断られたときの対処法についてよくある質問
dodaチャレンジの口コミや評判について教えてください
dodaチャレンジの口コミや評判は、障がいのある方が安心して利用できる就職支援サービスとして全体的に高く評価されています。
特に専任のキャリアアドバイザーによる丁寧な対応や、障がいの特性に合わせた求人提案がある点に安心感を持つ方が多いです。
一方で「希望条件に合う求人が少なかった」「紹介までに時間がかかった」という声もあり、求人状況や地域差によって満足度は変わる傾向があります。
それでも「履歴書や職務経歴書の添削が役立った」「面接の練習をしてもらえて自信につながった」というポジティブな意見が多く、総じて利用価値が高いと感じている人が多いのが特徴です。
障がい者雇用に特化しているからこそ得られる安心感が、口コミでの高評価につながっています。
関連ページ:dodaチャレンジの口コミは?障害者雇用の特徴・メリット・デメリット
dodaチャレンジの求人で断られてしまったらどうすれば良いですか?
dodaチャレンジの求人で断られたとしても、それは就職活動における一つの通過点であり、今後の改善につなげるチャンスと考えることが大切です。
断られる理由はスキル不足や経験不足、求人側の条件に合わなかったなど様々ですが、まずはアドバイザーにフィードバックを求め、自分に足りなかった点を知ることから始めましょう。
その上で、必要に応じて資格を取得したり、就労移行支援でスキルを補強したりすることで次のチャンスを広げることができます。
また、複数の求人に応募して並行して進めることで、一つの結果に左右されず前向きに活動できるのも大事なポイントです。
断られた経験は決して無駄ではなく、今後の成功につながるステップと考えて取り組むことが成功の近道になります。
関連ページ:dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談
dodaチャレンジで面談後に連絡なしの理由について教えてください
dodaチャレンジで面談を受けたあとに連絡が来ない場合、不安に感じる人は少なくありません。
理由としては、求人のマッチングに時間がかかっている、応募が集中して処理が遅れている、あるいはメールが迷惑フォルダに振り分けられているなど、いくつかの可能性が考えられます。
また、登録内容に不足があり確認に時間を要している場合もあります。
数日待っても進展がない場合は、遠慮せずにアドバイザーに問い合わせることが大切です。
状況を確認することで安心できますし、次の行動に移しやすくなります。
連絡が途絶えたと感じても、ほとんどの場合は一時的な遅れであり、対応を待つより積極的に確認する姿勢が解決につながります。
関連ページ:dodaチャレンジから連絡なしの理由と対処法/面談・求人・内定それぞれのケースと連絡なしの理由
dodaチャレンジの面談の流れや聞かれることなどについて教えてください
dodaチャレンジの面談では、まずこれまでの職務経験やスキル、そして希望する働き方について詳しくヒアリングが行われます。
障がいの内容や必要な配慮事項についても確認されるため、事前に整理しておくとスムーズです。
面談はオンラインや電話でも行われ、アドバイザーが一人ひとりに合った求人を提案してくれます。
また、履歴書や職務経歴書の確認、今後の選考に向けたアドバイスも受けられるため、準備不足を補えるのが大きなメリットです。
質問内容は難しいものではなく、安心して答えられるよう工夫されています。
面談を通じて自分の強みや課題が明確になり、就職活動の方向性が固まるきっかけになることが多いです。
関連ページ:dodaチャレンジの面談から内定までの流れは?面談までの準備や注意点・対策について
dodaチャレンジとはどのようなサービスですか?特徴について詳しく教えてください
dodaチャレンジは、障がいのある方の就職や転職を専門にサポートしている人材紹介サービスです。
一般的な転職サービスと異なり、障がい特性に応じた配慮やサポートを前提とした求人を紹介してもらえるのが大きな特徴です。
キャリアアドバイザーが一人ひとりの状況に合わせて面談を行い、希望条件や配慮事項を聞き取ったうえで、最適な求人を提案してくれます。
また、履歴書や職務経歴書の添削、面接練習、入社後の定着支援など、きめ細かいフォローを受けられる点も安心できるポイントです。
求人は事務職や技術職、営業補助など幅広く揃っており、特に大手企業の障がい者雇用求人を扱っているケースが多いのも魅力です。
就職活動に不安がある方でも、専門的なサポートを受けながら安心して進められるサービスです。
障がい者手帳を持っていないのですが、dodaチャレンジのサービスは利用できますか?
障がい者手帳を持っていなくても、場合によってはdodaチャレンジのサービスを利用できることがあります。
公式には障がい者手帳の所持が前提とされていますが、医師の診断書や支援機関からの証明書があれば、登録が認められることもあります。
特に、精神疾患や発達障がいなどで診断を受けていても、まだ手帳を取得していない方が相談できるケースがあります。
利用を希望する場合は、登録フォームで状況を詳しく記入し、初回面談でアドバイザーに正直に伝えることが大切です。
今後手帳を取得する可能性がある方は、アドバイザーと相談しながら進めると、将来的な選択肢も広がります。
手帳がなくても一歩踏み出すことで、自分に合ったサポートを受けられるきっかけになるのです。
dodaチャレンジに登録できない障害はありますか?
dodaチャレンジでは、障がいの種類によって登録を制限することは基本的にありません。
身体障がい、精神障がい、知的障がい、発達障がい、難病など幅広い人が対象となっています。
ただし、医療的ケアが常に必要で就労自体が難しい場合や、就労意欲が全く確認できない場合には登録が認められないケースがあります。
また、就労経験がなくても登録は可能ですが、生活リズムが安定していない場合には、まずは就労移行支援などを案内されることもあります。
つまり、障がいの種類そのものが理由で断られることは少なく、働く意欲や準備状況が登録の可否に影響するのです。
自分の状況が不安な場合は、まずアドバイザーに相談してみると安心です。
dodaチャレンジの退会(登録解除)方法について教えてください
dodaチャレンジを退会する方法はシンプルで、マイページからの操作か、担当アドバイザーに直接依頼する方法があります。
マイページからは「登録解除」や「退会申請」といった項目を選び、手続きを進めれば退会が可能です。
もし操作が難しい場合やわからない場合は、問い合わせ窓口にメールで依頼しても対応してもらえます。
ただし、進行中の案件や選考中の求人がある場合には、アドバイザーに確認してから退会を進めることが望ましいです。
退会後は登録情報が削除されるため、再登録を検討する場合には履歴書や職務経歴書を保存しておくと安心です。
手続き自体は難しくないので、安心して利用開始できるサービスといえます。
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングはどこで受けられますか?
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングは、主にオンラインまたは電話で受けることができます。
自宅にいながら面談を受けられるため、通院や移動に負担を感じる方でも利用しやすいのがメリットです。
また、首都圏や主要都市に住んでいる方は、オフィスに訪問して対面面談を受けることも可能です。
カウンセリングでは、自分のスキルや職歴、障がいの内容や必要な配慮事項について相談でき、アドバイザーがそれに合わせて求人を提案してくれます。
就職活動に不安を感じている方でも、面談を通してサポートを受けることで安心感を持てます。
状況に応じて柔軟に対応してもらえるので、気軽に利用できる仕組みです。
dodaチャレンジの登録には年齢制限がありますか?
dodaチャレンジには明確な年齢制限は設けられていません。
新卒から中高年層まで幅広い年齢層の人が利用でき、ライフステージに合わせた求人を紹介してもらえます。
もちろん、求人によっては企業側が年齢を条件にしている場合もありますが、サービスそのものは年齢で制限されることはありません。
若年層の場合はポテンシャルを重視した求人、中高年層の場合は経験やスキルを活かした求人が紹介されることが多いです。
年齢に関係なく「就職したい」という意欲があることが何より大切で、その意欲を支えてくれる仕組みが整っています。
年齢で諦める必要はなく、幅広い層に対応しているのがdodaチャレンジの強みです。
離職中ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
離職中であっても、dodaチャレンジのサービスは問題なく利用できます。
むしろ就職活動に集中できる状況にあるため、キャリアアドバイザーと密に連携しながら活動を進めやすいメリットがあります。
離職期間が長い場合でも、その間に学んだことや生活の中で工夫したことを整理し、職務経歴書に盛り込むことで前向きにアピールできます。
また、アドバイザーからは「ブランクをどう伝えるか」について具体的なアドバイスをもらえるため、不安を抱えずに選考に臨めます。
離職中だからこそ時間を活かしてスキルアップや資格取得に取り組み、それを強みにして応募できるのも利点です。
離職中であることを不利に考える必要はなく、再スタートのチャンスとして活用できます。
学生ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
学生でも、卒業後の就職を見据えてdodaチャレンジを利用することは可能です。
特に就職活動を控えた大学生や専門学校生が、将来のために早めに準備を進めたい場合に適しています。
dodaチャレンジでは、求人紹介そのものは卒業後を前提としていますが、在学中に面談を受けることで、履歴書の書き方や面接対策のアドバイスを得ることができます。
また、自分の障がいに関する配慮事項を整理しておくことで、就職活動をスムーズに進めやすくなります。
アルバイトの紹介は行っていませんが、学生のうちからサポートを受けておくことで安心感を持って就職活動に臨めるでしょう。
学生にとっても将来を見据えた準備の一環として利用する価値の高いサービスです。
参照: よくある質問 (dodaチャレンジ)
dodaチャレンジは断られない?その他の障がい者就職サービスと比較
| 就職サービス名 | 求人数 | 対応地域 | 対応障害 |
| dodaチャレンジ | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| アットジーピー(atGP) | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| マイナビパートナーズ紹介 | 350 | 全国 | 全ての障害 |
| LITALICOワークス | 4,400 | 全国 | 全ての障害 |
| 就労移行支援・ミラトレ | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| ランスタッドチャレンジ | 260 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪 | 全ての障害 |
| Neuro Dive | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| Cocorport | 非公開 | 首都圏、関西、東海、福岡 | 全ての障害 |
dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談 まとめ
今回は、dodaチャレンジでの断られた経験についてご紹介しました。
断られた理由やその対処法、難しいと感じた体験について触れました。
結論として、断られたという経験は誰にでもあるものであり、それを乗り越えるためにはポジティブな姿勢が重要です。
断られた理由を受け入れることは、成長するために必要な一歩です。
その理由を冷静に分析し、改善点を見つけることが大切です。
また、断られたとしても諦めずに挑戦を続けることが成功への近道となります。
難しいと感じた体験も、自己成長や学びの機会と捉えることができるでしょう。
さらに、断られた経験から得られる教訓を次に活かすことも重要です。
過去の失敗や困難を振り返り、今後のチャレンジに生かすことでより良い結果を得ることができます。
そして、周囲のサポートや助言を活用しながら、自分自身を成長させていくことが大切です。
断られることや難しい体験は誰にでもあるものですが、それを乗り越えて成長していくことが大切です。
ポジティブな姿勢を持ち、失敗や困難をチャンスと捉えることで、より良い未来に向かって歩んでいけるでしょう。
次のチャレンジに向けて、前向きな気持ちで取り組んでいきましょう!