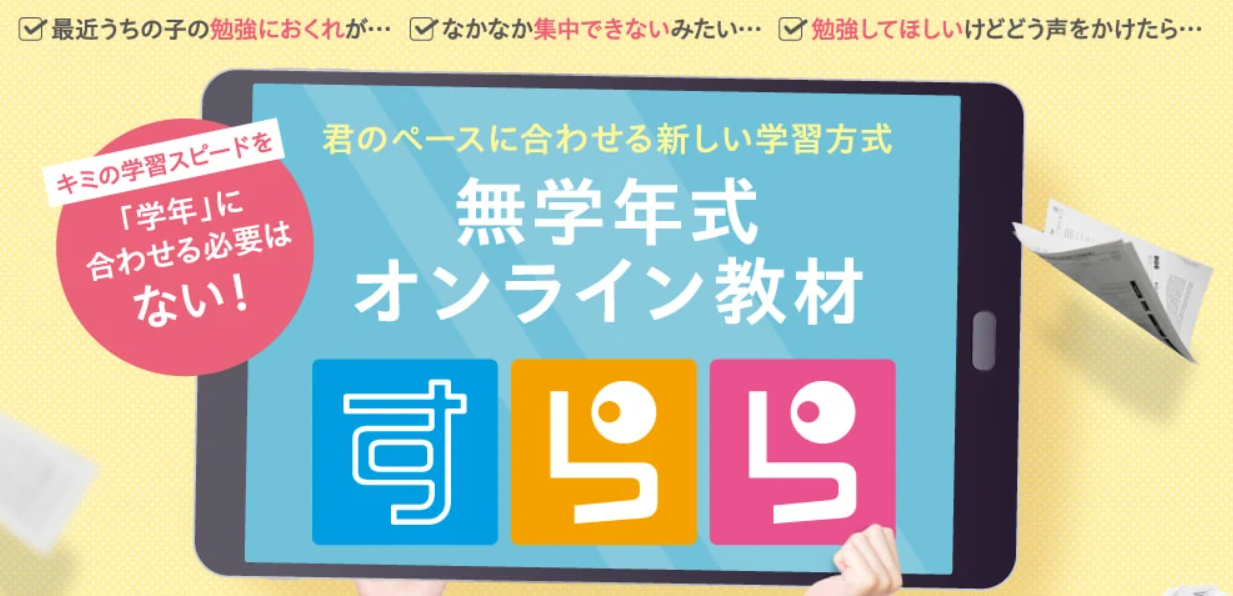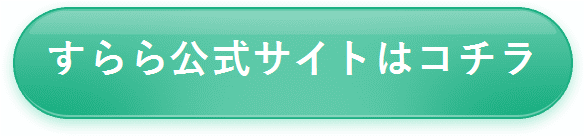すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について
すららは、不登校の子どもでも「出席扱い」になることがある学習教材として、多くのご家庭から注目されています。
出席扱いになるには、一定の条件をクリアする必要がありますが、そのポイントの一つが「学習内容の質」と「学習の継続性」、そして「学習記録が客観的に証明できること」です。
すららは、家庭で使う教材でありながら、まるで学校と同等、あるいはそれ以上の学習環境を提供してくれるため、多くの自治体や学校で出席扱いとして認められやすい傾向があります。
不登校で悩んでいるご家庭でも、「学びを止めずに進める」ことが可能なのは心強いですよね。
ここでは、なぜすららが出席扱いになるのか、その理由について詳しく見ていきます。
理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
すららが出席扱いとして認められる大きな理由の一つに、「学習の質」と「記録の透明性」があります。
自宅での学習だと「どれくらい勉強したのか分からない」と思われがちですが、すららではすべての学習データがシステムで管理されており、日々の取り組みや理解度が一目で分かるようになっています。
しかも、学習状況はグラフやレポートとしてまとめられるため、それを学校側に提出することで「この子はちゃんと学習を続けている」と客観的に伝えることができるのです。
このように、ただ勉強するだけでなく「見える学習」ができる点が、すららが学校からも評価される理由なんですね。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
すららでは、日々の学習内容や進捗が自動で記録されていき、そのデータをもとに詳細なレポートが生成されます。
このレポートは「誰が・いつ・どの単元を・どれくらい学習したか」が明確に記載されており、保護者が何か特別な手間をかけなくても、学校側にそのまま提出できる形式になっています。
紙のノートでは難しい「客観的な証明」が可能になることで、学校側としても「しっかりと家庭学習が行われている」と判断しやすくなります。
結果として「出席扱い」として認定されるケースが多いんですね。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい
すららの強みは、保護者が学習の進捗をいちいち記録しなくても、すべて自動的にデータ化されるという点です。
「勉強した時間」「正答率」「つまずいた単元」など、学習状況がリアルタイムで可視化されるため、保護者としても安心して見守ることができます。
この仕組みは学校側からも非常に評価されており、「信頼性のある学習」として扱われることが多いです。
手間なく、しっかりと「勉強している証明」ができるので、出席扱いを希望する際の提出資料としても非常に有効です。
不登校でも、学びを止めず、記録として残せるというのはとても心強いですね。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
すららの強みのひとつが、「コーチによる学習計画」と「継続のサポート」がセットで受けられる点です。
子どもによって学力や集中力、やる気の波はそれぞれ異なりますよね。
すららでは、その子にとって“ちょうどよい”学習スピードを見極め、無理のないプランを提案してくれる専任コーチがつきます。
このコーチがいることで、保護者はスケジュール管理の手間を大幅に減らすことができるんです。
さらに、すららの無学年式の仕組みと組み合わせることで、「得意はどんどん先に」「苦手はじっくり戻る」といった柔軟な対応が可能に。
続けることの難しさに直面してきたご家庭にとって、このサポートはまさに救世主のような存在かもしれません。
だからこそ、多くの保護者からも「安心して任せられる」と高く評価されているんです。
すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる
家庭学習でつまずきやすいのは、「今日は何をするか」が決まっていない状態。
そして、つい数日サボってそのままズルズル…という継続の難しさです。
すららでは、この2つを同時にクリアできるよう、専任コーチが学習計画を作成し、定期的に声かけやフォローをしてくれます。
子どもだけでなく、親にとっても心強い味方になってくれる存在なんです。
すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる
単に一度きりのプランを出して終わりではなく、すららのコーチは子どもの学習状況に応じて「継続的に」プランを調整してくれます。
体調やメンタルの浮き沈みにも柔軟に対応し、モチベーションが落ちた時期には声かけの工夫などもしてくれるから、長く続けられる子が多いのも納得ですね。
すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる
通常の教材だと「この学年の範囲だけ」という制限があるため、つまずくと取り返しにくいことも。
でもすららは学年に縛られず、戻り学習や先取り学習が自由にできる無学年式だから、子どもそれぞれの理解度に応じて柔軟に対応可能です。
焦らずマイペースに進める安心感があるのも魅力ですね。
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる
すららは単なるタブレット教材ではなく、家庭と学校、そしてすららの三者が連携しながら子どもの学びを支えるシステムを持っています。
たとえば、不登校や発達障害のあるお子さんにとっては、「出席扱い」や「個別支援計画」などが必要になることがありますよね。
そんなとき、保護者がすべての手続きを抱え込むのはとても大変です。
でもすららなら、必要書類の準備や学校とのやり取りまで含めて、きちんとフォローしてくれるんです。
専任コーチがレポートの書き方まで教えてくれたり、校長先生や担任の先生と円滑にやり取りできるようなアドバイスもしてくれたりと、本当に心強いパートナーになってくれます。
このような「人を巻き込んだ支援体制」があるからこそ、学校復帰を目指す家庭でも安心して取り入れられるんです。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
たとえば、「出席扱い」の手続きをするには、学校に提出する書類が必要ですが、すららではその書き方や手順を丁寧に教えてくれます。
保護者が初めてでも迷わないようにガイドをくれるので、「何から始めればいいかわからない」という不安を解消してくれます。
すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる
学習の記録を提出する際には、フォーマットの準備や記入例もコーチがサポートしてくれるため、提出までがスムーズです。
内容のアドバイスやチェックも受けられるから、「ちゃんと受理されるか心配…」という方も安心して任せられます。
すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる
「先生にどう説明したらいいかわからない」「学校と温度差がある気がして言いにくい」そんな悩みも、すららが間に入ってアドバイスしてくれることで、話しやすくなるんです。
保護者一人で悩むのではなく、すららの支援を活かすことで、学校との橋渡しがスムーズになりますよ。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは単なる家庭用タブレット教材ではなく、文部科学省にも「不登校支援教材」として正式に認められている数少ない学習サービスの一つです。
そのため、すららは全国の教育委員会や学校とも連携して導入が進められており、教育現場でも確かな信頼を得ています。
特に、不登校の子どもが学校に通えない間に自宅で学習を継続できるよう、無理なく取り組めるカリキュラムが組まれている点が評価されています。
「登校できない=学べない」ではなく、「その子に合った場所で学べる環境を整える」ことが大切であり、すららはその思いに寄り添って開発されています。
実際に、すららを使っているお子さんの中には、学習の遅れを取り戻し、自信をつけて学校に戻るきっかけをつかんだという声も多く聞かれます。
家庭学習を通じて再び学ぶ楽しさを感じられるようになる、そんな教材なんです。
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
すららは、すでに多くの自治体や学校と連携し、教育現場での活用実績を積み重ねています。
たとえば、自治体単位で不登校支援として導入されていたり、一部の学校では保健室登校の生徒向けの教材として使われていたりするケースもあるんです。
これは単に民間サービスとしての利用を超えて、公共教育の一部としても信頼されていることの証でもあります。
こうした広がりは、教材の質だけでなく「一人ひとりの学びに寄り添う設計」が評価されているからこそ。
すららを導入している教育委員会が増えているという点から見ても、その信頼性は十分に感じていただけるのではないでしょうか。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
「不登校支援教材」として、文部科学省が推奨しているリストにすららが掲載されていることをご存知ですか?これは教材としての内容や設計が、不登校の子どもたちの学びを支えるうえで適していると、国が認めている証なんです。
実際に、出席扱い制度の条件として「認可された教材で学習していること」が求められることがあり、すららはその条件を満たす数少ない選択肢の一つになっています。
保護者の方からも「学校に行けなくても学びが続けられて安心した」という声が多く寄せられています。
ただ勉強できるだけではなく、将来的に学校への復帰や進学を見据えた土台づくりにもなるのが、すららの大きな強みです。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
不登校の子どもにとって重要なのが「自宅での学習が学校に準じるものとして評価されるかどうか」ですよね。
その点ですららは、学習指導要領に準拠したカリキュラムが組まれているため、家庭での学びでも学校と同じような扱いを受けやすくなっています。
しかも、学習の進捗や定着度が明確に記録され、第三者にとっても成果が見えやすい設計になっているので、学校側にも説明しやすいのが大きなメリットです。
これは、出席扱いを目指す家庭にとって大きな安心材料になるはずです。
しっかりとした評価体制があることで、子ども自身も「ちゃんと認めてもらえている」という実感を得られ、自信をもって学び続けることができますよ。
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
すららの教材は、文部科学省が定める「学習指導要領」に準拠して作られているため、家庭での学びがそのまま学校の学習に直結します。
つまり、「学校の授業についていけるか心配…」という不安を感じている保護者の方も、安心して子どもに取り組ませることができるんです。
また、教科書レベルの内容だけでなく、基礎から応用まで幅広くカバーしているため、学年を問わず無理なく学習を進められます。
学校に通えない期間でも「自分はちゃんと勉強してる」という自信を持つことができるのは、すららならではの魅力です。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
すららには、学習の進捗を自動で記録・分析し、定期的にレポートとして表示してくれる機能が備わっています。
これによって、保護者や学校の先生が「どのくらい進んでいるのか」「どこにつまずいているのか」をすぐに把握できるのです。
とくに不登校のお子さんの場合、学校に提出するレポートや学習報告が求められることも多いですが、すららならその点もスムーズに対応できます。
AIによるフィードバックで理解度も高まりやすく、「わかったつもり」で終わらないのもポイント。
ただ進めるだけでなく、しっかりと定着させていく仕組みが整っているからこそ、学校に準じた学習環境として信頼されているのです。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について
すららは、学校に通えない子どもたちでも安心して学習を継続できる環境を提供しています。
そして実は、文部科学省が定める「出席扱いの制度」により、一定の条件を満たすことで、すららでの学習が学校の“出席”として認められる場合があります。
これは、不登校のお子さんにとってとても大きなメリットです。
出席扱いになることで、成績や進級に関する不安が軽減され、また本人の自己肯定感にもつながります。
ただし、出席扱いを受けるには、学校や医師との連携、そして必要な書類の準備など、いくつかのステップを踏む必要があります。
このページでは、すららを使った出席扱いの具体的な申請方法と、その際の注意点についてわかりやすくご紹介していきます。
申請方法1・担任・学校に相談する
まず、出席扱いの第一歩として大切なのが「担任や学校への相談」です。
学校ごとに対応が異なる場合があるため、まずは担任の先生や学年主任など、信頼できる教職員に「すららを使って学習していること」「出席扱いの制度を活用したいこと」を伝えてみましょう。
出席扱い制度は、文部科学省が通知している内容をもとにしており、対応している学校も増えてきています。
ただし、校長先生の裁量や地域の教育委員会の判断に左右される部分もあるため、学校ときちんと話し合いながら進めることがとても大切です。
無理にお願いするのではなく、「家庭での学習環境を整えていて、本人が前向きに取り組んでいること」をしっかり伝えると、理解されやすくなります。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
出席扱いの申請には、いくつかの必要書類や条件を満たす必要があります。
たとえば「学習内容が学校の教育課程に準ずること」「教員がその学習状況を把握できること」などが条件として挙げられます。
すららの場合、学習レポートや進捗確認機能がしっかりしているため、これらの条件をクリアしやすいといえます。
学校によっては、申請書類に加えて保護者による確認書や学習計画の提示が求められることもありますので、あらかじめ学校側とすり合わせをしておくことが大切です。
条件を丁寧に確認し、不備のないように書類を整えておくことで、申請がスムーズに進む可能性が高まります。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
申請にあたって、すべての場合に医師の診断書が必要というわけではありませんが、不登校の理由によっては提出が求められることがあります。
たとえば、精神的な不安や発達特性によって学校生活が難しいと判断されている場合には、「医師の意見書」が後押し材料になることがあります。
この診断書によって、「家庭での学習支援が適切である」と判断されやすくなるため、用意しておくと安心です。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
不登校の理由が「病気や発達障害によるもの」の場合、学校側が正式に出席扱いに認めるためには、医師による診断書や意見書の提出を求めることがあります。
これは、教育的配慮の必要性を客観的に示すために重要な書類となります。
「なぜ登校が難しいのか」「家庭学習が適切な選択である理由」などが明記された内容であれば、よりスムーズに対応してもらえることが多いです。
事前に学校側に「診断書は必要かどうか」確認することをおすすめします。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
診断書を用意する場合は、精神科・心療内科・小児科などで、医師に「不登校の状態」であること、そして「家庭での学習継続が望ましい」という見解を書いてもらうことが大切です。
とくに、発達障害や情緒的な不安が背景にある場合は、医師の見解が非常に重要視されます。
すららのような教材で継続的に学習していることを医師に説明しておくと、より具体的な意見書を書いてもらいやすくなります。
学校と医療の両方のサポートを受けながら、安心して申請を進めていきましょう。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
出席扱いを希望する場合、すららの学習記録を学校へ提出するステップが非常に重要になります。
すららでは、子どもの学習進捗が詳細にレポートとして記録されており、そのデータを保護者がダウンロードして、担任や校長先生に提出します。
このレポートには、学習した日時や内容、正答率、定着状況などが明確に示されているため、「しっかり学んでいる証拠」として学校側も判断しやすいです。
また、学習記録の提出と合わせて「出席扱い申請書」を学校で作成する必要がありますが、この申請書作成には保護者のサポートが求められるケースが多いです。
提出までの流れはとてもシンプルで、難しい手続きはありませんが、学校としっかり連携しながら丁寧に進めていくことが大切ですね。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
すららでは、子どもの学習履歴がデジタルデータとして自動で記録されていきます。
このレポートは保護者のマイページから簡単にダウンロードすることができ、それを印刷して学校へ提出するだけでOKです。
提出先は主に担任の先生、または学校長になります。
学習時間や達成度、苦手分野の克服状況など、学校が求める「客観的な証明書類」として非常に有効です。
特別な準備も必要なく、日々の学習を続けていれば自然と記録が蓄積されていくので、保護者としても安心ですね。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
出席扱いを正式に申請するためには、学校で「出席扱い申請書」を作成する必要があります。
この作業は主に学校側で行いますが、保護者からの協力や情報提供が不可欠です。
たとえば、すららでどのように学習しているのか、1日にどれくらいの時間取り組んでいるのかなど、具体的な状況を伝えてあげると、学校としても申請書をスムーズに作成しやすくなります。
また、学校ごとに書式や提出書類の内容が異なることもあるので、事前に担任や校長先生と打ち合わせをしておくと安心です。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
出席扱いを得るためには、学校長の承認が必須となります。
ここで重要になるのが、提出した学習記録と保護者の説明です。
すららでの学習がきちんとした教育的価値を持っていると認められれば、学校長が正式に「出席扱い」として判断してくれます。
また、自治体によっては教育委員会の承認が必要となる場合もあり、その場合は学校と教育委員会が連携して手続きを進める形になります。
保護者としては、焦らずに学校と協力しながら段階的に進めていくことが大切です。
学習の記録と内容が整っていれば、特に不利になることはありませんので、落ち着いて対応していきましょう。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
最終的な判断は、通っている学校の「学校長」が行います。
提出された学習記録や保護者の説明、子どもの学習状況を総合的に見て、「この子は家庭でもしっかり学習を続けている」と判断されれば、出席扱いが認められます。
このとき、すららのような教材は、学習記録がデジタルでしっかり残るため、学校長にとっても判断しやすい材料となります。
どんなに家庭で努力していても、証明ができなければ出席扱いにはなりません。
その点で、すららのレポート機能はとても心強い味方になってくれます。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
地域によっては、学校長の承認だけでは足りず、教育委員会への申請が必要になることもあります。
この場合、基本的には学校側が主導して手続きを進めてくれますが、保護者も必要に応じて情報を提供したり、書類の準備をしたりすることがあります。
大切なのは、学校と敵対するのではなく、協力し合う姿勢です。
すららを通じて得られる学びがしっかりと伝われば、教育委員会も前向きに検討してくれるケースが多いですので、安心して進めていきましょう。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します
すららは、不登校のお子さんでも出席扱いとして認められるケースがあるオンライン教材です。
これは文部科学省の「出席扱い制度」にもとづいており、一定の条件をクリアすれば学校での授業に出ていなくても、家庭学習を出席としてカウントしてもらえる場合があります。
そんな制度をうまく活用することで、子どもだけでなく、保護者にとってもさまざまなメリットが得られます。
とくに、すららのように専任コーチがサポートしてくれる教材では、必要書類やレポートの提出フォローも充実しているため、「何から手をつければいいのかわからない」という不安も軽減されやすいです。
ここでは、すららで出席扱いを認めてもらうことで得られる具体的なメリットについて詳しくご紹介していきます。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
不登校になってしまうと、どうしても気になるのが「出席日数の不足によって内申点が下がってしまうのでは?」ということですよね。
でも、すららでの家庭学習が出席扱いとして認められれば、学校の出席記録に反映されるため、内申点の評価に大きな影響を与えにくくなるんです。
これは受験や進学を考えるうえで非常に大きなメリット。
特に公立高校などでは、内申点が重要な判断材料になることも多いため、出席日数を確保できることは安心材料になります。
さらに、出席として認められることは、周囲との比較による焦りや不安の軽減にもつながります。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
すららでの学習が出席扱いになれば、物理的に登校していない間も「学びを続けている」と評価してもらえます。
その結果、出席日数の不足によって内申点が極端に下がるといったリスクが回避でき、進学の選択肢を守ることにもつながります。
中学・高校進学の選択肢が広がる
出席扱いを受けられることで、学力の遅れだけでなく、進路の選択肢も広がっていきます。
希望する学校の受験に不利になりにくくなるだけでなく、学校側からも「継続して努力できる子」として前向きに評価してもらえる可能性が高くなります。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
不登校が続いてしまうと、「もう授業についていけないかもしれない…」という不安がつきまといますよね。
でも、すららなら自宅で自分のペースで学習を続けられるため、そうした焦りやプレッシャーが大きく軽減されます。
無学年式のシステムにより、理解があいまいな部分までしっかり戻って復習できるので、知識の抜けをきちんと埋めることができます。
「学校に行けていない」ことよりも、「学び続けている」ことを大切にできる環境だからこそ、子どもの自己肯定感も育ちやすいのです。
学習への自信がつけば、次第に「また学校に行ってみようかな」という気持ちが芽生えるきっかけにもなります。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
学校で学ぶ内容と同等の学習を、すららで進めていくことができるため、「どれくらい遅れているのか」「取り戻せるのか」といった不安を感じにくくなります。
自分のタイミングで進められる点も安心材料になりますね。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
「何もしていない」「何もできていない」と感じてしまう状況が続くと、子どもの自己肯定感が下がりやすくなります。
でも、すららを通じて日々の学びを積み重ねていけば、「ちゃんと勉強している」という実感が持て、自信や前向きな気持ちが育まれます。
メリット3・親の心の負担が減る
子どもが不登校になったとき、親として一番つらいのは「何をどうしてあげればいいのか分からない」「全部ひとりで抱え込んでいる気がする」といった孤独感や無力感ではないでしょうか。
すららは、子どもの学びをコーチと一緒に支えていく体制があるので、親だけが頑張る必要がありません。
学校との連携もサポートしてくれるので、「担任の先生にどう伝えるべき?」「書類の準備はどうするの?」という細かい不安にも寄り添ってくれます。
家庭と学校、そしてすららの三者がつながっている安心感は、保護者の心にとって大きな支えになるはずです。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
親がすべてを背負うのではなく、すららのコーチや学校の先生と一緒に子どもを支える仕組みができることで、「自分だけで何とかしなきゃ」というプレッシャーが軽くなります。
悩みを共有しやすい環境が整っているのは、精神的なゆとりにもつながります。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します
「すららって本当に出席扱いになるの?」と気になっている保護者の方も多いと思います。
実は、すららは文部科学省の「出席扱いに関するガイドライン」に対応している教材として、多くの自治体や学校で出席扱いに認められている実績があるんです。
ただし、どの学校でも自動的に認められるわけではなく、いくつかの条件や事前の手続きが必要になります。
たとえば、学校との話し合いの場を持つことや、必要書類を提出すること、学習記録の提示などが求められる場合があります。
そこで今回は「すららを活用して出席扱いを目指すには、どんな点に気をつければいいのか?」をわかりやすくまとめてご紹介します。
お子さんの学びを支えつつ、少しでもスムーズに学校と連携できるよう、参考にしてみてくださいね。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
すららを使って不登校中の学習を継続し、出席扱いにしてもらうためには、学校側の理解と協力が欠かせません。
とくに担任の先生だけでなく、教頭先生や校長先生とも情報を共有しながら話を進めることが大切です。
学校によっては前例がない場合もあり、慎重な対応が求められることもありますので、早めに相談の場を設けると安心です。
丁寧に説明し、家庭がしっかりとお子さんの学習環境を整えていることを伝えることで、学校側も前向きに検討してくれることが多くなります。
「出席扱いになるのかな…」と迷っている場合でも、まずは一歩踏み出して相談することから始めてみるのがポイントです。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
出席扱いを目指すうえで、すららが文部科学省のガイドラインに対応した学習教材であることをきちんと伝えることがとても重要です。
学校の先生も「すらら」を知らない場合がありますので、いきなり教材名だけを伝えるのではなく、「この教材は国の基準に沿って作られているので、出席扱い対象として認められる事例が全国的に増えています」といったように、安心感を持ってもらえるような説明を心がけるとスムーズです。
資料などを一緒に提示すると、さらに説得力が増しますよ。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
学校側との連携をうまく進めるためには、すららの公式資料を印刷して持参するのがおすすめです。
カリキュラムの内容や、出席扱いとして採用された実績が載っている資料を提示することで、相手に安心感を与えることができます。
また、相談の相手は担任の先生だけにとどまらず、教頭先生や校長先生にも早めに話を通しておくと、学校全体としての合意が得やすくなります。
できるだけ感情的にならず、誠実な姿勢で話し合いを進めることが、成功の鍵になりますよ。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
すららを活用して出席扱いを申請する際に注意したいのが、「医師の診断書や意見書」が必要になるケースがあるという点です。
特に不登校の理由が体調面の問題や精神的な不安である場合、学校がその状況を正確に把握するために、医師からの書面が求められることがあります。
この診断書には、「通学が困難な状態にあること」「自宅学習が継続されており、教育的な効果が期待できること」などが記載されるのが一般的です。
すららでの学習の様子を記録しておき、それを医師に伝えると、より前向きな内容で書いてもらえる可能性が高くなります。
診断書は決して形式的なものではなく、お子さんの状態を支援するための大切な手段ですので、準備にはしっかり時間をとってくださいね。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
不登校の背景が「継続的な体調不良」や「心の不調」である場合、学校側はその正当性を判断するために医師の診断書や意見書の提出を求めることがあります。
これは、ただの「さぼり」とは違うことをきちんと示すために必要な書類です。
提出することで、出席扱いの申請がスムーズになるだけでなく、学校側もより柔軟な対応を取りやすくなります。
安心して申請するためにも、必要書類の準備は丁寧に進めましょう。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
診断書を依頼する際は、普段通っている小児科や心療内科で「学校に出席扱いとして認めてもらうための診断書が必要です」と具体的に伝えるのがポイントです。
医師もその目的が明確であれば、状況に合った内容で診断書を作成してくれます。
特にすららのような学習サービスを活用していることも伝えると、「学習の継続意思がある」ことが評価されやすくなります。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
診断書の内容は、ただ病名が書かれていれば良いというものではありません。
「家庭でしっかり学習している」「本人にやる気がある」といったプラスの情報を医師に伝えることで、より信頼性の高い、前向きな診断書になります。
すららでの学習進捗やログイン履歴をスクリーンショットで見せるのも効果的。
自宅学習への取り組みが記載されていれば、学校側の理解も得やすくなりますよ。
注意点3・ 学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
出席扱いにしてもらうためには、「家庭学習であれば何でも良い」というわけではないのが現実です。
文部科学省のガイドラインでも、「学習内容が学校の教育課程に準じていること」が重要視されています。
つまり、ただ問題集を解いたり読書をするだけではなく、「教科ごとに系統立てられた内容」で、「学校の授業と同程度の水準」で学ぶ必要があるんです。
すららは、その点でも非常に頼もしい教材です。
無学年式であっても、教科書に対応したカリキュラムと進捗の記録があり、AIによる習熟度チェックまで揃っているので、学校からも評価されやすいのが特徴です。
出席扱い申請に向けては、学習ログやテスト結果をきちんと保管しておくことも忘れずに。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
たとえば「漢字練習だけ」「読書だけ」では、出席扱いの申請が通らない可能性が高くなります。
学校教育と同じように、国語・算数・理科・社会などの科目をバランスよく学んでいることが求められるからです。
その点、すららなら主要教科が体系的に学べる設計になっているので、出席扱い申請にも対応しやすいですね。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
学習時間も、学校の授業に近い形を意識すると安心です。
もちろん最初から長時間は難しいこともあると思いますが、1日2〜3時間を目標に少しずつリズムを作っていくことが理想的です。
すららは短時間でも集中しやすい工夫がされているので、無理なく進めやすいですよ。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
学校によっては「主要3教科だけでは不十分」とされるケースもあります。
そのため、できるだけ幅広い教科をバランスよく取り入れていることをアピールできるようにしましょう。
すららの教材なら、主要3教科はもちろん、追加教科も選べるので、家庭学習の幅を広げることができますよ。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
出席扱いを申請する際にとても大切なのが、「学校との定期的なやりとり」です。
すららを使ってしっかり学んでいても、それを学校側が把握していなければ、出席扱いとして認めてもらうのは難しくなります。
たとえば月に一度、学習の進捗レポートを提出したり、担任の先生と電話やメールで状況を共有したりと、こまめな連絡が信頼関係につながります。
すららには保護者向けのレポート機能もあるので、それを活用することで学習状況を「見える化」しやすく、学校側も安心できますよ。
また、必要に応じて家庭訪問や面談の場を持つことも、スムーズな申請にとって大切なステップ。
学校としっかり連携しながら進めていくことで、お子さんが安心して学習を続けられる環境が整っていきます。
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
すららのような家庭学習で出席扱いを受けるには、「家庭が勝手にやっている」ではなく、「学校と連携して進めている」ことが大前提になります。
そのため、先生と学習状況を共有することが条件に含まれるケースが多いです。
信頼関係を築きながら進めましょう。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
すららには、学習時間や達成状況をまとめたレポート機能があり、それを月1回程度提出するだけでも、学校側は安心して出席扱いの判断がしやすくなります。
わざわざ書類を自作する必要もなく、すららの機能を活用するだけで済むのが嬉しいポイントです。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
先生が実際に子どもの学習環境を見たいと言ってくることもあります。
家庭訪問や学校での面談を通して、お子さんの学習の様子や意欲を直接伝えることができれば、よりスムーズに理解を得やすくなります。
無理のない範囲で協力しましょう。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
担任の先生とは「必要なときだけ」ではなく、定期的に連絡を取ることで信頼関係が生まれます。
「今週はこんな単元を勉強しました」「〇〇に苦戦していましたが、少しずつ理解が深まってきています」など、簡単な内容でもOK。
短くても続けることが大切です。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
出席扱いは、基本的には学校長の判断で決まりますが、自治体によっては「教育委員会への申請」が必要になる場合もあります。
特に不登校が長期にわたるケースや、発達支援が関係している場合などは、教育委員会の審査を通すことで、より正式な扱いになることがあります。
こうしたケースでは、家庭だけで判断して進めるのは難しいため、まずは学校の先生や校長先生と相談しながら、「教育委員会が関与する必要があるのか」「どんな書類が必要なのか」などを確認して進めるのが安心です。
すららのように、学習ログが明確な教材を使っていれば、そのまま資料として提出できることも多く、手続きのハードルがぐっと下がりますよ。
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
教育委員会への申請が必要な場合、個人で進めようとすると大変ですが、学校側と相談しながら進めることでスムーズになります。
必要な書類の書き方や提出方法も教えてくれるので、遠慮せず頼ってくださいね。
提出には時間がかかる場合もあるので、余裕を持って準備を始めましょう。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します
すららを使って学習しているお子さんが「出席扱い」になるためには、いくつかの成功ポイントを押さえて学校側にしっかりとアピールすることが大切です。
出席扱いは学校の判断に委ねられている部分が大きいため、単に制度を知っているだけでは不十分なんです。
そこで重要なのが、「前例の提示」や「本人のやる気」など、具体的で信頼性のある情報を伝えることです。
すららは全国の多くの教育現場で活用されている実績があり、学校が不安を感じにくい仕組みが整っています。
この記事では、出席扱いをより確実に認めてもらうために効果的な方法を、わかりやすくまとめてご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
出席扱いの申請を行うとき、学校側がもっとも気にするのは「本当にこれで大丈夫なの?」という前例の有無です。
だからこそ、「他校でのすらら活用事例」や「実際に出席扱いとして認められた例」を紹介することで、学校側の不安を払拭しやすくなります。
「前例がある」とわかれば、教職員の方々も前向きに判断しやすくなるんですね。
実際にすららの公式サイトには、出席扱いを成功させた事例がいくつも掲載されています。
こうした情報を、ただ口頭で伝えるのではなく、印刷して持参することで、より信頼感を与えることができますよ。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
「うちの学校では前例がない」と言われたときこそチャンスです。
他の地域・他の学校で「すららを使って出席扱いになった事例」があることを具体的に伝えると、学校側も一歩踏み出しやすくなります。
保護者が積極的に調べて共有する姿勢も、信頼を得る大きな材料になりますよ。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
口頭で説明するより、実際の資料を見せる方がずっと効果的です。
すららの公式サイトには、出席扱いになった事例や、教育委員会での評価実績なども掲載されています。
気になるページを印刷して、学校との面談時に持参すれば説得力がぐっと高まりますよ。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
出席扱いの可否において、「本人が自発的に学んでいるかどうか」はとても重要なポイントになります。
いくら環境が整っていても、本人の意欲が感じられない場合、学校は出席扱いを認めにくくなることも。
だからこそ、日々すららに取り組んでいる姿や、学んでいる内容への関心をきちんと伝えることが大切です。
本人が「自分の言葉」で意欲を示すと、学校側の印象も大きく変わります。
学習の感想を一言書くだけでも良いですし、学習目標を書いたメモでも大丈夫。
少しの工夫で「この子は真剣に学んでいる」と感じてもらえるようになりますよ。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
たとえば「今週は漢字が少しずつ読めるようになってきた」「算数の分数が面白いと思えるようになった」など、本人の素直な感想が学校側にとって大きな判断材料になります。
フォーマルな作文ではなくても大丈夫。
お子さんの言葉で表現された“学びの記録”を提出すると、出席扱いが一気に近づきますよ。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
学校との面談では、可能であればお子さん本人も一緒に参加しましょう。
「最近は毎日30分がんばってるよ」と自分の言葉で伝えるだけでも、教職員の心に響くものがあります。
うまく話せなくても問題ありません。
表情や声から伝わるやる気が、制度の後押しになることもあるんです。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
すららを使って出席扱いを目指すうえで、一番大切になるのが「継続すること」です。
どれだけ最初に意欲が高くても、無理なスケジュールでは途中で疲れてしまい、長続きしなくなります。
だからこそ、お子さんの性格や体調、家庭の環境に合った“現実的な学習計画”を立てることが大事なんです。
すららでは、「すららコーチ」というプロの学習支援者がついており、子どもの理解度や集中力の持続時間などを考慮して、無理のない学習スケジュールを提案してくれます。
週に何日、1日どれくらい学習するかといった具体的なペース配分を、一緒に考えてくれるのが心強いポイントです。
家庭で抱え込まず、コーチに相談することで「学習が習慣化」しやすくなりますよ。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
毎日コツコツ勉強を続けるのって、大人でもなかなか難しいもの。
だからこそ、子どもの「やる気の波」や「得意・不得意」に合わせた学習計画が大切です。
調子のいい日は多めに、疲れている日は軽めに──そんな柔軟さが、すららの魅力でもあります。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
「毎日2時間やってください!」といきなり言われても、現実的には難しいですよね。
すららコーチは、子どもや保護者の状況を聞きながら、実現可能なスケジュールを提案してくれます。
無理なく、だけどちゃんと成長できる、そんな学びのリズムを一緒に作ってくれます。
ポイント4・:「すららコーチ」をフル活用する
すららには、ただの教材では終わらない“伴走者”として「すららコーチ」がついてくれます。
これが他の家庭学習教材とは決定的に違うところ。
出席扱いの申請に必要な「学習証明」や「進捗の記録」など、面倒になりがちな部分も、コーチが丁寧にサポートしてくれるから安心なんです。
たとえば「どれだけ勉強したか」「どんな内容を学んだか」といった情報は、学校への報告に必要なこと。
でも、すららコーチはその情報をもとに、保護者や先生にも提出できるようなレポートを作ってくれることもあるんです。
学習相談だけでなく、制度のことや手続きに関することまでフォローしてくれるから、まさに“頼れる存在”です。
少しでも不安や疑問があるなら、気軽に相談してみるのがおすすめですよ。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
学校に提出するレポートって、意外と大変だったりしますよね。
そんな時でも、すららコーチは保護者の代わりに必要な資料を整えてくれたり、どんな形で伝えればいいかのアドバイスをくれたりします。
「何をすればいいのか分からない…」と不安な時ほど、コーチに頼ってみてくださいね。
すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
「すららはうざい」という声が一部で見られるのは、実際に使ってみた感想が期待と少し違ったと感じるユーザーがいるためです。
たとえば、「アニメのキャラが話しかけてくるのが子どもっぽく感じた」「テンポがゆっくりで合わなかった」など、好みの問題で合わなかったという口コミが挙がることがあります。
また、勉強のスタイルに合わず、継続できなかったことで「うざい」と感じてしまった可能性もあるでしょう。
ですがこれは裏を返せば、子ども一人ひとりの特性や好みによって合う・合わないがはっきりする教材だからとも言えます。
すららは“個別対応”を重視した設計なので、しっかりハマる子にはとても効果的な学習法になります。
まずは無料体験や説明会で、お子さんとの相性を確認してから始めるのが安心ですね。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららでは、発達障害や学習障害のあるお子さん向けに特化したコースも用意されており、その料金体系は家庭の負担を少しでも軽減できるよう工夫されています。
例えば、療育手帳を持っているご家庭や、自治体による助成制度が適用されるケースでは、月額料金が軽減される場合もあるんです。
また、すららはもともとが「無学年式」で、自分のペースに合わせて取り組めるため、ASD(自閉スペクトラム症)やADHDのお子さんにもやさしい設計となっています。
学習サポートがしっかりしている分、多少の費用はかかるものの、家庭学習の質がぐんと上がることを考えると、決して高い買い物ではないと感じる方も多いようです。
お住まいの地域や条件によっては補助金が使えることもあるので、ぜひ調べてみてくださいね。
関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
はい、すららは文部科学省が推奨する「ICTを活用した出席扱い制度」に対応しており、条件を満たせば、学校への登校が難しいお子さんでも“出席扱い”として認められる可能性があります。
具体的には、学校側との連携、家庭学習の記録の提出、場合によっては医師の意見書などが必要になることがありますが、すららには学習ログや進捗管理の機能があるため、提出資料として活用しやすいのが大きなメリットです。
また、すららは不登校の子が抱えがちな「勉強のブランク」や「自信のなさ」をフォローする工夫がたくさん盛り込まれているので、無理のないペースで学習を再スタートさせるきっかけにもなります。
出席扱いを希望する場合は、まずは学校の先生に相談してみてくださいね。
関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららでは、定期的に「入会金が無料になる」などの特典付きキャンペーンコードが発行されています。
このコードは、資料請求後に届く案内や、オンライン説明会に参加した方に限定で配布されることが多いんです。
コードの使用方法はとても簡単で、入会手続きを進める際に専用の入力欄があるので、そこにキャンペーンコードを入力するだけで割引が適用されます。
とくに初めて利用する方にとっては、入会時のハードルがぐっと下がるので、使わない手はありません。
ただし、キャンペーンによっては「〇月末まで有効」などの期限付きであることもあるため、事前にしっかりチェックしておくのが大切です。
まずは無料資料請求から始めて、お得な情報を見逃さないようにしましょう。
関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららの退会手続きはとてもシンプルですが、いくつか注意点もあります。
まず、退会を希望する場合は「すららサポート事務局」にメールや問い合わせフォームから連絡を入れる必要があります。
ここでポイントとなるのが、「解約」と「退会」は別の手続きということ。
毎月の課金を止めたい場合はまず「解約」を行い、その後、個人情報などをすべて削除してほしい場合には「退会」の申請も行います。
退会が完了すると、これまでの学習履歴も全て削除されるため、必要なデータは事前にバックアップしておくと安心です。
また、退会申請は月の締め日までに余裕を持って連絡するのがスムーズ。
キャンペーンなどの特典が消えるタイミングもあるので、手続き前にもう一度内容を確認しておくといいですよ。
関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららでは、基本的にかかる費用は「入会金」と「毎月の受講料」だけなので、非常にシンプルで分かりやすい料金体系になっています。
入会金はコースによって異なりますが、一度支払えば再度必要になることはなく、月額料金も明記されているため、あとから追加料金が発生するような心配はありません。
ただし、タブレットなどの端末は自前で準備する必要があり、すらら専用の機器が送られてくるわけではありません。
また、万が一の際のサポートやオプション機能などに追加費用がかかるケースもあるため、公式サイトや資料でしっかり確認するのがおすすめです。
全体的に「料金のわかりやすさ」と「後からの請求がない安心感」が、すららの魅力のひとつでもありますよ。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
はい、すららは「1契約で複数の子どもが使える」という点が、他の家庭学習教材にはあまり見られない、大きな魅力なんです。
同じアカウント内であっても、兄弟ごとに個別の学習履歴や進度が記録されるので、「お兄ちゃんが先にやってしまって進みすぎた」なんてことにはなりません。
兄弟がそれぞれ自分のペースで取り組めるのに、追加費用が不要というのは、本当に家計にやさしい仕組みですよね。
もちろん、契約時に「家族での利用」を想定している旨をきちんと確認することも大切です。
学年の違う兄弟が一緒に学べる環境を整えることで、学習の習慣づけにもなりやすいですよ。
すららの小学生コースには英語はありますか?
すららの小学生コースには、ちゃんと英語が含まれていますよ。
しかも、単なる読み書きだけではなく、「聞く」「話す」「読む」の3技能に対応しているのが大きな特長です。
たとえば、音声を聞きながら正しい発音をまねしたり、簡単な英語のやりとりをアニメキャラと楽しんだりと、自然に英語が身につくような仕組みが用意されています。
小学校で英語が教科化された今、「英語って難しそう…」と感じる子も増えていますが、すららならアニメーションの力でとっつきやすく、楽しく学習が進められます。
発音やイントネーションの練習もできるので、英語への苦手意識があるお子さんにもぴったりです。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららの最大の魅力のひとつが、「すららコーチ」と呼ばれるプロの学習サポートです。
これは、ただの質問対応ではなく、お子さんの特性や性格、学習履歴などを踏まえた“個別最適化”されたサポートが受けられる点で、他の教材とは一線を画しています。
たとえば、「どの単元から始めたらいいか迷っている」といったときには、現状のつまずきや得意分野を見て、最適な学習スケジュールを提案してくれますし、学習が進まないときも「ちょっとした声かけ」でやる気を引き出すようなフォローをしてくれるんです。
さらに、保護者向けにもアドバイスが届くため、親としても「何をどう見守ればいいのか」が分かって安心ですよ。
参照: よくある質問 (すらら公式サイト)
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ
今回のテーマは「すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて」でした。
出席扱いを希望する際には、まず適切な手続きや必要な書類を提出することが重要です。
また、出席扱いを受ける上での注意点としては、期限や条件を確認し、適切な形式での提出を心がけることが必要です。
成功するためには、的確な理由や根拠を示し、誠実な態度での申請が重要です。
出席扱いの申請手順や注意点をしっかり把握し、誠実かつ適切な方法で申請を行うことで、不登校でも出席扱いになる可能性が高まります。
また、周囲とのコミュニケーションを大切にし、サポートを受けながら進めることも成功のポイントです。
出席扱いを希望する際には、冷静な判断と準備を行い、問題解決に向けて前向きに取り組んでいきましょう。
不登校でも出席扱いを受けることは、正当な権利であり、適切な手続きを踏むことで実現可能です。
申請手順や注意点を理解し、成功のポイントを押さえながら、出席扱いを目指して努力を続けてください。
自らの権利をしっかりと主張し、学び舎での支援を受けながら、充実した学びの環境を築いていきましょう。