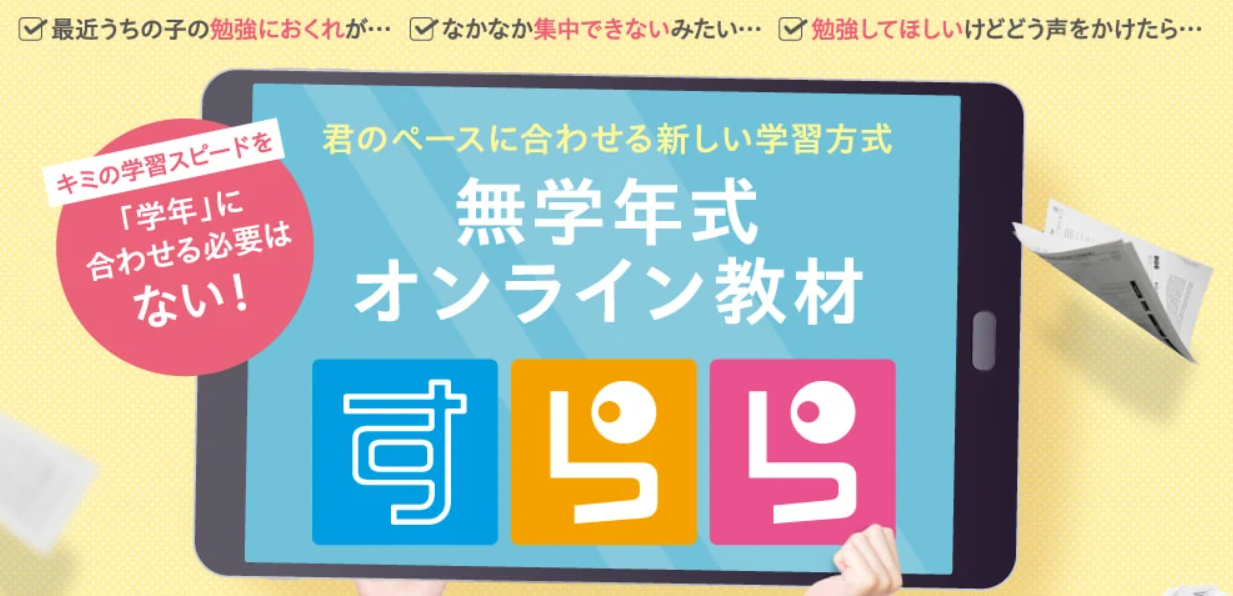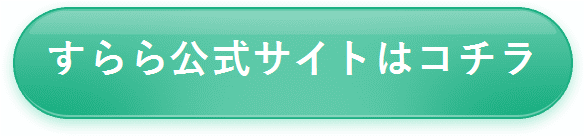すららはうざい!?すららが選ばれるおすすめのポイントを紹介します
「すららってうざいって本当?」という検索ワードを目にして、ちょっと不安になった方もいるかもしれません。
でもそれ、ただの誤解です。
すららは、むしろ子どもたちの可能性を最大限に引き出すために作られた、最新のオンライン学習サービス。
特に学習に悩みを持つ子や、親御さんが忙しくて手が回らないご家庭にとっては、まさに救世主のような存在なんです。
今回は、そんなすららがなぜこれほど支持されているのか、そのおすすめポイントを具体的に紹介していきます。
お子さんの学習方法に迷っている方や、「うちの子に合う教材が見つからない…」と悩んでいる方にとって、きっとヒントになる内容になっています。
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
すららのおすすめポイントをまとめました
すららが多くの家庭に選ばれているのは、ただ「流行っているから」という理由ではありません。
学習効果を最大化するための工夫が詰まっていて、しかも親にもやさしい設計になっているからなんです。
たとえば、学年に縛られず自分のペースで学べる無学年式。
これは、苦手な部分はしっかり戻って復習し、得意なところはどんどん先へ進めるという、自律型学習には欠かせない仕組みです。
他にも、キャラクターと会話する対話型授業や、プロのコーチが学習をサポートしてくれる「すららコーチ」など、家庭学習にありがちな問題点を一つ一つ丁寧に解決してくれる機能が揃っています。
この表では、それぞれのポイントを具体例付きで紹介していますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
| ポイント | 具体例 |
| 無学年式 | 小1の子が中学英語も学べる!苦手もじっくり戻れる |
| 対話型授業 | アニメキャラとの対話形式で「双方向」学習 |
| すららコーチ | 親がスケジュール管理しなくてOK!丸投げ可能 |
| 発達障害・不登校対応 | AIがつまずきを解析→無理なく学習再開できる |
| 成果が見える | テスト・レポート・定着診断で、親も安心 |
| 英語3技能対応 | 話す・聞く・読むがまんべんなく学べる |
| 兄弟OK | 1契約で複数人OK→家族で使えば超コスパがいい |
ポイント1・無学年式!学年に縛られず、得意も苦手も自由に学べる
すららの最大の魅力は、なんといっても「無学年式」の学習スタイル。
これがどういうことかというと、学年にとらわれず、子どもの理解度に合わせて学習内容を選べるという仕組みなんです。
例えば、小学3年生でも中学レベルの英語に挑戦できたり、中学生が小学校内容に戻って復習することもできるということ。
これは、一人ひとりの学力に合わせた“オーダーメイド学習”を可能にしてくれるんですね。
苦手はそのままにしない、得意は無駄に待たせない、そんな柔軟性があるからこそ、どんな子でも「自分に合った学び方」が見つかるのです。
これまで「勉強が苦手」と感じていた子でも、気づけばどんどん進んでいける。
それがすららの無学年式の力なんです。
学力や進度に関係なく、自分のペースで学べる
学校ではどうしても、「今はこの単元を学ぶ時間」と決められてしまいますよね。
でも、すららならそんな縛りは一切ありません。
学力に関係なく、本人の理解度や学習ペースに合わせて、自由に単元を選んで進められるんです。
「この前の内容、いまいち理解できなかったから、もう一回戻りたい」と思ったら、すぐに戻って学び直すことができますし、「ここは簡単そうだから、どんどん進みたい!」というときには先取り学習もOK。
つまり、やらされる学習ではなく、自分の意思で学び方をコントロールできるという点が、子どもにとってものすごく大きなメリットなんです。
こうして「わからない」が減っていくと、自然と「できる」が増えて、勉強が楽しくなっていきますよ。
「得意はどんどん進める」「苦手はじっくり戻る」が簡単にできる
学習にはリズムやテンポが大切です。
すららでは、得意な分野は子どものやる気が高まっているうちにどんどん先へ進むことができるので、成長スピードが加速します。
一方で、苦手なところはAIが自動で分析して、つまずいているポイントを特定。
必要な部分までしっかり戻って、繰り返し学習できるようになっています。
つまり、「理解できた」という実感がちゃんと持てるまで、焦らず丁寧に進められる仕組みなんです。
こうしたバランスの取れた学び方は、無理なく継続できるだけでなく、子どもが自分に自信を持てるようになる第一歩にもなります。
「できた!」という感覚を積み重ねていくことで、勉強そのものへのモチベーションも自然と高まっていくんですね。
ポイント2・「対話型アニメーション授業」で、わかりやすい&飽きない
すららの授業は、一般的な「講義動画を見るだけ」とはまったく違います。
アニメーションを使って、子どもがキャラクターと実際に会話しているような感覚で学べる「対話型アニメーション授業」が特徴なんです。
このスタイルは、ただ画面を眺めているだけでは飽きてしまう子どもたちにとって、とても魅力的な仕掛けとなっています。
しかも、キャラクターたちは説明だけでなく質問もしてくるので、子どもが受け身にならず、自然と考える力が育っていくんです。
勉強というより「物語に参加している」ような感覚で学べるから、どんなに飽きっぽい子でも夢中になって続けられるようになります。
楽しさとわかりやすさが両立しているからこそ、学習へのハードルがぐっと下がるんですよ。
アニメキャラが「先生役」として、子どもと会話しながら進めてくれる
すららのアニメキャラクターたちは、ただのガイドではありません。
まるで本当の先生のように、子どもと対話しながら授業を進めてくれます。
学習の途中で質問を投げかけたり、子どもの反応に応じてコメントを返してくれるので、「一人で学んでいる感覚」が薄れ、まるで誰かと一緒に勉強しているような安心感が生まれるんです。
この「対話型」の形式は、特に集中力が続かない子や、学習に対して不安を感じている子にとって、とても効果的です。
一方的に説明を聞くだけではなく、自分から答えたり、キャラに話しかけられたりすることで、自然と授業に引き込まれていきます。
こうした仕組みが、子どもの学習を楽しく、そして継続しやすくしてくれるんですよ。
難しいことも「図や動き」で視覚的に理解できる
子どもが勉強につまずく理由のひとつに、「イメージが湧かない」という問題があります。
特に抽象的な内容や、図形・理科の概念などは、言葉だけではなかなか理解できませんよね。
そこで活躍するのが、すららのアニメーションです。
例えば図形の問題なら、図が回転したり分割されたり、実際に動きながら解説されるので、「ああ、そういうことか!」と感覚的に理解しやすくなります。
また、理科や社会の仕組みも、イラストや映像を交えて説明されるため、頭の中でイメージを作りやすくなるんです。
こうした視覚的な補助があることで、難しいと感じる内容もスムーズに吸収できるようになります。
文字だけでは伝わりにくい部分が、しっかりサポートされているのが魅力です。
キャラが褒めてくれるからやる気UP!飽きっぽい子でも続きやすい
子どもにとって「褒められる」という経験は、学習のやる気を左右する大きなポイントですよね。
すららのキャラクターは、正解を出したときや頑張ったときにしっかり褒めてくれるから、子どもは「自分はできている」という実感を持てるようになります。
このポジティブなフィードバックが、勉強への抵抗感を取り除き、「またやってみようかな」という気持ちにつながるんです。
特に飽きっぽい子や、途中で投げ出してしまいがちな子でも、キャラクターとのやりとりを楽しみながら続けることができる仕組みになっています。
毎日の学習に小さなご褒美のような「褒め言葉」があるだけで、続けることが苦にならなくなりますよ。
ポイント3・「すららコーチ」がついて親の負担が激減
「毎日の勉強、ついていないと進まない」「今日は何をやらせればいいのかわからない」…そんな悩みを抱える親御さんは多いですよね。
でも、すららには『すららコーチ』という心強い存在がいます。
このコーチは、子ども一人ひとりの状況に合わせた学習計画を立ててくれたり、進捗をチェックしたり、時には励ましのメッセージを送ってくれたりするんです。
つまり、親が全部を管理しなくても、プロがしっかりと学習をサポートしてくれる体制が整っているんですね。
子どもにとっても「見守ってくれている大人」が他にもいることで安心感が生まれ、やる気が引き出されやすくなります。
家庭学習を継続するために、親の負担を軽くするというのはとても大切なことです。
プロの「すららコーチ」が学習計画を作成&フォローしてくれる
学習計画って、意外と作るのが難しいですよね。
内容の順番やペース、本人の集中力などを考慮しないと、うまくいかないことも多いです。
でも、すららなら大丈夫。
すららコーチが、子ども一人ひとりの理解度や学習ペースを見ながら、最適な学習計画を立ててくれるんです。
それだけではなく、進み具合に応じて計画を調整したり、つまずいた時にはアドバイスをくれたりと、まさに「かゆいところに手が届く」存在です。
親が無理に管理しなくても、コーチがサポートしてくれる安心感はとても大きいですね。
学習計画の作成だけでなく、途中での軌道修正もできるから、無理なく続けられる仕組みが整っているんですよ。
子どもの特性や希望に合わせたオーダーメイド学習計画を立ててくれる
すららコーチは、ただスケジュールを機械的に組むだけの存在ではありません。
子どもの性格や生活スタイル、得意・不得意、さらには本人の希望まで丁寧にヒアリングし、それらを反映したオーダーメイドの学習計画を提案してくれます。
たとえば、「朝はどうしても集中できない」という子には、夕方中心のスケジュールに。
「この分野は得意だから先取りしたい」といった要望にも柔軟に対応してくれるんです。
そのため、子ども自身が納得して学習に取り組めるようになり、計画倒れになりにくくなるのも大きなポイントです。
「やらされる勉強」ではなく、「自分のペースで進める勉強」になるからこそ、継続がしやすくなるんですね。
質問や相談はコーチに直接できるから親は見守るだけでOK
子どもが勉強していると、どうしても「わからない」「これで合ってるのかな?」という疑問が出てきますよね。
でも、親が毎回それに応じるのはなかなか大変です。
そんなときに助かるのが、すららコーチとのダイレクトなやりとり。
子ども自身が、疑問や悩みを直接コーチに相談できるようになっているので、親はその都度対応しなくても大丈夫なんです。
質問に対して的確なアドバイスがもらえるだけでなく、「このままの進め方で合ってますか?」といった不安もその場で解消できます。
さらに、子どもがコーチとのやりとりを通じて、自主的に学習を管理する力も身についていきます。
親は見守るだけでOKというのは、心にも時間にも余裕を生んでくれますよ。
ポイント4・発達障害・不登校にも対応!学習への不安を取り除いてくれる
すららが多くの保護者から支持されている大きな理由のひとつが、「学習につまずきやすい子にもやさしい設計」がされている点です。
特に、発達障害のあるお子さんや、さまざまな理由で不登校となっている子どもたちにとって、学校と同じスタイルの教材ではうまく学習が進まないことがありますよね。
すららはその点を深く理解したうえで、教材の構成や操作性、キャラクターの話し方、画面の設計に至るまで、誰にでもわかりやすく、ストレスなく取り組めるように工夫されているんです。
本人が「これならできる」と思える体験を重ねていくことで、自信を取り戻し、自然と学習への意欲が湧いてくる。
すららは、そうした“心の回復”にも寄り添う教材なんですよ。
文部科学大臣賞も受賞している学習支援ツール
すららは、その教育的価値と社会的貢献が高く評価され、なんと文部科学大臣賞まで受賞している実績のある教材なんです。
この賞は単なる形式的なものではなく、実際の利用者からの声や導入実績、そして成果がしっかりと証明されていなければ得られないものです。
それだけ、多様な子どもたちにとって“本当に役立つ教材”として認められているという証拠ですね。
特に支援が必要な子どもたちや、既存の教育の枠組みにうまくフィットできなかった子たちが、自分のペースで学びを取り戻せる場を提供しているという点が大きな評価ポイントとなっています。
安心して学ばせたいと願う親御さんにとっても、この受賞歴は大きな信頼材料になると思いますよ。
発達障害(ADHD、学習障害など)の子にも適した設計で安心
発達障害のある子どもたちは、学習面でもそれぞれ異なる課題を抱えています。
集中が長続きしにくかったり、音や文字に過敏だったり、指示が曖昧だと混乱してしまうこともありますよね。
すららでは、そうした特性に配慮した設計が随所にちりばめられています。
たとえば、音声と文字の両方で情報を伝えたり、画面の切り替えスピードをゆっくりにしたり、明確なステップで進行するよう工夫されているんです。
また、キャラクターたちの口調や表情も、過度な刺激を与えないようにデザインされているので、安心して学習に向き合える環境が整っています。
一人ひとりの「やりやすさ」を大切にしているからこそ、無理なく続けられるんですね。
不登校で学校の授業に追いつけない子でも取り組みやすい
不登校の子どもたちが学習に戻る際にもっともつらいのが、「何から始めればいいのかわからない」という不安です。
教科書のどこからやり直すべきなのか、どれくらい遅れているのかが分からないと、やる気を失ってしまうんですよね。
すららはその点においても非常に配慮されていて、最初に診断テストを受けることで、子どもが「今どこにつまずいているか」を明確にしてくれます。
その上で必要な単元に戻って復習を開始できるため、「どこから始めても大丈夫」という安心感を持って取り組めるんです。
しかも、周りと比べられたり、評価されたりすることもないので、プレッシャーもなく自分のペースで再スタートできる環境が整っています。
つまづきをAIが解析→理解不足の箇所を自動で出題してくれる
子どもが「どこでつまずいているのか」を正確に見つけるのって、実はとても難しいことなんです。
でもすららでは、AIが子どもの回答傾向を分析し、理解が不足していると思われる単元や問題を自動でピックアップして出題してくれるんです。
これによって、本人が気づかないまま進んでしまうような“穴”を、事前にふさぐことができるんですね。
また、間違えた問題を繰り返し出すだけではなく、なぜ間違えたのかを丁寧に解説してくれるので、「わからないまま先に進んでしまう」ということもなくなります。
AIが優しく導いてくれるような感覚で、自然と「わかる→できる」体験を積み重ねていけるのは、すららの大きな強みなんですよ。
ポイント5・オンラインテスト&リアルタイム学力分析で、成果が見える
すららが多くの家庭に選ばれている理由のひとつが、「成果が見える化」されている点です。
子どもがどれだけ学んだか、どこが苦手なのか、どこが得意なのか――それらをすべてデータで確認できるから、親としても安心なんですよね。
子ども自身も「これだけできるようになった」と実感しやすく、学習に対して前向きな気持ちを持ち続けやすくなります。
特に、途中でモチベーションが下がりやすい家庭学習では、この「成果の可視化」が大きなカギになります。
すららなら、テストの点数だけでなく、取り組んだ内容や定着率などもすべてデータで把握できるので、「ちゃんとできているのかな?」という不安を抱えずに済むんです。
親子ともに嬉しい仕組みが詰まっていますよ。
小テストで間違えた問題を即フィードバックできる
すららでは、各単元ごとに小テストが用意されていて、学習した内容がちゃんと理解できているかどうかをすぐにチェックできるようになっています。
しかもその場で採点され、間違えた問題はすぐに解説が表示されるので、理解があやふやなまま次に進むことがありません。
この「その場でのフィードバック」が、学力の定着にはとても効果的なんです。
通常の学校のように、テストを受けてから何日も後に結果が返ってくるという形式ではなく、リアルタイムでの気づきと復習ができることで、「わかったつもり」を防いでくれるんですね。
苦手なところをすぐ修正できるこの仕組みは、特に家庭学習での継続にとって大きな助けになります。
定着度診断でAIがどこが苦手か把握し即対策問題を出してくれる
ただ学ぶだけでは、どこが身についていて、どこがまだ不安定なのか分かりにくいですよね。
すららでは、「定着度診断」と呼ばれるAIによる分析機能があって、子どもが理解できていない部分を自動的に見つけ出してくれます。
そのうえで、苦手な単元に絞った対策問題を優先的に出題してくれるんです。
これにより、ただ漫然と勉強するのではなく、「今の自分に必要な学習」を効率よく進めることができるようになります。
本人も「できない」をそのままにせず、小さな成功体験を積み重ねていけるので、モチベーションの維持にもつながります。
自分では気づけない弱点をAIがカバーしてくれるのは、本当に心強いですね。
保護者にもレポート配信し「何をどこまで理解しているのか」をしっかり確認できる
すららは、ただ子どもが勉強するだけの教材ではありません。
保護者にも定期的にレポートが配信され、「何をどこまで学習しているのか」「どれだけ理解できているのか」といった情報をしっかりと把握できるようになっているんです。
このレポートはグラフや数値で可視化されていて、とても見やすく、苦手や得意が一目で分かります。
忙しくて毎日学習を見守れない親御さんでも、これがあることで「うちの子、ちゃんと進んでるんだな」と安心できますよね。
また、コーチとのやりとりの内容やアドバイスも確認できるので、親子のコミュニケーションにも役立ちます。
見える化された成果は、信頼と安心につながるんです。
ポイント6・英語が「リスニング」「リーディング」「スピーキング」の3技能対応
学校英語では、どうしても「読み書き」中心の学習になりがちですが、実際の英語力として大切なのは「聞く」「読む」「話す」の3つのスキルがバランスよく育つことですよね。
すららの英語教材は、これら3技能をまんべんなくカバーしてくれる構成になっているのが大きな特徴です。
特に、実際の英検などでも重視される「リスニング」「スピーキング」までしっかり取り組めるのは、他の通信教材にはあまり見られない強みです。
ネイティブ音声を何度も聞きながら自然と耳を慣らしていき、発音練習や音読のチェックもできるから、本物の英語力が育っていくのを実感できるんです。
アニメーションを使って文法も丁寧に説明してくれるので、初心者でもつまずきにくく、楽しく続けられますよ。
ネイティブ音声のリスニングを学ぶことができる
英語を聞く力、いわゆるリスニング力は、教科書を読むだけではなかなか伸びませんよね。
でもすららでは、ネイティブの発音を何度でも聞くことができる教材が用意されていて、英語の「音」に自然と慣れていくことができます。
スピードもゆっくりから始まり、段階的に速くなっていくので、「聞き取れない…」という不安がないまま学習を進められるんです。
また、繰り返し聞いてから問題に挑戦することで、「音」と「意味」がしっかりリンクしていくのを実感できるようになります。
教科書英語に偏らない、実際に使える英語力を身につけたい方にとっては、このリスニング重視の構成はとても心強いポイントです。
音読チェックでスピーキング練習ができる
「英語を話す」というスキルは、意外と家庭学習では取り組みにくいものですよね。
でもすららなら、音読機能を使って、実際に声に出して読むことでスピーキングの練習ができるんです。
しかも、ただ読むだけではなく、正しい発音かどうかをチェックしてくれる仕組みもあるので、発音のクセや苦手な音を自分で把握できるのも魅力です。
最初は恥ずかしがっていた子どもも、キャラクターと一緒に練習していくうちにだんだん自信をつけていきます。
リスニングで覚えた英語を、音読でアウトプットする流れが自然に組み込まれているから、「聞く・話す」の循環ができて、英語力がしっかりと定着していくんですよ。
家にいながらスピーキングまで学べるって、本当にありがたいですね。
単語・文法もアニメーションで丁寧に解説してくれるから英検対策におすすめ
英語の基礎力として欠かせないのが単語と文法の知識ですが、それってどうしても「暗記っぽくなりがち」で、苦手意識を持ちやすいんですよね。
でもすららでは、アニメーションを使って、文法の仕組みや単語の使い方を視覚的にわかりやすく解説してくれるので、頭にすっと入ってくるようになります。
たとえば、過去形や疑問文のルールもキャラクターが丁寧に教えてくれるので、小学生でも安心して理解できますよ。
英検の対策としても使える内容がしっかり盛り込まれているので、「将来的に検定を受けさせたい」と考えているご家庭にとっても非常に頼れる教材です。
わかりやすく、しかも楽しく学べるからこそ、無理なく続けられるんですね。
ポイント7・料金体系が「1人分じゃない!」兄弟OK&科目追加自由
通信教材って、「兄弟それぞれに契約が必要」と思っている方が多いかもしれません。
でもすららは違います。
なんと1つの契約で、兄弟や姉妹が一緒に使えるという驚きの料金体系になっているんです。
しかも追加料金は不要。
さらに、学年をまたいだ科目の選択も自由なので、「小学生の兄と中学生の妹がそれぞれのレベルで学習する」といった使い方もできるんですよ。
家庭全体で教育コストを抑えながら、質の高い学びを提供できるこの仕組みは、本当にありがたいですよね。
特に複数のお子さんを育てているご家庭にはピッタリ。
「1人分の値段で、家族全員が賢くなれる」そんな夢のような仕組みが、すららには整っているんです。
1つの契約で兄弟同時利用OK!(人数分の追加料金なし)
すららの大きな魅力の一つが、1契約で複数の子どもが一緒に使えるという点です。
一般的な教材では、それぞれに個別契約が必要になるため、兄弟がいる家庭だと費用が倍以上になってしまうことも珍しくありません。
でもすららでは、その必要がありません。
兄弟それぞれのアカウントを持ちながら、同じ契約内で自由に利用できるんです。
しかも追加料金も発生しないというのだから驚きです。
これなら、学年の異なる子どもたちをそれぞれのペースで学ばせることができるし、家計への負担も抑えることができますよね。
コスパの良さと教育効果を両立したいご家庭には、本当におすすめのシステムです。
小学生の兄と中学生の妹、同じ契約内で利用できるからコスパがいい
たとえば、小学4年生のお兄ちゃんと中学1年生の妹さんがいるご家庭でも、すららなら同じ契約の中でそれぞれに合った学習内容を進められるんです。
これって本当に画期的ですよね。
一般的には、学年ごとに教材を変える必要があったり、兄弟分の費用がかかったりしますが、すららならそうした心配はいりません。
むしろ兄弟で取り組むことで、お互いに刺激を受けながら学習意欲も高まっていくケースも多いんです。
同じ教材を使っていても、学習内容は個別に設定できるから、無理なくそれぞれのペースで進められます。
家族全体で「勉強する習慣」が自然と身につく、そんな素敵な環境を整えてくれるのがすららの強みなんです。
科目ごとに選んで追加できるから、無駄がない
すららでは、必要な科目だけを選んで学習できるシステムも大きな魅力です。
たとえば「国語と算数だけで十分」という場合は、その2教科のみを契約すればOKなんです。
反対に「英語も追加したい」と思えば、後から追加することも可能です。
この柔軟な設計があるおかげで、無駄な費用をかけずに本当に必要な学習だけをピンポイントで取り入れることができるんですよ。
お子さんの学習状況に応じて、科目の組み合わせを変えられるので、成長に合わせたカスタマイズができるのも嬉しいポイントです。
無理なく、無駄なく、そして効率よく。
家庭ごとのニーズにしっかり応えてくれるのが、すららならではの魅力なんです。
【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材にはないすららのメリットについて
最近「すららってうざいのでは?」といった声がネットでチラホラ見かけることもありますが、それって本当に中身を知らずに誤解してるだけかもしれません。
実際に中身を知れば、「え、こんなに手厚いの?」と驚く保護者の方も多いんですよ。
市販のタブレット教材は数多くありますが、すららがここまで長く支持されているのにはちゃんと理由があるんです。
特に対人サポートの充実度、学びの柔軟性、発達や学力に課題のあるお子さんへの対応力など、他の教材とは一線を画しています。
ここでは、そんな「すららだけの強み」に焦点を当てて、他の教材との違いをしっかりとお伝えしていきますね。
使って初めてわかるその魅力、ぜひ知っておいて損はありませんよ。
メリット1・対人サポート付き!「すららコーチ」がある
多くの家庭用教材が「自動で進む」「AIが判断」などと自立型をうたっている中で、すららの最大の特徴はやはり“人の力”を活かしたサポート体制にあります。
それが「すららコーチ」の存在です。
AIによる分析も素晴らしいですが、やはり子どもは人とのやりとりから大きな影響を受けます。
すららでは、学習状況やつまずきを人が見てアドバイスしてくれる仕組みがあるからこそ、つまずいた時も一人じゃない安心感があるんです。
親が毎日見張る必要もないし、プロに任せられるから負担も軽くなります。
勉強の面倒を見きれない…そんなおうちにこそ、ぴったりのサービスですよ。
子どもに合った学びを、優しく支えてくれる“人の存在”があるって、本当に心強いです。
すららはプロの学習コーチが進捗を管理してくれる
家庭学習を続けるうえで、最大の壁って「継続」だと思いませんか?最初はやる気があっても、ついサボってしまったり、何をすればいいかわからなくなったり。
すららでは、そんな問題を「すららコーチ」が解決してくれます。
このコーチはただのサポート担当ではなく、教育の専門的な視点から学習の進捗を丁寧に見守ってくれる存在なんです。
子どもの理解度に応じて進度を調整したり、モチベーションが落ちたときには声かけしてくれたりと、きめ細かいフォローが受けられるんですよ。
「毎日見張るのは無理…」と感じている親御さんにとって、これはまさに救世主のような存在です。
コーチの存在があるからこそ、学習習慣が自然と身についていきます。
コーチが学習スケジュールを子どもに合わせて作成してくれる
教材を用意しても、結局「今日は何をどこまでやるの?」と子どもが迷ってしまい、学習が進まない…そんな経験はありませんか?すららでは、そんな不安を解消するために、コーチが一人ひとりに合わせた学習スケジュールを作成してくれます。
たとえば、朝が苦手な子には夜に集中したスケジュールを、週末に習い事がある子には平日を中心に、といった具合に、その子の生活リズムや性格に寄り添った無理のない計画が立てられるんです。
「計画倒れ」になりにくく、自分のペースで続けやすいのも、このパーソナライズされたスケジューリングのおかげです。
コーチがついていてくれるという安心感は、親だけでなく、子ども自身の自信にもつながりますよ。
メリット2・不登校・発達障害対応に特化している
すららが他の教材と大きく異なるのは、「平均的な子ども」に合わせた一律型ではなく、発達障害や不登校の子どもにも配慮された設計になっている点です。
たとえば、学校に通えない子でも無理なく自宅で学べるように、やさしい導入や繰り返し学習ができるようになっていたり、ASDやADHDの子が集中しやすい画面構成や操作性が考えられていたりと、細部にまでこだわりが詰まっています。
しかも、文部科学省からも推薦されるほど、その教育的効果が高く評価されているのも信頼できるポイントです。
誰一人取り残さない、という理念がしっかりと貫かれていて、「うちの子には合わないかも」と不安を感じているご家庭にこそ、ぜひ知ってほしい教材です。
不登校や発達障害の子向けに、文科省推薦教材として採用されてる実績がある
すららは、全国の自治体や学校からも評価されており、文部科学省が推奨する教育プログラムのひとつとして、多くの現場で採用されてきた実績を持っています。
これは単なる民間サービスという枠を超えて、公共性や教育効果の高さが認められている証でもあります。
特に、不登校や発達障害のある子どもにとっては、「学校と同じ教材は合わない」という声が多く聞かれますが、すららはそうした子たちが学びやすいように構成されているんです。
授業の進め方や説明のスピード、操作のしやすさなど、すべてが「やさしさ重視」で設計されているから、安心して導入できるんですね。
信頼できる実績があるからこそ、多くの学校でも選ばれているんです。
不登校児童に対して「出席扱い」される学校も多い
すららを導入している自治体や学校の中には、学習状況に応じて「出席扱い」として認定しているケースも少なくありません。
つまり、学校に実際に通っていなくても、すららでの学習が一定の基準を満たせば「ちゃんと学んでいる」と見なされるんです。
これは、不登校のお子さんにとって大きな自信と安心につながる制度ですよね。
「通えない=何もしていない」ではなく、「自宅で努力している」ということが、正式に認められる。
そんな環境が整っているからこそ、子ども自身も前向きな気持ちで学習を続けられるようになりますし、保護者の心の負担も軽くなるはずです。
学校と連携しながら、学びを止めない工夫がされているのが、すららの強みなんです。
ASD・ADHD・LD(学習障害)に合わせたカリキュラム&サポートが受けられる
子どもによって得意・不得意や集中力の持続時間、刺激の感じ方などはまったく異なります。
特にASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)、LD(学習障害)といった特性を持つお子さんには、それに合った教材選びがとても大切です。
すららはこうした多様な特性を理解したうえで、必要なサポートやカリキュラムの設計がなされています。
音声と文字のバランス、画面の切り替えのスピード、キャラの表情や話し方までが繊細に調整されていて、「やさしい学び」が提供されているんです。
さらに、学習の進め方や取り組みやすさに関しても、保護者がコーチと相談しながら調整できるので、子どもの安心感も格段に高まります。
メリット3・学年を超えた「無学年学習」ができる
すららの大きな特徴のひとつが、この「無学年学習」という仕組みです。
一般的な学校の授業や通信教材だと、学年ごとに内容が固定されていて、「わからない単元があっても進まざるを得ない」「先取りしたくても制限がある」なんてことも多いですよね。
でも、すららではそんな心配は一切ありません。
子どもの理解度に合わせて、前の学年にさかのぼることも、逆に得意分野をどんどん先に進めることも自由なんです。
この柔軟さがあるからこそ、「勉強がわからない…」というストレスが減り、自分のペースで無理なく進めていけるんですね。
成績に追われず、安心して学び直せる環境が整っているという点は、まさにすららならではの魅力です。
学年関係なく自由にさかのぼり・先取りできる
「小学生だけど中学英語が得意」「中学生だけど小学校の算数につまずいている」――子どもの理解度は、本当に十人十色です。
でも、学校や一般教材ではどうしても学年がベースになってしまい、自分に合った学習ができないこともありますよね。
すららの無学年式は、そうした固定概念を取り払い、必要な単元を自由に学べるようになっています。
たとえば、過去に習った内容を復習し直すのも簡単だし、興味のある先の内容に挑戦するのもOK。
学年に縛られないことで、「やりたいところをやれる」「わからないところは戻って確認できる」という、自分にぴったりの学び方が叶うんです。
これが、子どもの「自分で考えて学ぶ力」を育ててくれるんですよ。
発達障害の子は「つまずいたまま進まない」からマイペースに進められるのはポイント
発達障害のある子にとって、「つまずいたまま授業が進んでしまうこと」ほど大きなストレスはありませんよね。
でも、すららの無学年学習ならその心配はありません。
本人の理解度に合わせて、ゆっくりじっくり、必要なだけ時間をかけて取り組める仕組みだからです。
「みんなが進んでいるから自分もやらなきゃ」というプレッシャーもなく、自分のペースで学べる安心感があるんですよ。
特に、注意がそれやすかったり、集中にムラがあったりする子には、この自由度がとても合っているんです。
決まった時間や内容に縛られず、「できるところから始める」「わかるまで繰り返す」が当たり前にできる環境って、学習の土台を築くうえで本当に大切なんですよね。
メリット4・AI診断×対人コーチングで学習設計が精密
すららが他の教材と大きく違うのは、「AIによる分析」と「人間のコーチング」のダブル体制で子どもの学習をサポートしてくれるところです。
AIだけでも優秀なサポートは受けられるけれど、そこに“人の目”が加わることで、さらにきめ細やかで精度の高い学習設計が可能になるんですね。
たとえば、AIが提示したデータを元に、すららコーチが個別の生活スタイルや性格を考慮して学習プランを調整してくれるから、「ただやらせる」のではなく、「その子にとって無理のない形」で進めることができるんです。
だからこそ、勉強が苦手な子も無理なく続けられるし、得意な子はどんどん伸ばせる。
すららならではの“人とAIの最強タッグ”が、学びの質を大きく高めてくれますよ。
AI+人間コーチのWサポートはすららだけのポイント
学習をサポートしてくれる存在がAIだけだったら、どうしても画一的な対応になってしまいがちですよね。
でもすららでは、AIが学習データをもとに分析を行い、それを人間の「すららコーチ」が確認・調整してくれるという、他にはないWサポート体制が整っているんです。
AIの得意分野である“正確な解析”と、人間の得意分野である“共感や柔軟な対応”が組み合わさることで、まさに最適な学習環境が生まれるんですよ。
子どもの苦手や得意、つまずきのパターンまで細かく把握できるので、学習効果はぐんとアップします。
「AIに任せるのはちょっと不安…」という保護者の方にも、この体制なら安心して任せられますね。
AIだけではフォローしきれない細かい学習状況を、コーチが調整してくれる
AIの分析は確かに優秀ですが、それだけでは対応しきれない部分もあるんですよね。
たとえば「最近、学校で忙しくて集中できていない」「家庭環境の変化でペースが落ちている」といった、数字には現れない“人間らしい変化”ってありますよね。
すららコーチは、そうした細かい状況まで把握し、必要に応じて学習ペースや内容を調整してくれるんです。
子どもとのやり取りを通じて、「今この子に必要なサポートは何か?」を見極めてくれるので、一人ひとりに最適な学習プランが提供できるんですね。
まさに、AIと人の力が組み合わさった、最強のチームです。
数字に表れない部分にも目を配ってくれるからこそ、安心して任せられるんですよ。
メリット5・紙を使わず、すべてデジタルでも「記述力」が鍛えられる
すららの最大の特徴のひとつが、紙のワークを使わず、すべてデジタル上で完結する学習スタイルにもかかわらず、「記述力」までしっかり鍛えられることです。
多くのデジタル教材は選択肢を選ぶだけの形式が多い中で、すららはあえて“自分の言葉で書く力”を伸ばすことに重点を置いています。
記述式問題が用意されており、AIやすららコーチによる添削・フィードバックを通して、自分の考えを論理的に整理し、相手に伝える文章力を自然と育てていける設計なんです。
紙のノートを使わないことで、手が疲れやすい子どもにもやさしく、気軽にトライしやすいのも魅力ですね。
学びながら書く力も伸ばせる教材は、なかなか貴重な存在です。
「論理的に書く力」「説明する力」にフォーカスしたカリキュラム
すららでは、ただ文章を書かせるだけでなく、「どのように考えをまとめ、わかりやすく説明するか」という力を段階的に育てるカリキュラムが用意されています。
例えば、読んだ内容を要約してみたり、自分の考えを他人に伝える形式でアウトプットさせたりと、実生活でも役立つ記述力がしっかり鍛えられていくんです。
また、論理構成の基本となる「起承転結」や「理由→結論」といったフレームも、自然と身につくよう工夫されています。
こうしたスキルは、今後の受験や社会での表現力にも直結するので、早いうちからトレーニングしておくことがとても大切なんです。
すららなら、ゲーム感覚でそれができちゃうのが嬉しいですね。
読解+記述のトレーニングがデジタル完結でできる教材は珍しい
読解と記述を組み合わせた学習を、すべてオンライン上で完結できる教材は、実はそれほど多くありません。
多くの学習アプリは選択問題や暗記型のクイズに偏りがちですが、すららはそこを一歩先へ進めています。
物語文や説明文を読んだあとに、自分の考えを書く、まとめる、意見を述べるといったアウトプットが求められる構成になっていて、まさに“デジタルで作文力を鍛える”という珍しいスタイルなんです。
しかも、入力方式も子どもにやさしい設計なので、キーボード操作が不慣れでも安心。
紙ではつまずきやすい子も、画面上なら抵抗なく取り組めるケースが多いです。
現代の学びにマッチした教材といえるでしょう。
メリット6・途中でやめても「再開」がしやすい
子どもたちの学習には波がありますよね。
とくに不登校や発達障害を持つお子さんにとっては、「調子が良い日」「どうしても気持ちが乗らない日」が交互にやってきます。
すららは、そうした子どもたちの状態に配慮して、途中で中断しても、またすぐに再開しやすいシステムになっているんです。
一度お休みしても、学習の履歴や進捗がすべて保存されているので、何をどこまでやったかが一目で分かります。
そのため、「前どこまでやったっけ?」と迷うこともなく、ストレスなく再開できるんです。
日々の学習に波があっても、その子なりのペースで歩みを進められる環境は、まさに“やさしい教材”と言えるでしょう。
すららは一時中断→復帰が簡単にできる
他の学習教材では、一度中断してしまうと「どこまで進んだかわからなくなった」「前の内容を忘れてしまって再開できない」といった声をよく耳にします。
でもすららでは、すべての学習履歴やテストの結果がクラウド上に保存されているので、いつでもその続きから再開することができるんです。
また、必要であれば過去の単元に戻って復習することも簡単にできます。
だからこそ、少し休んでも焦ることなく、「またやってみようかな」という気持ちが芽生えたタイミングですぐに取り組めるんですね。
復帰のしやすさは、継続につながる非常に重要なポイントです。
不登校や発達障害の子は「学習ペースに波がある」から、自由に休んで戻れる環境は重要
毎日同じペースで学習できる子ばかりではありません。
特に不登校の子や、発達障害を持つお子さんの場合は、体調や気分に大きく左右されることが少なくありません。
そんなとき、無理に学習を進めようとすると、かえって逆効果になることもあります。
すららは、そうした「波のある学習ペース」に合わせて、自由に休み、また戻ってこれる設計になっているのが大きな魅力です。
しかも、再開時にはどの単元から始めるべきかのガイドもあるので、自分のリズムで安心して復帰することができます。
継続だけを求めるのではなく、柔軟さを持たせたシステム設計こそが、すららが支持される理由のひとつなんですよ。
メリット7・出席認定・教育委員会との連携実績がある
すららは、ただの学習教材にとどまらず、実際に「学校の授業の代わり」として認められるほどの信頼を獲得しています。
全国各地の学校や教育委員会と連携しており、すららで学習を継続することで“出席扱い”と認められるケースが多数あるんです。
これにより、不登校中の子どもたちが将来的に進学で不利にならないようサポートする体制が整っています。
また、学校現場や医療機関と連携しながら、子どもの学習をフォローアップする仕組みもあり、まさに社会全体で子どもの学びを支えるモデルとして注目されているんです。
「家庭でも安心して勉強を続けられる」だけでなく、「学校とつながりを持てる」というのは、親にとっても子にとっても大きな安心材料ですよね。
すららを使っていると「出席扱い」として学校が認めるケースが多数
すららを導入している家庭では、すでに多くの自治体や学校から「出席扱い」の認定を受けた実績があります。
これは、単に教材としての質が高いだけでなく、「継続的な学習記録が残る」「学力の定着を支援する体制がある」といった信頼に基づいているからです。
不登校や体調不良などで学校に通えない場合でも、すららで学び続けることで、出席日数としてカウントされるのは、進学や評価の上でも非常に重要なこと。
学校との連携をスムーズに行う方法もサポートされているので、保護者の負担も少なくて済むんですよ。
実績があるからこその安心感です。
不登校支援教材として、学校や病院と連携しているのはすららならでは
すららは不登校支援教材として、学校だけでなく、医療機関や支援センターとも連携を行っている数少ない教材です。
たとえば、病院での療養中の学習支援や、スクールカウンセラーとの協力のもとでの活用も進んでおり、子どもの状況に応じた多角的な支援が受けられる仕組みが整っています。
こうした連携は、単なる“家庭学習ツール”の枠を超えた存在感を持っている証拠でもありますよね。
教育委員会や学校現場との連携があるからこそ、子どもが「自分はひとりじゃない」と感じられることにもつながります。
すららは、学びの継続だけでなく、心のつながりまでサポートしてくれる存在なんです。
【すらら】はうざいと言われる原因は?すららのデメリットについて紹介します
すららは非常に評価の高い教材ですが、すべての子どもにとって「完璧」かと言われれば、そうとは限りません。
実際に「うざい」と感じる人がいるのも事実です。
これは教材そのものというより、学習スタイルや子どもの性格、家庭環境による影響が大きいんですよね。
すららはサポートが充実している分、干渉されていると感じてしまったり、自分のペースで進めたい子には逆にプレッシャーになることもあるようです。
でもこれは裏を返せば、それだけ手厚いフォローがあるという証でもあります。
ここでは、実際に「合わなかった」と感じるケースについて、よくある声をもとに整理しながら、それぞれの背景や対処法についてもご紹介していきますね。
原因1・すららコーチやサポートからの連絡がしつこいと感じることがある
すららの大きな魅力のひとつである「すららコーチ」ですが、人によってはそのサポートが少し“干渉的”と感じることもあるようです。
特に、何でも自分で進めたいタイプの子や、マイペースにやりたい家庭にとっては、「連絡が多い」「進捗確認がうるさい」と感じることがあるみたいです。
でもこれって、逆に言えば“放置されない”という安心材料でもあるんですよね。
サボり癖がある子にはピッタリですが、自立型の子どもにとっては余計なお世話に思えるかもしれません。
そんな時は、コーチとの連絡頻度を調整したり、希望を伝えることである程度対応してもらえるので、まずは遠慮なく相談してみることをおすすめします。
使い方を工夫すれば、無理なく活用できますよ。
自主的にやりたい子や、放っておいてほしい子には合わないこともある
すららの特長である「コーチによる学習サポート」は、子どもにとっては励みになる一方で、「自分のペースで進めたい」と考える子には少し窮屈に感じてしまうこともあります。
特に、もともと学習習慣がしっかりしていたり、自主性の強い子の場合、「あれやった?」「進んでる?」という確認がプレッシャーになってしまうこともあるんです。
もちろんこれは、すららが悪いわけではなく、性格や家庭の教育方針との相性の問題なんですよね。
すららでは、必要に応じてコーチの関わり方を調整してもらうこともできますので、合わないと感じた場合は柔軟に相談することで解決するケースも多いですよ。
無理に合わせるのではなく、環境に合わせて活用することが大切です。
原因2・「やらされ感」が強くなるとプレッシャーに感じることがある
すららはAIやコーチがしっかりと学習計画を立ててくれるぶん、「やらなきゃ」という気持ちが強くなりすぎてしまう子もいるようです。
本来は助けになるはずの仕組みが、義務のように感じられると、学習そのものがストレスになってしまうこともあります。
特に完璧主義だったり、自分を追い込みがちなタイプの子には、計画通りにいかないことがプレッシャーになることもあります。
でもこの点に関しても、すらら側で調整は可能なんです。
「今日はここまでやればOK」といった柔軟な目標設定をすることもできるので、過度に真面目に取り組んでしまう子ほど、親が一緒にフォローしてあげると安心です。
うまく使えば、無理なく継続できる仕組みなんですよ。
自動で学習計画を作ってくれるAIに縛られていると感じてしまうことがある
すららでは、AIが子どもの理解度や進度を分析して、最適な学習計画を立ててくれます。
これ自体は非常に便利な機能なんですが、中には「自由にやりたいのに、勝手に決められている感じがして嫌だ」と感じる子もいます。
特に自由度の高い学習スタイルに慣れている子にとっては、「次はこれ」「今日はここまで」とAIに指示される流れが窮屈に映ってしまうこともあるようです。
でも、すららのAIは絶対的な指示ではなく、あくまで“提案”なんですよ。
無理に従う必要はなく、スキップしたり、やりたい部分だけ選んで学ぶことも可能です。
親子で一緒にスケジュールを見ながら、「今日はこの単元にしようか」と話し合って調整することで、ストレスなく進められるようになりますよ。
原因3・キャラクターやナビゲーションが子どもっぽい・くどいと感じることがある
すららの特徴として、アニメキャラクターによる対話型の授業があるのですが、それが一部の利用者にとっては「子どもっぽい」「くどい」と感じられてしまうことがあるようです。
特に高学年や中学生、思春期に差し掛かった子どもたちにとっては、「アニメで話しかけてくる」ことが逆にイライラの原因になってしまうケースも見られます。
もちろん、多くの子には親しみやすくモチベーションを引き出す手段として機能していますが、年齢や性格によっては「もう少し落ち着いたトーンの方が合う」という声もあるのが事実です。
そうした声がSNSなどで拡散され、「すららは子どもっぽすぎてうざい」といった印象が先行してしまう場面もあるのかもしれませんね。
高学年や思春期の子にはキャラクターがうざいと感じることがある
すららに登場するキャラクターたちは、明るく元気に、子どもに語りかけるようなスタイルで学習をサポートしてくれます。
ただし、そういった演出は低学年や勉強に苦手意識のある子には効果的な一方で、高学年や思春期を迎えた子どもには逆効果になってしまうこともあります。
「なんでこんなにテンション高いの?」「もう少し普通に教えてほしい」といった声が出るのも、その年代特有の感受性ゆえでしょうね。
大人びた感覚を持ち始めた子にとっては、キャラクターのテンションや語りかけが子どもっぽく感じられ、「うざい」「くどい」と思われてしまうのも仕方ない部分かもしれません。
使い方の年齢調整が、今後の課題かもしれませんね。
原因4・勧誘や営業の印象が「しつこい」と感じる人がいる
インターネット上では、すららの営業や案内について「しつこい」と感じるという声も一部で見られます。
特に無料体験や資料請求をしたあと、一定期間で電話やメールなどの連絡があるため、それを「営業がうざい」とネガティブに受け取る人もいるようです。
ただこれは、逆に言えば「しっかりフォローしてくれている」という証でもあり、保護者の不安を解消しようとする真摯な姿勢の表れでもあります。
ただし、タイミングや回数によっては負担に感じる方もいるでしょうから、「もう少し控えめにしてほしい」という意見が出てしまうのも理解できますね。
このあたりは感じ方の差が大きい部分ではありますが、SNSではどうしてもネガティブな印象が拡散されやすい傾向にあります。
「連絡が頻繁」と感じると、SNSでは「うざい」と言われることがある
すららでは、資料請求や体験申し込みをした方に対して、電話やメールなどでフォローアップを行っているのですが、人によってはその連絡の頻度を「多すぎる」と感じることもあるようです。
特に「一度資料を見ただけ」「まだ検討段階」という方にとっては、連絡がくるたびにプレッシャーを感じてしまい、「しつこいな」「営業うざい」とネガティブな感情を抱くこともあるようです。
そのような声がSNSで拡散されると、まだ利用したことがない人にも「すららって営業が強引なんでしょ?」という印象を与えてしまうことにつながります。
ただ、連絡を止めたい場合はきちんと伝えれば対応してくれるので、過度に恐れる必要はありません。
丁寧な対応をしてくれる企業であることは確かです。
原因5・料金が高く感じる割に効果が実感できない場合がある
すららは他のタブレット教材に比べてやや料金が高めに設定されているため、「価格の割に効果がわからない」という声が出ることもあるようです。
特に、「タブレット学習=放っておいても勝手に伸びる」と思ってしまうと、思ったような結果が出なかったときに「お金をかけた意味がなかった」と感じてしまうのかもしれません。
すららは、ただの動画教材ではなく、しっかり取り組めば確実に力がつく仕組みになっていますが、その分、ある程度の継続と家庭のサポートも求められます。
「やらせっぱなしでは成果が出にくい」というのは、どんな教材でも同じですよね。
そのため、活用法や子どもとの相性によって、満足度に差が出るのは当然のことなのかもしれません。
子供が1人で学習に取り組めないままだと勉強効果を実感できない保護者もいる
すららは自宅学習をサポートしてくれる強力なツールですが、「使えばすぐに成績が上がる」という魔法の教材ではありません。
子どもが主体的に学習に取り組む姿勢がないままだと、せっかくの機能も十分に活かしきれず、保護者としては「こんなにお金を払っているのに…」と不満に思うこともあるようです。
とくに、小学生のうちはまだ自己管理が難しいため、親の声かけやサポートもある程度は必要になります。
すららにはコーチによるフォローがありますが、やはり「完全に放っておいて大丈夫」というわけではありません。
使い方次第で大きな成果が出る教材であるからこそ、ある程度の親子の協力体制もセットで考えておく必要がありますね。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは高い?すららの料金プランについて紹介します
「すららってちょっと高くない?」という声も見かけますが、実はその中身をよく見ると、かなりコストパフォーマンスが良いんです。
一般的なタブレット教材では、ただ教材を渡して終わりというケースもありますが、すららは“プロのコーチが付く”という強力なサポート体制が整っているのが大きな違いです。
また、発達障害や不登校の子にも対応している専門性の高いカリキュラム、AIを活用したつまずき分析、学力の見える化など、単なる教材以上の価値がありますよ。
料金を“ただの月額”と見ると割高に感じるかもしれませんが、家庭教師や塾に通わせるよりは圧倒的にリーズナブルです。
今回はそんなすららの料金プランについて、わかりやすく紹介していきますね。
すらら家庭用タブレット教材の入学金について
すららの利用を始める際には、最初に入学金がかかります。
これは1回限りの費用で、利用するコースによって金額が異なります。
たとえば、「小中・中高5教科コース」は7,700円(税込)と比較的お手頃で、主要5教科をまとめて学べるプランとしては非常に良心的です。
一方、「小中・中高3教科」「小学4教科コース」は11,000円(税込)とやや高めではありますが、サポート体制や教材の質を考えると納得の内容です。
市販のドリルや通信教材と比べると少し高い印象があるかもしれませんが、すららは「学びやすさ」と「続けやすさ」をしっかり支える仕組みがあるので、最初にしっかりと準備することで安心してスタートが切れます。
子どもの未来への投資として見れば、決して高い買い物ではないですよ。
| コース名 | 入学金(税込) |
| 小中・中高5教科コース | 7,700円 |
| 小中・中高3教科、小学4教科コース | 11,000円 |
すらら家庭用タブレット教材/3教科(国・数・英)コース月額料金について
すららの月額料金については、選ぶプランや支払い方法によって金額が変わります。
ここでは3教科(国語・数学・英語)のコースについて詳しく説明していきますね。
金額だけ見ると一見「高いかも?」と感じるかもしれませんが、実はサービスの中身を知れば知るほど「この値段でここまでやってくれるの?」と驚く方も多いんです。
AIによる学習分析、つまずき対応、そして何より“人”によるコーチングまでついてこの価格というのは、他のタブレット教材にはない魅力です。
しかも、4ヵ月継続コースを選べば毎月の負担も少し軽くなるので、家計を見ながら無理なく続けられるのも嬉しいポイントですね。
それでは次に、支払いパターン別の料金を具体的に見ていきましょう。
毎月支払いコースの料金
まずは、もっともスタンダードな「毎月支払いコース」の料金から紹介します。
このプランでは、小中コース・中高コースともに月額8,800円(税込)となっていて、どちらも3教科(国語・数学・英語)をカバーしています。
料金の中には、すららコーチによる学習サポート、AI分析、個別の進捗管理、定着度診断などがすべて含まれており、非常に手厚い内容となっています。
毎月の金額としては決して安くはないかもしれませんが、塾や家庭教師の料金と比較すると圧倒的にリーズナブルですし、何より子どもの特性に合わせて丁寧に対応してくれるところが、すららならではの魅力です。
「まずは気軽に試してみたい」という方にもぴったりのコースとなっていますよ。
| コース名 | 月額 |
| 小中コース | 8,800円 |
| 中高コース | 8,800円 |
4ヵ月継続コースの料金
もっとお得に利用したい方には「4ヵ月継続コース」がおすすめです。
このプランでは、月額が8,228円(税込)と、毎月支払いプランより少しだけ割安になっています。
年間で見ると数千円の差にはなりますが、「塵も積もれば山となる」ですよね。
継続を前提としたこのプランは、学習習慣をしっかり定着させたい家庭に向いています。
また、短期で効果を求めるよりも、子どものペースでじっくりと理解を深めていきたい場合に特におすすめです。
すららのコーチや教材は、使い続けることでその良さがじわじわと実感できるものなので、ある程度の期間続けるつもりならこのプランの方が断然お得です。
コストと成果のバランスを考えるなら、こちらの選択肢も検討する価値がありますよ。
| コース名 | 月額 |
| 【4ヵ月】小中コース | 8,228円 |
| 【4ヵ月】中高コース | 8,228円 |
すらら家庭用タブレット教材/4教科(国・数・理・社)コース月額料金について
すららでは、国語・算数(数学)・理科・社会の4教科を対象としたコースも用意されています。
まず「小学コース(毎月支払い)」は月額8,800円で、学年に関係なく幅広く学べるのが特徴です。
一方、「小中コース(4ヵ月継続コース)」を選ぶと、月額はやや抑えられて8,228円となり、長期的に継続する意志がある方にはこちらが断然お得です。
月ごとに料金が違うことで、自分の家庭スタイルに合った契約ができるのが嬉しいですよね。
毎月払って様子を見たい方もいれば、最初から4ヵ月がっつり学びたいという方もいるはず。
そんな多様なニーズに応えてくれるのが、すららの良いところです。
料金は一見すると高く感じるかもしれませんが、教材の質・サポートの手厚さ・対象範囲の広さを考えれば、十分納得の価格帯です。
| コース名 | 月額 |
| 小学コース(毎月支払いコース) | 8,800円 |
| 小中コース(4ヵ月継続コース) | 8,228円 |
すらら家庭用タブレット教材/5教科(国・数・理・社・英)コース月額料金について
5教科対応のコースになると、英語まで学べるようになるため、将来を見据えてしっかり学ばせたい家庭には非常に人気があります。
国語・算数(数学)・理科・社会・英語がすべてカバーされているので、学校の授業対策はもちろん、中学受験や高校進学にも役立つ力をつけられるのが魅力です。
英語が加わることで「高いのでは?」と思われがちですが、内容を見ればむしろ割安感さえ感じられる充実ぶり。
毎月支払いか、4ヵ月継続で申し込むかによっても価格が変わってくるため、ライフスタイルに合わせた選択がしやすくなっています。
「家庭学習だけで5教科すべてのフォローは大変…」というご家庭にとって、すららの5教科対応は本当に助けになる存在だと思いますよ。
毎月支払いコースの料金
毎月支払いコースの5教科対応版では、小学コースも中高コースも同一価格で、月額10,978円です。
この価格には、国語・数学(算数)・理科・社会・英語の5教科すべての学習コンテンツと、「すららコーチ」などのサポート機能も含まれています。
他のタブレット教材だと、英語は別課金だったり、サポートがついていなかったりすることも多いですが、すららはそれらをすべてまとめてこの価格なので、むしろ安心できるという声も多いんですよ。
毎月支払いなら、まずは気軽にスタートして様子を見ることができるので、「いきなり契約するのはちょっと不安…」というご家庭にもおすすめです。
教材の質やコーチの対応を体感してから、継続するかどうかを決められるのも大きなメリットですね。
| コース名 | 月額 |
| 小学コース | 10,978円 |
| 中高コース | 10,978円 |
4ヵ月継続コースの料金
すららの5教科コースを4ヵ月以上継続する予定があるなら、断然お得なのがこの「4ヵ月継続コース」です。
小中コース・中高コースともに、月額10,428円と毎月支払いよりも550円お安くなります。
たった550円と思うかもしれませんが、1年継続すれば6,600円もの差になるので、長期的に見るとかなりお得感がありますよね。
加えて、学習のリズムをきちんとつけたい方にとっても、4ヵ月という単位は無理がなく、ちょうど良い区切りになるんです。
実際に使っているご家庭からは「料金に対して教材とサポートの質が非常に高く、満足度が高い」との声も多数寄せられています。
お子さんの学びにしっかりと投資したい方には、このコースは非常におすすめです。
| コース名 | 月額 |
| 【4ヵ月】小中コース | 10,428円 |
| 【4ヵ月】中高コース | 10,428円 |
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの勉強効率や勉強効果は?コースについて紹介します
「すららって本当に勉強になるの?」「効果あるの?」と疑問に感じている方もいらっしゃるかもしれません。
でも実際に使ってみると、その“効率の良さ”と“成果の出やすさ”に驚く声が多いんです。
特に、3教科(国語・数学・英語)に絞ったコースでは、基礎から応用までを短時間で無理なく学べる構成になっていて、限られた時間の中でも「できる実感」が得られやすいんですよ。
さらに、学年に縛られない無学年式なので、つまずいた単元までさかのぼってやり直せる一方で、得意なところはどんどん先に進めるのが魅力です。
学校の授業に合わせるだけでなく、自分のペースで「わかる→できる」に変えていくすららの学習設計は、本当に効率が良いんです。
すらら3教科コース(国・数・英語)の勉強効果について紹介します
すららの3教科コースは、学校の成績を上げたい子どもたちにとって非常に効果的です。
このコースは、国語・数学・英語という主要科目に特化しており、それぞれの教科で“わからない”を“わかる”に変えていく仕組みがしっかり設計されているんですよ。
たとえば国語では文章の構造を視覚的に理解できるよう工夫されていたり、数学ではアニメーションで図形が動いて直感的に学べたりと、「苦手意識を持ちやすい教科こそ、丁寧に学べる」設計になっているのがすららの強みです。
英語もリスニング・リーディング・スピーキングをバランスよく学べるよう工夫されていますし、テスト対策にも直結しています。
家庭学習でここまで本格的に、しかも楽しく学べる教材はなかなかありませんよ。
勉強効果1・基礎力の定着がとにかく早い
すららの学習設計は、基礎を徹底的に固めることに特化しています。
「わかったつもり」で先に進んでしまうことが多い子どもにとって、これは大きなメリットです。
たとえば、苦手な単元で間違えた場合には、AIがつまずきの原因を分析して、必要な単元まで自動的に戻ってくれるんです。
これにより、基礎的な知識が本当に身についているかを確認しながら進めることができ、結果として“定着の速さ”がぐんと上がります。
さらに、視覚的に理解しやすいアニメーション解説があることで、「見てわかる」感覚を育てながら、しっかりと土台を築いてくれるんです。
勉強の習慣がまだついていない子でも、「わかる楽しさ」によって自然と集中力が持続するようになりますよ。
勉強効果2・短時間で「できる→わかる→応用」の流れを作ってくれる
ただ「知識を詰め込む」のではなく、実際に問題を解いて「できる」→解説を見て「わかる」→応用問題に挑戦して「活かす」という流れが、すららでは自然に組み込まれています。
この学習ステップがとても効率的で、短時間でもしっかりと理解と定着が得られる仕組みになっているんです。
特に、日々の学習時間が限られている家庭や、習い事などで忙しい子どもにはこの時短効果がかなりありがたいはず。
さらに、間違えた問題に関してはすぐにフィードバックが入り、同じミスを繰り返さない工夫が施されているので、自然と“できること”が積み重なっていくのを感じられるはずです。
勉強って「伸びてる実感」があると、どんどん楽しくなってくるものなんですよね。
勉強効果3・中学生は主要3教科で内申点が決まるから「点数を上げたい」「定期テストで成果を出したい」という目的に直結する
中学生にとって内申点は、高校受験にも直結するとても重要な要素ですよね。
特に主要3教科(国語・数学・英語)は、成績の比重も高く、苦手なままにしておくと大きなリスクになります。
すららの3教科コースは、こうした中学生の“得点力”を高めることにフォーカスしているので、「定期テストで点数を取りたい」「内申を上げたい」と考えている家庭にぴったりなんです。
また、すららは教科書準拠ではないからこそ、どの単元からでも自由に戻って復習できるのが大きな強み。
苦手なところは徹底的に対策できるし、得意なところはどんどん進めることができます。
点数が上がると、子ども自身のモチベーションもぐんと上がって、ますます勉強が楽しくなりますよ。
すらら4教科コース(国・数・英語・理科または社会)の勉強効果について紹介します
すららでは、3教科(国語・数学・英語)に加えて、理科または社会を加えた4教科コースも選ぶことができます。
この4教科対応のカリキュラムは、単に科目を増やすというだけでなく、それぞれの特性に合った学習方法をしっかり取り入れているのが特徴です。
たとえば、理科や社会のように暗記要素が多い教科では、「繰り返し学ぶ」「視覚で理解する」などの工夫が詰まっており、無理なく知識が定着するようになっています。
また、要点を絞った解説で効率的に学べるので、限られた時間の中でもしっかりと成果が出やすいんです。
学校の授業についていけなかった子でも、基礎から着実に復習できるため、「わからない」が減って自信にもつながります。
ここからは、それぞれの勉強効果について詳しくお話していきますね。
勉強効果1・理科・社会は、「繰り返し学習」と「確認テスト」で記憶の定着率が高まる
理科や社会は、一度学んだだけではなかなか記憶に残りにくい教科ですよね。
年号や用語、科学的な用語や法則など、覚えるべき内容が多くて「苦手意識」を持ちやすい子も多いです。
でも、すららのカリキュラムでは、それらを自然と定着させるための「繰り返し学習」や「確認テスト」がとても効果的に組み込まれています。
授業を視聴したあと、すぐにミニテスト形式で理解度をチェックできるので、その場で覚えた知識をしっかり整理できるんです。
また、つまずいたポイントは自動的にピックアップされて再出題されるので、「わかるまでやる」スタイルが自然に身につきます。
こうした復習サイクルを何度も回すことで、知識が定着しやすくなり、「覚えたつもり」が確かな理解に変わっていきますよ。
勉強効果2・ポイントを押さえた要点学習で、時間対効果がとてもいい
忙しい毎日の中で、子どもに「たっぷり勉強の時間を確保する」のって意外と難しいですよね。
でも、すららでは限られた時間でもしっかり成果を出せるように、「ポイントを押さえた要点学習」が徹底されています。
理科や社会では、よく出る重要語句や必須知識にしっかり焦点を当てて解説してくれるので、無駄な時間をかけずに大切な部分だけを効率よく学ぶことができるんです。
特に、記憶すべき情報が多いこれらの科目では、「全部やろう」とすると逆に中途半端になってしまうこともあります。
でも、すららなら“ここを覚えれば大丈夫”という目印がわかりやすく示されているから、子どもも安心して取り組めます。
短時間でも「わかる」を実感できるから、学習のモチベーションもぐんと上がりますよ。
勉強効果3・通常の塾や学校より、短時間で理解→テスト対策ができるところが強み
すららの強みのひとつは、なんといっても「効率的な学習」で結果につながるという点です。
たとえば、学校や塾では同じ単元にたっぷり時間をかけることが多く、テンポがゆっくりすぎて退屈になってしまう子もいるかもしれません。
でもすららでは、要点だけをピンポイントで教えてくれるから、短時間で全体像をつかむことができるんです。
さらに、インプット直後に確認問題を解く流れになっているので、理解した内容をすぐにアウトプットできるのも大きな特徴です。
こうした流れが自然とテスト対策になっているから、「塾に行かなくても点が取れるようになった」と実感する家庭も多いんですよ。
時間がない日でも無理なく取り組めるのに、テスト前にはしっかり実力がついている…そんな理想的な学びがここにはあります。
すらら5教科コース(国・数・英語・理科・社会)の勉強効果について紹介します
すららの5教科コースは、単に科目数が多いというだけではなく、「学習の幅」と「効果の深さ」の両方をバランスよく取り入れている点が大きな特長です。
多くの教材では主要3教科のみの対応が一般的ですが、すららでは理科・社会まで含めてAIが分析しながら効率的に学習できる仕組みになっているので、子どもが自分のペースでバランスよく取り組めます。
また、学校の成績や通知表の向上はもちろん、高校受験を視野に入れた対策にも強く、模試や実力テストでの成果が見えやすいという声も多いんです。
5教科をまんべんなくカバーしつつ、無理のないペースで進められるので、「塾はハードルが高い」と感じていた家庭にとっても、とても取り入れやすい教材だと思います。
勉強効果1・全教科を満遍なくカバーし、内申点・通知表UPに直結/ 特に中学生の内申点は「5教科バランス型」が必須
中学生にとって「通知表の点数=内申点」は、高校受験を左右する重要な要素ですよね。
特に公立高校を目指す場合は、学力テストの点数だけでなく、5教科すべての内申点が重視されます。
ところが多くの通信教材やタブレット教材では、国語・数学・英語の3教科に絞られていることが多く、理科・社会は手薄になりがち。
でも、すららの5教科コースなら、すべての教科にしっかり取り組むことができるので、通知表のバランスアップにもつながりやすいんです。
AIが進捗や理解度を見ながら弱点を補強してくれるので、ただ勉強量を増やすのではなく、必要な箇所をしっかり押さえて効率よく学べるのも大きなポイントです。
結果として内申点アップを狙いやすくなりますよ。
勉強効果2・高校受験にも直結する実力アップ/模試や過去問対策にも応用できる
高校受験に向けた学力アップには、単なる教科書の理解だけでなく、「実戦力」が必要になってきますよね。
すららでは、ただ単元ごとの学習を進めるだけでなく、模試や過去問対策に応用できるような“応用力”もしっかり養えるように設計されています。
たとえば、問題を解くスピードや正確さ、苦手分野へのフォーカスなど、AIが分析した上で個別の課題を提示してくれるんです。
また、複数の教科にまたがるような設問にも対応できるよう、総合的な学力の底上げが目指せます。
「今どこが弱いか」「どこを伸ばせば点数につながるか」がわかるので、受験勉強に向けて無駄のない学習ができるのは本当にありがたいですね。
勉強効果3・ 5教科すべてAIが自動で弱点を分析し、学習計画を立ててくれるから効率的
学習効率を高めるうえで最も大切なのが「自分の弱点を正しく把握すること」なんですが、これって実はとっても難しいんですよね。
すららはその点、AIが子どもの解答傾向や理解度をリアルタイムで分析し、「どこが苦手なのか」「どこから復習すればいいのか」を自動で提示してくれます。
しかも、それをもとに学習計画まで自動作成されるので、親が毎回指示を出さなくても、子どもが自立して進められる仕組みなんです。
5教科すべてにこの機能が適用されているので、苦手を放置することなく、得意を伸ばしながら全体の底上げを目指せます。
限られた時間の中で最大限の成果を出すには、こうした“効率重視”のシステムは本当に頼もしい存在です。
勉強効果4・他の教材や塾より、時間あたりの学習効果は高いと感じる人が多い
塾に通っても「ただ時間だけが過ぎてしまう」「集団授業では質問しづらい」という悩みを抱えている子は少なくありません。
すららでは、AIによる個別最適化された学習プランに沿って進めることができるため、1回の学習で得られる“成果”が大きいという声がとても多いです。
1日30分の学習でも、その子に合わせて重要なポイントだけをギュッと凝縮してくれるので、無駄が少なく集中しやすいのが特徴です。
さらに、キャラクターによる対話型授業や視覚的な説明のおかげで、内容の理解度も高まりやすくなっています。
時間あたりの効果が実感できるというのは、子ども自身のやる気にもつながりますし、何より親としても安心して任せられますよね。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは発達障害や不登校でも安心・安全に使える理由
「すららはうざい」なんて声を見かけることがありますが、実際のところ、発達障害や不登校の子どもたちにとっては“かなり優しい教材”なんです。
というのも、すららは一般的な「画一的な学習教材」とはまったく違って、それぞれの子の特性や状況に合わせて、学習方法やサポート体制を柔軟に変えられるように設計されているからです。
学校に通えない日が続いても、焦らず自宅で自分のペースで進められる。
人との関わりが苦手でも、アニメキャラクターが優しく声をかけてくれる。
こうした「学びへの安心感」が、何よりも子どもたちにとって大切なんです。
今回は、すららがどうして“安心して使える教材”なのか、その理由を具体的にご紹介していきますね。
安全な理由1・「本人のペースで学習できる」からプレッシャーがない
すららの魅力のひとつは、「周りと比べなくていい」こと。
学校では、学年やクラスでの進度に合わせて授業が進むため、どうしても「わからないまま進んでしまう」ことや「もう知ってるのに待たされる」といったストレスが生まれがち。
でも、すららならその心配は一切ありません。
自分の理解度に合わせて、苦手なところは何度でも戻って学べるし、得意な分野はどんどん進めることができます。
これは特に、発達障害を持つお子さんにとって大きなメリット。
自分のペースを尊重してくれる環境は、安心感にもつながります。
つまずきをAIが検知して、自動で補強してくれる機能もあるので、「置いてけぼりにならない」仕組みが整っているんですよ。
学校の授業の「遅れ」や「先取り」を気にせず、マイペースに学べるから、ストレスが少ない
学校では、「みんなと同じスピード」で学ぶことが前提になっていますが、実際には子ども一人ひとり、理解のペースも得意・不得意もまったく違いますよね。
でもすららなら、そういった“ズレ”を感じる必要がありません。
今の自分のレベルに合わせて進められるので、「遅れている」「ついていけない」といった不安がなく、学習のストレスが驚くほど軽減されるんです。
逆に「この単元はもう知っている」といった内容なら、スキップして先に進むこともできるので、時間を無駄にすることなく、自分にとってちょうどいい学びを続けられます。
子どもが「学ぶことって楽しいかも」と思えるようになるきっかけが、ここに詰まっているんですよ。
ADHDタイプの子は「集中できる時に一気に」、ASDタイプの子は「毎日決まったペースで」、それぞれに合った使い方ができる
発達障害にもいろいろなタイプがありますが、すららはその多様性をしっかりと理解した設計になっているのがすごいところです。
たとえば、ADHD傾向のある子は「集中力に波がある」ので、集中できるタイミングに一気に学習を進められる柔軟さがとても助かります。
一方、ASD傾向のある子は「日々のルーティン」を重視することが多いため、毎日決まった時間に同じ流れで学習ができることが安心につながります。
どちらのタイプに対しても無理なく対応できる自由度があるのが、すららの魅力。
親が「この子にはどう使わせたらいいんだろう」と迷わずに済むよう、すららコーチも一緒になってサポートしてくれるので、家族にとってもとても頼もしい存在です。
安全な理由2・「対面の緊張や不安がゼロ」だから取り組みやすい
人と直接関わるのが苦手だったり、過去に学校での人間関係にストレスを感じた経験がある子どもにとって、「誰とも会話せずに学べる環境」は非常に大きな安心材料です。
すららでは、アニメーションのキャラクターがやさしく授業を進めてくれます。
質問されても責められることはないし、間違えても怒られることはありません。
自分のペースで、緊張せずに学べる空間がそこにはあります。
これは、対人コミュニケーションに不安を感じやすいASD傾向の子や、不登校で人との接触がトラウマになっている子にとって、本当にありがたい特徴です。
教室のようなプレッシャーがなくても、しっかりと学びは成立する。
そんな優しさに満ちた設計になっているんです。
アニメーションのキャラが優しく教えてくれて、正解でも不正解でも感情的な反応をされることはない
先生に怒られた経験がある、クラスで発言して笑われた、そんな小さなトラウマが勉強への苦手意識につながってしまうことって意外と多いんですよね。
でもすららなら、その心配は一切ありません。
登場するアニメキャラクターは、常に穏やかでやさしく、正解しても間違っても、子どもを否定するような態度を一切とりません。
むしろ「ここはこうだったね、もう一度やってみよう!」と励ましてくれるので、子ども自身が「やってみよう」と前向きな気持ちを持ちやすくなるんです。
勉強を“怖いもの”ではなく、“対話しながら進めていくもの”として体験できることで、自然と学びへの自信が育まれていくのがすららの良さなんです。
人とのコミュニケーションに不安がないから安心して学ぶことができる
発達障害のある子や、不登校の子の中には、「誰かと話すこと」そのものに大きなストレスを感じるケースもありますよね。
でも、学びの場でそういった不安が常につきまとうと、なかなか集中して取り組むことができません。
その点、すららは“人とのやりとりが不要”な設計になっているため、自分だけの空間で安心して学べます。
しかも、ただ静かに動画を見るだけでなく、キャラクターとの対話形式になっているから、退屈せずに続けやすいんです。
コミュニケーションが苦手な子にとって、「誰にも気を遣わずに、自分だけで学べる」という環境は、本当にありがたいもの。
学習=不安というイメージを払拭してくれる、そんな設計になっているのがすららなんです。
安全な理由3・発達障害に対応した「ユニバーサルデザイン」設計
すららは、ただのデジタル教材ではなく、すべての子どもが学びやすいように設計された“ユニバーサルデザイン”が大きな魅力です。
特に、発達障害のある子どもたちにとって、通常の教科書や一方向型の映像授業では理解が難しかったり、つまずきやすかったりする場面が多々あります。
ですが、すららは「視覚で理解する」「音声で聞く」など複数の感覚を使って学ぶ構成になっているため、情報が頭に入りやすいんです。
さらに、操作性もシンプルで直感的に使えるよう工夫されており、読字障害や言語理解に時間がかかるお子さんでも安心して学習に取り組めるんですよ。
「どんな子でも学びを止めない」そんな設計思想が、すららにはしっかりと込められています。
すららは「誰でも理解しやすく、つまずきにくい」ように作られている
一般的な教材では、「難しい言葉」や「抽象的な表現」が多くて、子どもたちが混乱してしまうことも少なくありません。
でも、すららは違います。
すららの教材は、どんな学力の子どもでも理解しやすいように、言葉選びや表現方法まで丁寧に設計されているんです。
図やアニメーションでの解説が豊富なので、視覚的な理解が得意な子にもピッタリですし、対話形式で進んでいくことで、つまずく前に「なぜわからなかったのか」が自分で気づけるようになっているのが特長です。
一つのミスで置いていかれない、そんな安心感のある教材だからこそ、長く続けられるんですよ。
読字障害(ディスレクシア)、言語理解に時間がかかるASDの子にも分かりやすい
すららは、読字障害(ディスレクシア)や自閉スペクトラム症(ASD)の子どもたちにも配慮された教材です。
文字を読むことに困難を感じる子には、音声での解説やイラストの補助がとても有効ですし、言語理解に時間がかかる子には、繰り返しの説明や図解によって「じっくりと考える時間」が与えられます。
学校の授業ではスピードが早すぎてついていけなかった子でも、すららなら自分のペースでゆっくりと理解を深められます。
「みんなと同じようにできない」ではなく、「自分に合った方法でできる」ことが、子どもの安心とやる気につながっていくのです。
「視覚優位」「聴覚優位」どちらのタイプの子にもマッチしやすいのが特長
学習スタイルには個人差があります。
中には「目で見て理解する方が得意」という視覚優位の子もいれば、「耳から聞くとスッと入る」という聴覚優位の子もいます。
すららの魅力は、そんな異なるタイプの子どもたちの特性を想定した設計にあります。
アニメーションや図解による視覚的な説明と、ナレーションによる音声ガイドが同時に進行するため、どちらのタイプにも無理なくマッチするんです。
また、見た目やテンポも工夫されていて、集中が途切れにくいように構成されています。
自分に合った方法で学べるって、実はとても大事なこと。
すららなら「学びにくさ」を感じさせずに、自然と知識が身につく環境が整っているんですよ。
「音声速度」を調整できる機能もあるから、「ゆっくり聞きたい」「早く進めたい」など、子どもの特性に合わせられる
すららには、音声のスピードを調整できる機能が搭載されています。
これは実は、発達特性を持つ子どもにとってものすごくありがたい機能なんです。
たとえば、処理速度がゆっくりな子どもにとっては、通常の話し方でも内容が流れてしまうことが多いんですよね。
そんなとき「音声をゆっくり再生」できる機能があると、聞き取りやすくなるだけでなく、焦る気持ちも減って学習に集中できるようになります。
逆に、テンポよく進めたい子どもにはスピードアップも可能です。
このように、一人ひとりの理解のスピードや集中力に合わせて調整できるから、ストレスなく、無理のない学習が実現できるのです。
学びのストレスを減らしてあげられるって、親としても安心ですよね。
安全な理由4・間違えても怒られない・恥をかかない設計
すららが多くの子どもたちに受け入れられている理由のひとつが、「間違えることが怖くない」という安心設計です。
学校のように周りの目を気にすることもなく、塾のように厳しい指導でプレッシャーを感じることもありません。
すららでは、間違えたとしても頭ごなしに否定されたり、叱られたりすることはなく、「なぜそうなるのか」「どこで間違えたのか」を一緒に振り返るような流れになっているんです。
これによって、子ども自身が「次はこうしてみよう」と前向きに捉えられるようになります。
間違えることで学ぶのが当たり前、という空気感があるからこそ、子どもが自信を失わず、ポジティブに学習を続けられるようになるんですよ。
「否定」ではなく「納得」させてくれるから、自己肯定感が下がりにくい
すららの授業は、ただ正解か不正解かを示すだけではありません。
間違えたときに「違うよ」ではなく、「ここがポイントだったね」「一緒に確認してみよう」というような、前向きなフィードバックをくれるんです。
このスタンスが、子どもの心にとても優しく響きます。
自己肯定感が育まれる環境では、失敗を恐れずにチャレンジできるようになり、その結果、理解も定着もしやすくなっていきます。
「できなかった自分」よりも「次はできる自分」を育ててくれるのが、すららの大きな魅力なんです。
親としても「またやる気をなくしてしまったらどうしよう」という不安が減り、安心して任せられる環境ですよ。
学校や塾では感じがちな「恥ずかしい」「できない」といったネガティブ感情を抱きにくい
学校や塾では、周りの目が気になって「間違えるのが恥ずかしい」と感じてしまう子どもも多いですよね。
でも、すららなら自宅で一人で取り組める環境だから、そうしたプレッシャーから解放されます。
特に、間違えたときに先生やクラスメイトの反応を気にして言い出せなかったり、自信を失ってしまうタイプの子どもにとっては、すららの学習環境はまさに理想的です。
人目を気にせず、思いきり自分のペースで挑戦できるから、失敗を恐れずにどんどん取り組めるようになるんです。
これは、勉強に対して「前向きな気持ち」が育つ大きなきっかけになりますよ。
誰にも気を使わず、自分だけの空間で安心して学べるって、本当に貴重なことです。
安全な理由5・「ゲーム感覚」の楽しい仕組みで続けやすい
すららの大きな魅力のひとつが、ゲーム感覚で学べる楽しさです。
特に集中力が持続しづらい子どもや、勉強に対して苦手意識を持っている子には、「楽しさ」ってものすごく大事なんですよね。
すららでは、学習内容が単調にならないように、アニメキャラクターとの対話形式やクイズ形式の演出がたっぷり取り入れられています。
まるでゲームをプレイしているかのような感覚で学べるので、子どもたちも「もう1問だけやってみよう」と、自発的に取り組んでくれるんです。
勉強に対して「やらされ感」があるとどうしても続かないけれど、自分から進んで取り組めるようになれば、それはもう習慣になりますよね。
楽しく学べる仕組みがあるからこそ、無理なく続けられるのがすららの強みです。
アニメキャラクターがナビゲートし、クイズ形式やゲーム感覚の要素があるから「もうちょっと続けたい」と思わせる工夫がされてる
すららでは、ただ問題を解くだけではなく、学習全体をエンタメのように楽しめる仕組みが整っています。
アニメキャラクターたちが子どもに話しかけながら授業を進めてくれるから、まるで“先生とおしゃべり”しているような感覚で勉強できるんです。
さらに、問題もクイズ形式で出題されたり、テンポよく進む設計になっているので、子どもが途中で飽きてしまうことがありません。
「あと少しだけやってみよう」という気持ちを引き出す工夫が随所に盛り込まれていて、気づけば1時間経っていた…なんて声もよく聞きますよ。
こうした楽しい体験が「勉強=つらいもの」というイメージを変えてくれるので、自然と続けやすくなります。
ADHDの子は「すぐに褒められる」「すぐに結果が出る」とやる気が続きやすい傾向がある
ADHDの特性を持つお子さんにとっては、「今やったことがすぐに評価される」「頑張った結果がすぐにわかる」という体験がとても大事です。
すららでは、問題を解いた瞬間にフィードバックがもらえるようになっていて、正解すればキャラクターが褒めてくれたり、ポイントが加算されたりと、すぐに“達成感”を味わえるよう工夫されています。
この即時性があるからこそ、「やった!」という成功体験が積み重なり、モチベーションが持続しやすいんです。
また、ミスをしても優しくフォローしてくれるので、「怒られたくないからやらない」という気持ちにはならず、安心して学習に取り組めます。
こういった細やかな配慮が、続ける力を育ててくれるんですよ。
安全な理由6・「すららコーチ」がいるから親子で抱え込まなくていい
家庭学習の最大のハードルは、やはり「親の負担」だと思います。
特に発達障害のあるお子さんの場合、どんなふうに教えたらよいのか、どこでつまずいているのかが見えづらく、親も悩みを抱えがちです。
すららでは、こうした問題を「すららコーチ」がしっかりサポートしてくれるから、親が一人で抱え込まなくても大丈夫なんです。
コーチは、子どもの特性に応じて学習内容や進め方を調整してくれるので、本人も無理なく学習を続けられますし、親も見守るだけでOK。
しかも、日々の学習状況や進度もレポートで共有されるので、「本当にやってるのかな?」と不安になることもありません。
信頼できるプロに任せることで、親子ともに気持ちが軽くなる、そんな安心感がここにはあります。
ADHDやASD、学習障害の特性を理解した対応をしてくれるコーチが多い
すららのコーチは、ただの「進捗管理者」ではなく、教育現場で発達特性のある子どもたちを支援してきた経験を持つプロフェッショナルが多く在籍しています。
ADHDやASD、LDなど、それぞれの子どもが持つ特性に寄り添いながら、どうすれば学びがスムーズに進むかを一緒に考えてくれる存在です。
「こういう声かけが合っていた」「こういうタイミングでつまずきやすい」といったノウハウが豊富なので、親では気づけなかった視点からもサポートがもらえるんですよ。
自宅での学びに不安がある方でも、こうした専門的な対応を受けられることで、より安心して継続できます。
「プロが一緒に見てくれている」この事実が、親子にとって何より心強いんです。
コーチが学習計画を立てたり、つまずきポイントを教えてくれる
すららでは、子どもの性格や学習状況を踏まえて、コーチが一人ひとりに合わせた学習計画を立ててくれます。
これがあることで、「今日は何をすればいいの?」「このペースで合ってるのかな?」といった不安がなくなり、子ども自身も迷わずに取り組めるようになるんです。
また、つまずきポイントを見つけて「ここをもう一度復習してみよう」と的確にアドバイスしてくれるので、無駄な時間をかけずに学びを深めることができます。
保護者の目が届きにくい部分もしっかりカバーしてくれるから、家庭学習がスムーズに回りやすくなるんですよ。
学びにおいて「次に何をすべきか」が明確になることで、子どもも安心して前に進めるようになります。
安全な理由7・「完全オンライン」だから家で完結できる
「すらら」は、完全オンラインで学習が完結できるというのも、大きな安心ポイントです。
わざわざ塾へ通わせる必要がないので、送迎の手間や時間も不要ですし、交通費もかかりません。
特に、不登校や外出に不安を感じているお子さんにとっては、安心できる自宅という環境で学べることが、学習への大きな一歩になりますよね。
また、タブレットさえあればすぐに学習が始められるので、特別な準備も不要です。
どこにいても同じクオリティの学びが提供されるのは、家庭にとっても子どもにとっても、非常にありがたいことだと思います。
いつでも・どこでも・自分のペースで進められるからこそ、学習が生活に無理なくフィットし、長く続けやすくなるんです。
タブレット1台あればできるから、環境づくりもシンプルだし、親の負担も減る
勉強を始めるために、あれこれと環境を整えるのって意外と手間がかかりますよね。
でも、すららならタブレット1台あれば、すぐに学習がスタートできるんです。
複雑な教材の準備やプリントの整理、学習スペースの確保といった手間がないから、親の負担もグッと減ります。
しかも、タブレットは持ち運びも簡単なので、リビングでも寝室でも、好きな場所で気軽に学べるのも魅力のひとつです。
「今日はここでやってみよう」と子ども自身が場所を選べることで、より自由度の高い学びが可能になります。
こうした柔軟さがあるからこそ、無理なく毎日の生活に学習を組み込むことができるんですね。
通学できない間も学習の「穴」を作らず、自信を持たせてあげられる
学校に通えない期間が続くと、「うちの子だけ取り残されているのでは?」と不安になる保護者の方も多いはず。
でも、すららなら家にいながらでも学びの流れを止めずに続けられるので、学習の“穴”を作る心配がありません。
しかも、本人のペースに合わせて無理なく取り組めるように設計されているので、「わからないまま進む」といったことも少なく、自信を持って次のステップに進むことができます。
これって、すごく大事なことなんですよね。
「通えなくても自分は学べている」と感じられることで、子ども自身が自信を取り戻し、前向きに変化していくんです。
学校に戻る準備期間としても、すららはとても心強い学びのパートナーになりますよ。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの解約・退会方法について紹介します
「すららを使ってみたいけど、もし合わなかったら解約はどうすればいいの?」そんな不安を抱えている方も少なくないと思います。
特にタブレット教材って、一度申し込むと手続きがややこしかったり、やめるタイミングが難しかったりしますよね。
すららはその点、ちゃんと明確に「解約」と「退会」の違いがあり、ルールに従えばスムーズに手続きができます。
とはいえ、ややこしく感じる部分もあるかもしれませんので、ここではその違いと具体的な手順を丁寧にご紹介していきますね。
「いつでも辞められる」とわかっているだけでも、気持ちがだいぶラクになりますよ。
無理なく、納得して利用できるよう、正しい情報を押さえておきましょう。
すららの【退会】と【解約】は意味が異なる!それぞれの違いについて解説します
「すららをやめたい」と思った時、注意しなければならないのが【解約】と【退会】は別物だということです。
一般的な感覚だと、どちらも「やめる」ことには違いありませんが、すららではこの2つに明確な違いがあります。
まず解約とは、「月額料金の支払いを止めること」、つまり教材の利用を一旦ストップする手続きです。
一方で退会は、「会員情報そのものを削除し、学習履歴などのデータもすべて消える」ことを意味します。
将来的にまた再開したいと考えている場合は、退会ではなく“解約”の方を選ぶべきですね。
この違いを知らずに退会してしまうと、せっかくの学習記録が全部消えてしまうので、注意が必要です。
すららの解約は「利用を停止すること」。毎月の支払い(利用料)を止める手続き。
解約とは、すららの月額料金の支払いを止める=利用を一時中断するという意味になります。
つまり、アカウントや学習データはそのまま残しつつ、教材の利用を一時お休みするようなイメージです。
解約後は月額料金が発生しなくなるため、家計の負担も軽減されますし、「一時的に使えなくなるだけ」という柔軟な対応が可能です。
特に、夏休みや冬休みなど一時的に学習をストップしたいときには、この“解約”が便利です。
再開したいときには再契約すればOKなので、データが引き継がれるのも嬉しいポイントですね。
完全に辞めるか迷っている方にとっては、まずこの「解約」を選ぶのがおすすめです。
すららの退会は 「すららの会員そのものをやめること」。データも消える。
退会は、「すららというサービス自体から脱退すること」を意味します。
この手続きをすると、これまでの学習記録や個人情報、すららコーチとのやり取りの履歴などもすべて削除され、再度利用したいと思った時には、ゼロからのスタートになります。
「もう二度と使う予定はない」「完全に終了したい」という意思がある場合には退会でも問題ありませんが、少しでも「また使うかも」と思っている場合は、安易に退会を選ばない方が良いです。
退会後に「やっぱりまた始めたい」と思っても、過去のデータは戻らないため、最初からすべて設定し直しになってしまいます。
迷っている場合は、解約で様子を見る方が安心ですね。
すららの解約方法1・すららコール(サポートセンター)に電話
すららを解約したいときの手続き方法として、唯一の公式手段は「すららコール」に電話をかけることです。
近年ではメールやWEBフォームで完結するサービスも増えていますが、すららは電話での本人確認と意思確認を大切にしているため、解約は電話のみの対応となっています。
ちょっと面倒に感じるかもしれませんが、その分しっかりと対応してもらえるので安心感がありますよ。
オペレーターの方が丁寧に案内してくれるので、初めての方でも心配いりません。
あらかじめ会員情報を手元に用意しておくと、スムーズに進められますし、混み合う時間帯を避ければ、数分で手続きは完了しますよ。
| 【すららコール】
0120-954-510(平日10時~20時 土日祝休み) |
すららの解約はメールやWEBからは受け付けていない
すららの解約は、電話でのみ受け付けています。
メールや公式サイトの問い合わせフォームからでは手続きができないため、そこは注意が必要です。
最近はネット完結型のサービスが多いので、つい「WEBで解約できるはず」と思い込んでしまう方もいますが、すららの場合は本人確認やヒアリングの重要性を重視しているため、電話での直接対応がルールになっています。
どうしても日中に電話する時間がとれないという方には不便に感じるかもしれませんが、その分、サポートの質は高く、親切丁寧な対応をしてくれるという評判も多いです。
土日祝はお休みなので、解約を考えている場合は平日の早めの時間に連絡するのがおすすめです。
すららの解約方法2・電話で本人確認/登録者氏名・ID・電話番号など
すららを解約する際には、公式サイトにある解約専用の電話番号に連絡する必要があります。
その際に大切なのが「本人確認」。
これは、不正な解約や情報の誤操作を防ぐために行われる大切なステップです。
電話では、登録時に使用した名前や、ユーザーID、そして登録している電話番号などの情報を確認されます。
こうした情報がすぐにわかるように、事前に手元に用意しておくとスムーズに対応できますよ。
特に、ユーザーIDはログイン画面やメールなどに記載されていることが多いので、事前に確認しておくことをおすすめします。
電話口で焦らないためにも、メモなどに整理しておくと安心です。
すらら側もとても丁寧に対応してくれるので、落ち着いて手続きを進めてくださいね。
すららの解約方法3・解約希望日を伝える/日割り計算はされません
解約手続きの電話では、本人確認のあとに「いつで解約するか」を伝える必要があります。
たとえば「今月末で解約したい」「今日付で解約したい」など、希望のタイミングを明確に伝えることがポイントです。
注意しておきたいのは、すららでは月額料金の**日割り計算がされない**という点です。
つまり、月の途中で解約しても、その月の料金はまるごと1ヵ月分発生することになります。
これは少しもったいないと感じる方もいるかもしれませんが、あらかじめルールとして明確にされているので、後で混乱しないように事前に把握しておきましょう。
「あと数日使ってから解約した方がいいかも」と思ったら、希望日をうまく調整するのもひとつの方法です。
親身に対応してくれるスタッフさんに、遠慮なく希望を伝えてくださいね。
すららの退会方法について/解約手続き完了後に退会依頼をする
すららには「解約」と「退会」の2つの手続きがありますが、これはちょっとややこしいので違いをしっかり知っておくと安心です。
「解約」は毎月の支払いを止めること、「退会」はすららの会員情報自体を削除してもらう手続きになります。
つまり、解約だけではアカウントが残っている状態です。
退会を希望する場合は、解約手続きが完了した後に「退会も希望します」と電話で伝えることで、正式にデータ削除が行われます。
ただし、退会しなくても料金が発生することはありませんので、特別な理由がなければ解約だけでも問題ありません。
再開を検討している方や、データを残しておきたい場合は、そのままにしておいても大丈夫ですよ。
すらら解約の電話時に退会希望の旨を伝える
すららの解約手続きを電話で進める際、「退会も希望しています」とその場で伝えれば、解約とあわせて退会手続きまで一括で進めてもらうことができます。
もちろん、後日あらためて退会依頼をすることも可能ですが、手間を減らしたい方は、最初の電話の時点でまとめて伝えておくのがスムーズです。
退会手続きを行うと、すららに登録されている個人情報や学習履歴なども削除されます。
今後すららを再開する可能性がない方や、情報を残しておきたくない方には安心の対応です。
対応スタッフさんもとても丁寧なので、どんな小さな疑問や不安もその場で質問してしまいましょう。
解約だけでなく、退会もきちんと手続きしておけば、気持ちよくすららを卒業できますよ。
すらら解約後に退会をしなくても全く問題はありません(料金の支払いは停止します)
「解約はしたけど、退会まではしていない…」という場合でも、心配はいりません。
すららでは、解約の手続きさえ完了していれば、月額料金の引き落としはきちんと止まります。
退会はあくまで「登録情報や学習履歴を削除したい」という方のためのオプション的な手続きです。
そのため、「また使うかもしれない」「データは残しておきたい」という方は、退会しないままでも全く問題ありません。
もちろん、将来的に再開する際には、残っている情報を活かしてスムーズに学習を再スタートすることも可能です。
退会を迷っているなら、まずは解約だけ済ませて、落ち着いてから決めても良いですね。
安心して自分に合った選択ができる仕組みになっています。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの効果的な使い方について紹介します
「せっかく教材を用意したのに、うまく活用できなかった…」そんな声、実はとても多いんです。
でも大丈夫。
すららはただ“用意して終わり”の教材ではなく、しっかり活用すれば、毎日の学習リズムを整える“強い味方”になります。
とくに家庭学習は習慣化がカギ。
少しずつコツを掴んでいくことで、すららの本当の効果が発揮されるようになるんですよ。
今回は、実際に多くの家庭で「続けられている」「効果を感じている」使い方をご紹介します。
これを参考にすれば、無理なく楽しみながら勉強できるようになるはずです。
特に小学生のお子さんがいるご家庭では、親御さんのちょっとした工夫が、学習継続の決め手になりますので、ぜひ一緒にチェックしてみてくださいね。
【小学生】すららの効果的な使い方について紹介します
小学生はまだ勉強習慣が定着していないケースが多いので、「どうやって取り組ませるか?」がとても重要になります。
でも、すららは小学生にも取り組みやすい構成になっていて、ちょっとした工夫を加えるだけで驚くほど続きやすくなるんです。
大切なのは“楽しみながら勉強する”というスタンスをつくってあげること。
たとえば「短時間でOK」とすることで心理的ハードルを下げたり、ごほうびや親の声かけで気持ちを盛り上げたりすることで、子どもが自然と学習に向かうようになります。
学力を伸ばすために必要なのは「量」よりも「継続」なんですよ。
ここでは、小学生がすららを最大限に活かすための具体的な使い方を紹介します。
使い方1・「短時間×頻度」でリズムを作る/1回20〜30分を目安に、毎日少しずつ続ける
小学生にとって「長時間の勉強」は集中力を保つのが難しく、かえってストレスになりがちです。
だからこそ、すららを使うときには“短時間×高頻度”を意識して取り組むのがおすすめです。
1回20分〜30分を目安に、毎日決まった時間に少しずつ学ぶだけでも、十分に効果があります。
とくにすららは、短時間でも「理解→確認→応用」という流れがしっかり組まれているので、内容の濃さは折り紙つきです。
毎日コツコツ続けることで、少しずつ「やるのが当たり前」になり、習慣として根付いていきます。
最初は短くてもOKなので、まずは続けることにフォーカスしてみてくださいね。
使い方2・「ごほうび制度」を活用する/1ユニット終わったらシールを貼るとか、小さな達成感を演出すると、やる気が続く
子どもにとって勉強は“義務”になってしまうと、なかなか続けにくいもの。
でも「やったらうれしい」「終わったら楽しいことが待ってる」と思えるだけで、取り組む姿勢がガラッと変わるんです。
そこでおすすめなのが「ごほうび制度」の導入です。
たとえば、1ユニット終わったらシールを貼る、好きなおやつを食べられる、好きな番組を見ていい…など、小さな達成感を演出するだけでもモチベーションが続きます。
ごほうびは“盛大すぎない”ことがコツで、あくまで「自分でがんばったことを認める」という視点を大切にしましょう。
学習=楽しい体験、とインプットされることで、自ら進んで取り組むようになりますよ。
使い方3・親も一緒に楽しむ姿勢を/とくに低学年は、親が「一緒にやろう!」と言うと素直に取り組むことが多い
特に低学年のうちは、子どもだけで学習を続けるのはなかなか難しいものです。
でも、親が少しでも一緒に関わることで、子どものやる気や集中力はぐんと高まります。
「今日の内容、ママも気になるな〜」とか、「一緒にチャレンジしよう!」という声かけがあるだけで、子どもは“楽しい時間”として受け取るようになります。
すららの対話形式の授業は、親子で一緒に楽しめる構成になっているので、ぜひこの時間を「学習タイム」というより「親子のコミュニケーションタイム」として使ってみてくださいね。
一緒に笑ったり、驚いたりしながら学ぶことで、子どもにとっても大切な思い出になるんです。
使い方4・苦手克服から入るのがおすすめ/好きな科目ばかりやると偏るから、すららのAI診断で弱点を把握して、そこから攻略する
好きな教科に偏ってしまうのは、よくあること。
でもそれだけだと、成績のバランスが悪くなってしまったり、苦手科目へのハードルがどんどん高くなってしまったりするんですよね。
だからこそ、すららのAI診断をうまく活用して、まずは「どこが苦手か」を把握することが大切です。
そして、その苦手な部分から少しずつ攻略していくことで、「やればできる」という成功体験が積み重なり、自信につながっていきます。
はじめは抵抗があるかもしれませんが、すららはつまずきを丁寧に分析し、必要な単元を無理なく提示してくれるので安心です。
苦手を克服することで全体の学力が底上げされる、それがすららの魅力のひとつなんですよ。
【中学生】すららの効果的な使い方について紹介します
中学生になると、部活や塾、課題などで毎日がとにかく忙しくなりますよね。
そんな中で「勉強時間をどうやって確保するか」は、保護者にとっても子どもにとっても大きな課題です。
すららは、そんな中学生のスケジュールに寄り添って、自分のペースで無理なく続けられる学習スタイルが魅力です。
特に定期テストや受験に向けて、どのようにすららを活用するかで、効果の出方が変わってきます。
今回ご紹介する使い方は、忙しい中学生でも効率よく力を伸ばせる実践的な方法ばかり。
ポイントは「目的を持って活用する」こと。
なんとなく毎日触るのではなく、「このために使う」と意識を持つだけで、すららの学習効果はぐんと高まるんです。
では、具体的な使い方を順番にご紹介していきますね。
使い方1・「定期テスト対策」に直結させる/単元ごとにまとめテストがあるから、テスト範囲を逆算して、今どこをやるべきか計画を立てる
中学生にとって定期テストは、内申点にも大きく関わる重要なイベントですよね。
すららはこの定期テスト対策にもばっちり対応してくれるんです。
各単元ごとに「まとめテスト」や「確認問題」が用意されていて、実際のテスト範囲に合わせてピンポイントで学習を進めることができます。
効果的な使い方としては、テスト日から逆算して「今どこをやるべきか」を計画すること。
すららの画面上でも学習の進捗が確認できるので、やるべき範囲を可視化できて、とてもわかりやすいんです。
これなら「まだ時間があるから」と先延ばしにすることなく、毎日少しずつ計画的に学習を進められますよ。
自主学習が苦手な子でも、目的が明確になると取り組み方が大きく変わってきます。
使い方2・部活後の「夜学習」を習慣に/寝る前の「タブレット学習ルーティン」を決めると、ペースが乱れない
部活が終わって帰ってきたらクタクタ…そんな中学生も多いですよね。
でも、少しだけ頑張って「夜に15〜30分だけすららに取り組む」と決めておくと、学習のペースが崩れにくくなります。
すららは短時間でも学べるように設計されているので、疲れていても「これだけやろう」と思える手軽さがあります。
おすすめは、寝る前の“タブレット学習ルーティン”をつくること。
ベッドに入る前の時間を少しだけ使うことで、無理なく習慣化できるんです。
画面の操作も簡単で、内容もアニメーションや会話形式で進むから、疲れていても取り組みやすいんですよね。
「今日もできた」という小さな達成感が積み重なっていくと、自然と自信にもつながっていきますよ。
使い方3・「すららコーチ」をフル活用/学習計画のアドバイスやつまずきのサポートをしてくれる
すららには、ただ教材があるだけではなく、「すららコーチ」という頼れる存在がいるのが大きな魅力です。
中学生になると学習内容も難しくなってくるので、自分ひとりで計画を立てたり、理解できていないところを見つけるのはなかなか大変です。
そんなときに、すららコーチのサポートがあるととても心強いんですよ。
学習スケジュールの作成はもちろん、どの単元に苦手があるか、どこを重点的にやるべきかなど、子ども一人ひとりに合わせたアドバイスをしてくれます。
特に思春期の子どもには、親から言われるよりも第三者のサポートの方が素直に受け入れやすいこともありますよね。
だからこそ、すららコーチの存在は、学習の継続にとっても大きな支えになるんです。
使い方4・「復習と予習」をバランスよく/英語や数学の文法・公式の理解は予習でやると授業が楽しくなる
中学生になると、授業スピードも早くなり、「理解できないまま進んでしまった…」ということが増えがちです。
そんなときにおすすめしたいのが、すららを使った「予習と復習のバランス学習」です。
特に英語の文法や数学の公式など、理解していないと授業がちんぷんかんぷんになる単元は、事前に予習しておくと授業がグッと楽になるんです。
そして授業後には、同じ範囲をすららでサッと復習することで、知識がしっかり定着しますよ。
すららは一方通行の学習ではなく、「わかっていないところを教えてくれる」仕組みがあるからこそ、予習でも復習でも使いやすいんです。
学校の勉強と連動して使えば、自然と成績アップにつながる力が身につきますよ。
【高校生】すららの効果的な使い方について紹介します
高校生になると勉強内容も一気に難しくなり、ただ教科書を読むだけでは理解が追いつかないことも増えてきますよね。
特に苦手教科やつまずきがある場合、「どう勉強すればいいのか分からない」と悩む子も多いものです。
そんなときにすららは、AIによる分析と個別最適化された学習プランで、勉強に対する不安を軽減してくれる強い味方になります。
高校生向けのすららは、基礎から応用まで幅広く対応していて、学校の授業に合わせて学ぶことも、自分のペースで進めることもできる柔軟なスタイルが特徴です。
部活やアルバイトで忙しい高校生活の中でも、効率よく「できる時間に、できるだけ」の学習が可能になるので、無理なく続けられる点も嬉しいですね。
使い方1・「苦手克服」×「得意分野の強化」を並行する/つまずいてるところは基礎から復習し、得意分野は応用問題に挑戦する
高校生になると、勉強の難易度がグッと上がり、「得意・不得意」がよりハッキリ分かれるようになります。
そんな中ですららを活用する最大のメリットは、苦手と得意を同時に伸ばせるという点です。
AIが苦手な分野を自動でピックアップし、復習や基礎学習を提案してくれるので、つまずきの放置がなくなります。
一方で、得意な分野についてはレベルの高い応用問題や発展問題にチャレンジできるよう設定されており、常に“今の自分にちょうどいい負荷”で学習が進められるのです。
これにより、全体の学力の底上げだけでなく、得意をさらに伸ばして入試対策にも直結する力がついていきます。
どちらか一方ではなく、両方にバランスよく取り組めるのがすららの大きな強みですね。
使い方2・学校の授業が合わない場合は、すららで自分に合うペースで進める
学校の授業はどうしても集団向けに進められるため、「速すぎる」「逆に遅すぎる」と感じることがありますよね。
そんな時、無理に授業についていこうとするより、自分の理解度に合わせて勉強できる“すらら”のような教材を取り入れる方が、ずっと効率的なんです。
すららなら、自分がわかるところから始められるので、授業でつまずいたところも置いていかれずに復習できますし、逆に「ここはもうわかってる」という単元はどんどん先へ進められます。
これによって、無駄な時間を減らしながら自分のペースで学べるから、ストレスも少なくなりますよ。
「授業についていけない自分が悪い」と思っていた子が、すららで勉強の楽しさを取り戻すこともあるくらいなんです。
使い方3・模試や共通テスト対策に連動/すららは基礎力の定着にはかなり強い
高校生にとって避けて通れないのが模試や共通テスト。
実力を試す場でもあり、志望校選びの判断材料にもなる重要な機会ですよね。
すららは、そういった試験に向けた基礎力をしっかりと固めるのにぴったりの教材なんです。
単元ごとの理解度をAIが自動的に分析し、定着度に応じて復習や演習を提案してくれるので、弱点を見逃さずに対策できます。
特に共通テストでは「基礎がいかに正確に身についているか」が問われるため、すららでの地道な積み上げが結果に直結しやすいです。
また、すららの問題はただ解くだけでなく、“なぜその答えになるのか”というプロセスを重視しているので、理解の深さも増していきます。
毎回の学習がテスト対策につながる感覚は、自信にもつながりますよ。
使い方4・学習時間を「見える化」する/学習時間や達成度がグラフで表示される
勉強って、やったつもりになってしまいがちですよね。
でも「自分がどれだけやったか」「どこまで進んでいるか」が目に見えると、やる気や達成感が全然違ってきます。
すららでは、学習時間や達成度が自動でグラフ化されて表示されるので、自分の努力の成果をしっかり可視化することができます。
「今週はこれだけ頑張ったな」とか、「先週よりも時間が減ってるから気を引き締めよう」といった振り返りも簡単にできるんです。
また、保護者の方にもこの情報が共有されるので、わざわざ声かけしなくても「頑張ってるね」と応援の言葉をかけてもらえるのが嬉しいという声も多いです。
視覚的にモチベーションを維持できる仕組みって、やっぱり続けやすさに大きく影響するんですよね。
【不登校】すららの効果的な使い方について紹介します
不登校のお子さんにとって、学習への不安や生活の乱れは避けられない悩みですよね。
無理に学校に戻すのではなく、まずは「自宅で安心して学べる環境」を整えることが大切です。
そんなときにぴったりなのが「すらら」なんです。
すららは、教科の学習だけでなく、子どもの気持ちに寄り添いながら「生活リズムの立て直し」や「自信の回復」にも役立つよう設計されています。
特に、ほめてくれるアニメキャラや、親以外の存在として寄り添ってくれる“すららコーチ”の存在は、不登校の子にとってとても大きな支えになります。
ここでは、すららを不登校のお子さんにどう活用すれば効果的なのか、4つの具体的な方法をご紹介していきますね。
使い方1・「生活リズム作り」に役立てる/朝起きる→学習→休憩…の「ミニ時間割」を作って生活リズムを整えられる
不登校が続くと、夜型生活になったり、生活のリズムが崩れたりしてしまうことが多いですよね。
でも、いきなり早寝早起きを求めてもなかなか難しいもの。
そんなときは、すららを使って“朝の学習”を少しずつ習慣化することで、自然と生活リズムを整えることができるんです。
たとえば、「朝9時に起きて、10時から30分だけすららをやる」といった“ミニ時間割”を作ってみるのが効果的です。
無理に何時間も勉強しようとせず、まずは「決まった時間に起きて取り組む」という行動を定着させることが第一歩。
すららは自分のペースで取り組めるから、プレッシャーも少なく、気軽に続けられるのが嬉しいポイントです。
使い方2・「一人でも安心してできる環境」を整える/自分のペースで、周りを気にせず学べるのがすららの強み
不登校のお子さんの中には、「人と関わるのが怖い」「誰かと比べられるのがしんどい」と感じている子も多いです。
そんな子どもたちにとって、自分ひとりで落ち着いて学べる環境はとても大切。
すららは、まさにそういう子のために作られたような教材です。
アニメキャラと対話する形式なので、誰かに見られることもなく、自分の間違いを笑われる心配もありません。
さらに、自分の好きなタイミングで学習を始められるので、「今日はちょっとだけ」「明日はしっかりやろう」など、心のコンディションに合わせた使い方が可能です。
親もそっと見守ることができるので、干渉しすぎずに安心して子どもをサポートできますよ。
使い方3・「成功体験」を増やして自信を回復/すららの「ほめ機能」を活用する
不登校の子どもが抱えるのは、勉強の遅れだけじゃありません。
多くの場合、「自分はできない」「みんなに置いていかれている」という気持ちが自信を奪っています。
そこで役立つのが、すららに搭載されている“ほめ機能”です。
問題を解くたびにアニメキャラが褒めてくれたり、「がんばったね」と声をかけてくれたりすることで、子どもは「認められている」と実感できるんです。
この“ちいさな成功体験の積み重ね”こそが、自信を取り戻す第一歩。
間違えても怒られないし、できたらしっかり褒めてくれる。
それだけで、子どもは「またやってみようかな」と思えるようになるんです。
学びへの苦手意識をやわらげ、自信を育てる環境が、すららには整っているんですよ。
使い方4・コーチングの活用で「孤立感」を減らす/すららコーチに相談すると、親とは違う「第三者の声」がもらえるので、気持ちの負担が和らぐ
不登校の子どもにとって、最大の悩みは「孤独感」です。
学校に行けないことで、友達と離れ、社会との接点が少なくなってしまう。
そんなとき、すららの“コーチング機能”はとても心強い存在になります。
すららコーチは、学習面のアドバイスだけでなく、子ども一人ひとりの気持ちに寄り添いながら声をかけてくれる“第三者”です。
親には言えない悩みも、コーチには自然と話せることも多いんですよ。
コーチからのメッセージは、子どもにとって「誰かが自分を見てくれている」という安心感にもつながります。
また、親にとっても「全部を自分で抱え込まなくていい」という意味で、精神的な負担がグッと軽くなるはずです。
孤立せずに前を向ける学びの場として、すららはとても心強い味方になってくれますよ。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららを実際に利用したユーザーの評判を紹介します
良い口コミ1・うちの子は、元々タブレットが好きで、ゲーム感覚で学べるところがハマったみたいです。アニメのキャラが優しく教えてくれるので、塾に行くよりも緊張しないし、自分のペースでできるのが良いみたい
良い口コミ2・ADHD気味で集中力が長続きしない子でも、すららはアニメーションやイラストで説明してくれるので理解しやすいです
良い口コミ3・学校に通えない期間が長く、勉強にブランクがありましたが、すららなら自分のレベルに合わせて無理なく進められました。先生の顔を見ずに自分だけのペースで学べるので、安心感があります
良い口コミ4・塾に通う時間が取れなかったけど、すららは家でスキマ時間にできるから便利!部活が忙しくても、夜に少しずつ進めていけるし、テスト対策にも使えるのがいい
良い口コミ5・発達に凸凹があって、書くことが苦手な子ですが、すららはタブレット操作で進められるので、嫌がらずに学習ができています
悪い口コミ1・タブレットで勝手に学んでくれると思っていたけど、低学年の子は一人で進めるのが難しいこともあり、結局そばで見守ることに…。もう少し親が楽できる設計だったらよかったかな
悪い口コミ2・初めは楽しく続けられていたのですが、不登校の子だと一度やる気が下がると放置してしまう…。サポートメールや先生からのアドバイスは来るけど、やっぱり一人だと限界を感じることもあります
悪い口コミ3・高校生用のコースを受講していますが、基礎に時間をかけすぎる印象です。進学校に通っていると、物足りなさを感じるかもしれません
悪い口コミ4・アニメーションで楽しく学べるのはいいけれど、うちの子は飽きるのも早くて…。もう少し、変化に富んだコンテンツがあると良いですね
悪い口コミ5・通塾よりは安いですが、長期間利用を考えるとそれなりに負担感があります。特に兄弟で同時に使う場合は、一人ずつの契約が必要なので、コストはやっぱりかさみます
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの会社概要を紹介します
| 運営会社 | 株式会社すららネット |
| 創業 | 2008(平成20)年8月29日 |
| 本社住所 | 〒101-0047
東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田7階 |
| 従業員数 | 正社員88人、契約社員5人 |
| 資本金 | 298,370千円 |
| 代表取締役 | 湯野川 孝彦 |
| すらら公式サイト | https://surala.co.jp/ |
| すららの講座一覧 | ・3教科(国・数・英)コース
・4教科(国・数・理・社)コース ・5教科(国・数・理・社)コース |
参照: 会社概要 (すらら公式サイト)
【すらら】はうざい!?についてのよくある質問
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
ネット上で「すららはうざい」というキーワードを見かけると、ちょっと不安になりますよね。
でも実はこれ、教材そのものの質というよりは、「保護者や子どもの期待とズレていた」と感じたケースで出てきやすい言葉なんです。
たとえば、親が「タブレットを渡せば勝手にやるはず」と思っていたのに、実際は声かけが必要だったり、子どもが反応しなかったりすると、「面倒」「合わない」と感じてしまうこともあるんですよね。
とはいえ、すららは元々が“無学年式”や“AI学習”といった独特の仕組みを持っているので、合う子にはとことん合う教材でもあります。
導入前にしっかり特徴を理解することで、こうしたネガティブな口コミに振り回されず、自分にとって合っているかを判断できるはずです。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららは、発達障害や学習障害を抱えるお子さんでも安心して取り組めるように設計された教材ですが、実は料金面でもそういったご家庭に配慮された仕組みがあるんです。
具体的には、療育手帳や医師の診断書などの提出があれば「発達障害対応コース」として、通常よりも割安な料金で利用できるケースがあります。
これは、経済的な負担を軽減しつつ、子どもに合った学びを提供するための特別なプランです。
料金が下がるからといってサポートの質が落ちるわけではなく、むしろ子どもの特性に合わせた学習スケジュールやコーチのフォローが丁寧になることも多いです。
気になる方は、公式サイトやサポート窓口で詳細を確認してみると安心ですよ。
関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
実はすららは、不登校の子どもでも「出席扱い」として認められるケースがある教材なんです。
これは文部科学省が定める“特別な事情による出席認定”の基準をクリアしているためで、学校や教育委員会に必要な手続きを行うことで、すららでの学習時間を出席としてカウントしてもらえることがあります。
もちろんすべての学校が対応しているわけではありませんが、実際に全国で多くの実績があるのも事実です。
家庭での学習が認められれば、子どもは精神的な負担を減らしながら学習の遅れを取り戻せますし、保護者としても安心してサポートできますよね。
この制度をうまく活用すれば、学校に戻るきっかけにもなりますし、新しい学びのスタイルとして前向きに取り入れられると思います。
関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららでは、定期的に「入会金無料」や「特典付きキャンペーン」など、さまざまなお得なキャンペーンが行われています。
その際に必要になるのが「キャンペーンコード」です。
使い方はとっても簡単で、入会手続きのフォームに進んだ際に“キャンペーンコードを入力する欄”があるので、そこに正しいコードを入力するだけでOKです。
ただし、有効期限があるコードも多いので、見つけたら早めに使うのがポイント。
また、公式サイトではなく紹介ページや口コミサイトなどに掲載されている限定コードもあるので、しっかりチェックしておくといいですね。
キャンペーンをうまく活用することで、初期費用を抑えつつ、すららの学びをスタートできるのは嬉しいところです。
関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららを実際に使ってみて「ちょっと合わなかったかも…」と感じた場合でも、退会手続きはとてもスムーズに行えるようになっています。
手続きは基本的にWeb上で完結でき、すらら公式サイトのマイページまたはサポートへ連絡を入れることで、簡単に退会申請ができます。
ただし、月の途中で解約しても日割り計算にはならないことが多いので、タイミングを見て「次月の課金前までに退会する」のが安心です。
また、退会前に解約理由を聞かれることはありますが、無理な引き止めはされませんので、その点も安心ですね。
休会制度もあるため、いったんお休みしたいだけのときは、無理に完全退会せずに選択肢を相談してみるのもおすすめです。
関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららでは、基本的に入会金と毎月の受講料以外には大きな費用はかかりません。
紙の教材やプリントを買い足す必要もなく、全てオンラインで完結できるのが魅力です。
必要なのはタブレットやパソコンなどの学習端末くらいで、すでにご家庭にあるものを活用できるなら、追加購入の心配もありません。
もちろん、インターネット環境は必要ですが、特別なアプリや高性能機器は必要ないため、導入のハードルはとても低いんですよ。
シンプルでわかりやすい料金体系なので、後から追加請求があるのでは…という不安もなく、安心して始められるのが嬉しいポイントです。
必要な費用が明確だからこそ、計画的に学習を進めていきやすいですね。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
はい、すららでは、1契約で兄弟姉妹が一緒に使えるという魅力的なシステムがあります。
家庭学習を複数人分申し込もうとすると、どうしても料金がかさんでしまいますよね。
でもすららなら、一つの契約で複数の子どもが利用可能なので、家計にもとても優しいんです。
それぞれの子どもに専用のIDが発行され、学習履歴や進捗管理も個別にできるから、混乱することなくしっかりと管理ができるんですよ。
年齢の違う兄弟でも、それぞれに合った学年・レベルで学習を進められるのも魅力です。
とくに、年子の兄弟や、小学生と中学生が一緒に使うケースでも無理なく対応できるので、家族全体の学習コストを抑えながら、しっかりとサポートが受けられるのが嬉しいですね。
すららの小学生コースには英語はありますか?
すららの小学生コースには、しっかりと英語も含まれています。
しかも、ただ単に単語を覚えるだけでなく、「聞く・読む・話す」といった3技能をバランスよく身につけられる構成になっているのが特徴なんです。
小学生のうちから英語を始めることで、中学校以降の英語学習にスムーズに入れるというメリットもありますし、何よりも「英語=楽しい」という印象を持てるのが大切ですよね。
すららでは、アニメキャラクターと一緒に発音を真似したり、音声を聞いて答える形式など、インタラクティブな仕掛けも豊富。
飽きっぽいお子さんでも夢中になって取り組める工夫がいっぱいです。
早いうちから楽しく英語に触れられる環境があるのは、とても心強いことですね。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららの大きな強みのひとつが「すららコーチ」の存在です。
このコーチは、学習の進め方に迷ってしまったり、子どもがつまずいたときに親身になってサポートしてくれる頼れるパートナーです。
学習計画を立ててくれるのはもちろん、子どもがどの分野で苦戦しているかを把握し、どう進めればいいか具体的なアドバイスももらえるんです。
また、保護者からの相談にも対応してくれるので、「うちの子、このままで大丈夫かな?」といった不安も気軽に共有できるのが安心です。
とくに発達特性のあるお子さんに対しても丁寧なフォローをしてくれるので、家庭学習がうまくいかない時の心の支えにもなりますよ。
コーチがそばにいてくれることで、親も子も学習に前向きに取り組みやすくなりますね。
参照: よくある質問 (すらら公式サイト)
【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材と比較しました
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較まとめ
本記事では、【すらら】というタブレット教材について料金や評判などを比較しました。
結論として、【すらら】には様々な評判や口コミがありますが、利用者によって異なる点があることが分かりました。
料金面では、他の教材と比較して高額であるという声もありますが、その分内容やサポートの充実度が高いという意見も見られます。
また、最悪の噂や不満の声についても、一部の利用者からは出ていますが、全体的には良い評価を受けているようです。
そのため、【すらら】を選ぶ際には、自身やお子さんの学習スタイルや目的に合った教材かどうかを考慮することが重要です。
他の利用者の口コミや評価を参考にしながら、自分に最適な選択をすることが大切です。
さらに、【すらら】を活用することで、お子さんの学習環境や成績向上に役立つ可能性があります。
タブレットを活用した学習は、従来の学習方法とは異なる魅力や効果があるとされています。
そのため、【すらら】を使うことで新しい学習体験や成長の機会を提供できるかもしれません。
【すらら】はうざいという声もあれば、有用であるという意見もあるようです。
最終的には、自身やお子さんの状況に合った教材を選ぶことが重要です。
【すらら】を通じて、充実した学習体験ができることを願っています。